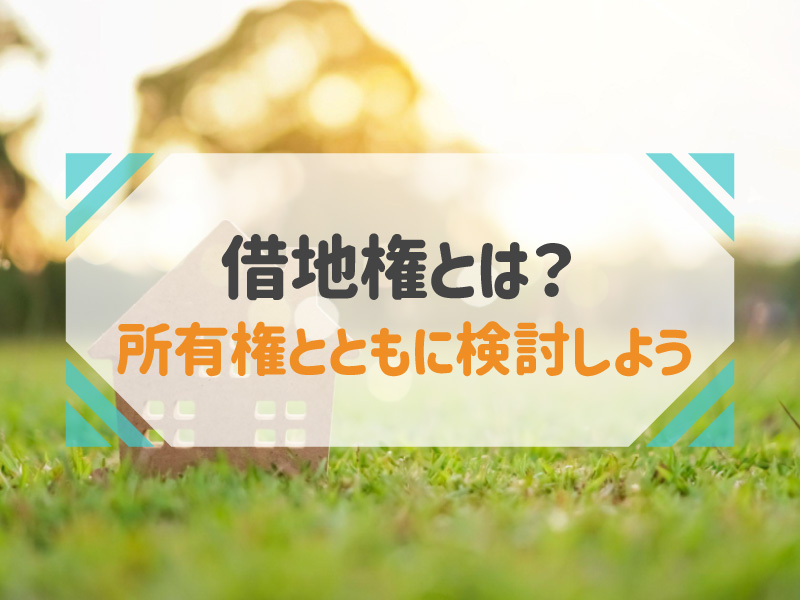土地と建物を購入した場合、完全なる所有権を有します。
対して、土地を借りる場合は借地権が設定されます。
借地権は、文字通り土地を借りる権利であり、購入するよりも安価で土地を利用できます。
ただし、デメリットがあるのはもちろん、借地権がトラブルを起こす場合もあるため正しい理解が重要です。
この記事では、借地権の解説や借地権を得るデメリットなどを解説します。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「IELICO(イエリコ)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
目次
1.借地権とは建物所有目的で土地を借りる権利のこと

借地権(しゃくちけん)とは、建物を所有する目的で土地を借りる権利(地上権または賃借権)のことです。
借地権は地主から簡単に契約を解除できず、借主にとって強い権利であることが特徴となります。
また、「建物を所有する目的」というのがポイントであり、駐車場として利用するために借りる場合は建物を所有しない場合の借地となり、借地権には該当しません。
借地権は建物の所有が前提にあることから、『借地権付き建物』『借地契約後に住居を建てる条件付き』で取引されることがほとんどです。
借地権付き建物とは、土地は貸物、建物は売物として取引される物件で、購入すると借地権と建物の所有権を取得します。
借地権付き建物は、市場価格よりも安く、土地にかかる不動産取得税や固定資産税がかからないなど、支出を抑える面でメリットがあります。
1-1.所有権との違い
所有権とは土地を所有する権利のことです。
所有権の土地は完全に自分のものとなるため、自由に売却や建て替えができるうえ、地代の支払いがありません。
自由度の高い権利ほど価値が高いため、所有権の方が買値、売値は高くなります。
資産価値が高い点、借地権ではしばしば起こりうる地主とのトラブルがない点は大きなメリットです。
1-2.借地権は地上権と賃借権に分かれる
借地権は地上権と賃借権の2種類に分かれます。
地上権は物権と呼ばれる権利に分類され、賃借権は債権と呼ばれる権利に分類されます。
物権は全ての人に対して主張できる権利ですが、債権は原則として契約の相手方に対して主張できる権利であるという違いがあります。
| 比較項目 | 地上権 | 賃借権 |
|---|---|---|
| 地代 | 支払わない契約も可能 | 支払う |
| 譲渡 | 地主への許可は不要 | 地主への許可が必要 |
| 土地への登記義務 | 必要 | 不要 |
1-3.借地権割合とは
借地権割合とは、更地価格に対する借地権価格の割合のことです。
例えば、更地価格が1億円、借地権価格が7,000万円であるときは、借地権割合は70%となります。
借地権割合は、借地権の需要の高い地域ほど借地権価格も高くなることから、高い割合となります。
一般的には住宅地よりも商業地の方が借地権割合は高い傾向にあります。
また、借地権が設定されている土地の所有権のことを底地権(そこちけん)と呼びます。
底地権の価値(評価額)は、土地の価値から割合分を差し引いたものになります。
借地権と底地権をどちらも有せる状態が、完全な所有権といえます。
1-4.借地権は相続も売却もできる
借地権は長期安定的に土地を利用できる権利であることから、有償で取引がなされます。
売ると値段が付くことから一定の資産価値があり、相続税を計算する上での財産にも含まれます。
相続に際して、地主に許可を取る必要はありませんが、遺贈の場合は許可が必要になります。
2.借地借家法による「普通借地権」と「定期借地権」

借地権の種類について解説します。
現在の借地権に関する法律は「借地借家法」と呼ばれ、1992年から施行されたものです。
それより以前の借地権に関する法律は「借地法」という法律でした。
借地借家法では、契約更新のできない定期借地権が創設され、現在広く利用されています。
以下より、借地借家法(新法)における普通借地権と、定期借地権について違いを説明します。
2-1.普通借地権
普通借地権とは、借主が更新を申し出れば更新ができる借地権のことです。
普通借地権の契約期間は30年以上となります。
更新後の契約期間は1回目が20年、2回目以降が10年です。
地主が更新拒絶をするには、正当事由と立ち退き料が必要となります。
正当事由とは、土地を返してもらうのに正当な理由のことです。
正当事由はなかなか認められないため、実質的に地主は更新拒絶をすることがほとんどできません。
つまり、普通借地権では借主の権利が強く守られており、半永久的に土地を借り続けることができます。
そのため、次節で紹介する定期借地権よりも価値が高いと言えます。
普通借地権のメリットとデメリットを示すと下表の通りです。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
2-2.定期借地権
定期借地権とは、更新ができない借地権のことです。
定期借地権には3つの種類があり、それぞれ用途と契約期間の定めが異なります。
| 用途 | 契約期間 | |
|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 制限なし | 50年以上 |
| 建物譲渡特約付き借地権 | 制限なし | 30年以上 |
| 事業用定期借地権 | 事業用に限る | 10年以上50年未満 |
契約期間を満了すると賃貸借契約は終了し、原則、建物を解体し更地で返却する必要があります。(建物譲渡特約付き借地権を除く)
地主にとっては、契約期間が満了すると確実に土地を取り戻すことができ、立ち退き料も必要ありません。
定期借地権は契約満了時に借りる権利が終了してしまうことから、普通借地権と比べて借りる権利は弱いといえます。
よって、定期借地権の資産価値は普通借地権と比べると低いと言えます。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
3.借地権の不動産のメリットとデメリット

普通借地権であれば他人の土地を半永久的に借りることが可能です。定期借地権でも、50年という十分な期間借地権が有効なので、「都合がいい」と感じる方も少なく成りでしょう。
ただし誰にでも都合のいいものではありません。
以下で、借地権を持つメリットとデメリットを確認してみましょう。
【メリット】
借地権の不動産のメリットとして、以下が挙げられます。
- 所有権より安く購入できる
- 長期間利用できる安定した権利が保証されている
- 定期借地権では新規に設定しやすい
【デメリット】
一方、借地権の不動産のデメリットとしては、次が挙げられます。
- 地代が発生する
- 資産価値や担保価値が低い
- 普通借地権では権利金や更新料等の一時金が発生する
借地権は、所有権の土地を購入するよりも安く、限られた予算の中で有力な選択肢となるでしょう。
ただ、購入時の支出が少ないのなら、当然手放すときの収入も少なくあなります。
少なくとも、「資産として土地を持ちたい」と考えている方には、ほとんどの場合で向きません。
4.借地権で生じるトラブル

借地権では、普通借地権の一時金や定期借権の保証金などでトラブルが生じるケースがあります。
この章では借地権でありがちなトラブルについて解説します。
4-1.普通借地権の更新料や建て替え承諾料で揉める
普通借地権では、更新料や建て替え承諾料といった一時金が発生します。
これらの一時金は、契約書に記載されていないことも多く、また、金額も高額であることから地主との間で揉めてしまうことが多いです。
例えば、更新料であれば「年額地代の10倍」、建て替え承諾料であれば「更地価格の3%」が1つの目安とされています。
ただし、これらの目安も決まりではなく、地域や地代等で異なることが一般的です。
なお、契約書に記載がなければ支払いの義務はなく、双方の話合い次第となることが多くあります。
4-2.定期借地権の相続で多額の保証金が返還できなくなる
定期借地権は契約期間が長いため、契約期間中に相続が発生することもあります。
貸主が相続により変更になる場合は、保証金に注意が必要です。
被相続人が契約時に多額の保証金を預かっていると、相続人が契約終了時に、借地人(借主)に保証金を返還できないといったトラブルがあるためです。
契約期間中に相続が想定されるようであれば、相続人と話し合って預かる保証金の額を決めておくことが望ましいでしょう。
定期借地権の保証金も、特に決まりはありません。
預からないこともありますし、預かる場合は地代の6ヶ月分程度としていることが多いようです。
4-3.定期借地権付きマンションの売却価格が著しく下がる
トラブルではありませんが、定期借地権付きマンションは売却時に価格が著しく下がることがあります。
定期借地権付きマンションは、定期借地権が設定されている土地の上に建つマンションのことです、契約満了時には解体し更地で返還されます。
契約期間以上人が住めないため、借地期間の終了に近づくほど需要は減り、価値も下がっていきます。
土地の所有権もないため、一般的なマンションよりも価格が大きく下がります。
定期借地権付きマンションを売却するのであれば、十分に借地期間が残っているうちになるべく早く売ることをおススメします。
この記事のポイントまとめ
- 借地権とは、建物所有目的で土地を借りるための権利です。
詳しくは「1. 借地権とは建物所有目的で土地を借りる権利のこと」をご覧ください。
詳しくは「2.借地借家法による「普通借地権」と「定期借地権」」をご覧ください。
- 所有権より安く購入できる
- 長期間利用できる安定した権利が保証されている
- 定期借地権では新規に設定しやすい
デメリットは以下の点です。
- 地代が発生する
- 資産価値や担保価値が低い
- 普通借地権では権利金や更新料等の一時金が発生する
詳しくは「3.借地権の不動産のメリットとデメリット」をご覧ください。
- 普通借地権で更新料や建て替え承諾料で揉めることがある
- 定期借地権の相続で多額の保証金が返還できなくなることがある
- 定期借地権付きマンションの売却価格が著しく下がることがある
詳しくは「4.借地権で生じるトラブル」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点