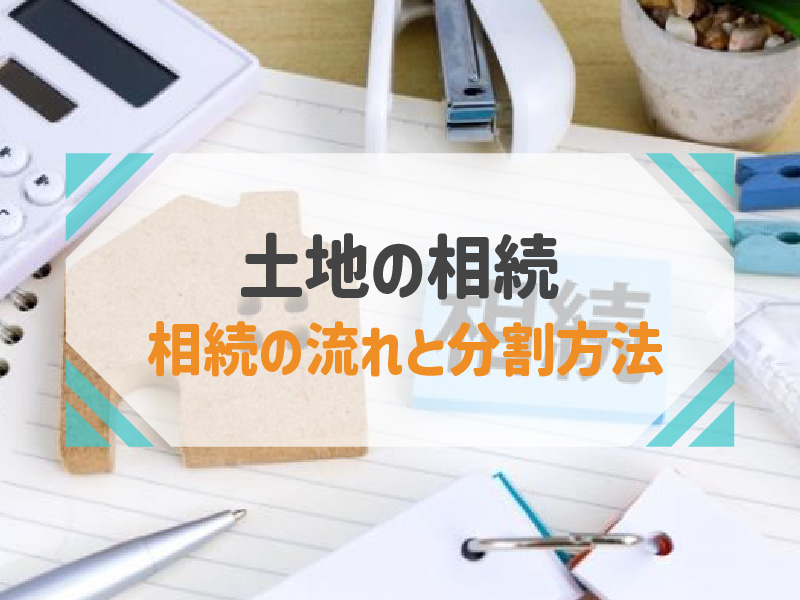土地の相続をスムーズに行うためには相続の流れや分割方法、費用や税金について知っておくことが大切です。
本記事では「土地」相続の方法について
- 土地相続の流れ
- 土地の分割方法
- 相続登記
- 相続税の計算方法
- 節税方法
などを解説します。
近い将来に相続を控えているならば、あらかじめ「何が必要か」を踏まえ、相続時に適切な行動を取れるようにしておきましょう。
- 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格”を見つけましょう
- 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
目次
土地を相続する際の流れ

土地を相続する際の流れでは、上記のフローに従って相続を進める必要があります。
1つずつ解説していきましょう。
Step1】相続人の確認
土地相続の手続きを進めるためには、まず相続人の数を確認しなければなりません。原則として、遺産分割をするためには相続人全員の許可が必要になるからです。
相続人の数を調べるには、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、養子や婚外子の有無を確認します。
また、法律で相続の優先順位が決められており、誰でも相続人にはなり得ないので注意が必要です。
相続人の順位は以下のように決定しています。
- 第一順位:直系卑属(子ども、子どもが既に死亡していれば孫)
- 第二順位:親(直系尊属)
- 第三順位:兄弟・姉妹
※配偶者の優先順位は常に最も高い
順位は、故人の家族状況によって変動します。たとえば、故人に子どもがいれば親は相続人になれず、子どもがいなければ親が相続人になるので兄弟姉妹は相続人になれません。
ただし、配偶者は必ず相続人になります。また、子どもが亡くなっている場合でも、その子ども(孫)による代襲相続も考えられます。
相続人の数、順位、代襲相続を踏まえ、相続人数を確定しましょう。
Step2】相続財産の調査
相続が発生したら相続財産を調査する必要があります。
相続財産の調査とは、「財産がどれくらいあったのか」を調べることです。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 土地や建物などの不動産
- 預貯金や現金
- 自動車や船舶などの動産
- 有価証券
- 宝飾品など
一方で、下記のような故人のマイナスの資産も調べなければなりません。
- 借金や借り入れ
- 負債
- 損害賠償責任など
以上の有無を確認してプラスの資産とマイナスの資産を合算し、総額を調べます。土地や建物など不動産など金額が定められていないものは、評価額を調べる必要があります。
Step3】遺言書の確認
遺言書は故人が生前に遺した意思表示で、相続時にはその有無が重要です。
もし、生前に「実家は長男に継がせたい」口約束をしていても、遺言書にしていなければ法律上の効果はありません。
そして、遺言書があった場合は、遺言書の効力がポイントになります。「遺言が改ざんされている」「故人の自筆かどうか分からない」などの物言いが入る可能性もあるからです。
遺言には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 |
|
|
| 公正証書遺言 |
|
|
| 秘密証書 |
|
|
検認とは遺言書を発見した人や保管していた人が、家庭裁判所に遺言書を渡し、相続人立会のもとで、開封、内容の確認をする作業です。
遺言書を確認した結果、遺言内容に問題なければ相続手続きを進めます。
検認の結果、問題があると感じている相続人がいる、もしくは遺留分を侵害している内容ならば遺言書の無効申立をして、裁判所の判断を仰ぎます。
遺言書の内容が有効だと認められれば、その内容のとおり相続を進めて、無効だと認められれば遺産分割協議を進めます。
Step4】遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合うことが遺産分割協議です。
遺産分割協議には法律上の期限はありません。ただし、相続税には10か月の納税期限があります。
そのため、10か月より遺産分割協議が長引く場合には、暫定的に法定相続分で相続税を申告し、遺産分割協議後に修正申告などで相続税を精算します。
遺産分割協議をしなければ財産は相続人の共有の持ち物になります。共有状態では財産が活用しづらく、一部の相続人が財産を使い込んでしまう可能性があります。
また、相続税の控除など特例を受けられなくなるため、相続内容が決まっていない状態で遺産分割協議をしないことはデメリットしかありません。
遺産分割協議で相続する内容が決まれば、相続人が合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
作成された遺産分割協議書をもとに、相続登記が進められるようになります。なお、遺産分割協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用し、裁判所の審判を仰ぐことも可能です。
Step5】相続登記
土地や建物など不動産の相続人が決まったら、名義変更のために相続登記します。
相続登記して名義変更しなければ、賃貸や売買の活用ができません。また、2024年4月から相続登記が義務になり、理由もなく未登記の状態でいると10万円以下の過料が科せられるペナルティが発生します。
現在、未登記の物件に対してもさかのぼって相続登記が義務化されるので、未登記の物件を所有しているのならば登記手続きを進めましょう。
一般的に手続きは司法書士に依頼し、登記申請を代行してもらいます。
Step6】相続から10か月以内に相続税の申告
相続が発生した日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要です。
申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署で、以下の方法にて納税します。
- 税務署の窓口
- 金融機関から振り込み
- コンビニで支払い(納付額30万円以下)
- インターネットでクレジット決済(納付額が1,000万円以下)
相続税を期限内に納税しなければ「延滞税」が加算されます。
延滞税は納付期限から2か月以内は最大で年利7.3%、納付期限から2ヶ月を過ぎたら最大で年利14.6%が納税額に対して日割りで加算されます。
相続税額にもよりますが、大きな金額になり得るので期限を守るようにしましょう。
相続した土地の分け方は4種類
相続した土地を分割する方法は以下の4種類です
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
それぞれのどのような特徴があるのか解説します。
現物分割
現物分割は財産の種類を変更しないで相続する方法です。
土地や株式を売却して現金に換えず、長男は土地、次男は預貯金といったような分け方です。土地の現物分割では、相続人同士で物理的に土地を分割して相続することを指します。
たとえば「300坪の土地を3人の相続人で100坪ずつ分割して相続する」といった考え方です。
土地が広ければ分割してそれぞれで活用でき、共有持分もないので自分の意思で自由に土地を利用できます。
一方で、以下の例のように現実的に土地を分割できない場合には、原則的に使えません。
- 敷地が狭い
- 分割することで著しく価値が減少する(変形地形、未接道地の発生など)
また、土地の価値で等分するのか、土地の面積で等分するのかなど考えなければならないことも多数あります。
たとえば、上下水管の引き込みの有無や敷地内の高低差だけでも土地にかかる費用が変わるため、現物分割ではトラブルの発生も懸念されます。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して現金で分け合う方法です。土地を売却すれば現金で公平に分けられるので、相続人が利用しない土地には取り入れやすい分割方法です。
相続人が遠方に住んでいる、既に住宅を所有していて土地を利用する予定がない、土地が広大で手に余る、などのケースでも利用されるでしょう。
換価分割は相続人同士が公平に分割できる一方で、売却に手間や費用がかかることも想定されます。
- 仲介手数料
- 印紙代
- 譲渡所得税
- 測量費など
費用だけでもこれだけの種類が必要なので、換価分割をする際には事前に売却価格などを把握して予算を検討しておく必要があります。
代償分割
代償分割は土地を相続した相続人が、他の相続人に対して超過分の現金を支払う方法です。
物理的に分けられない土地などで利用されます。
たとえば、評価額が3,000万円の土地を3名の相続人で分割するとき、長男が土地を相続し、長男が現金を1,000万円ずつ次男と三男に支払います。
土地を売却する必要もなければ、公平性も保てる分割方法です。しかし、土地を相続する相続人には資金力が必要で、土地の評価額を巡って相続人同士でトラブルが発生する可能性もあります。
共有分割
共有分割は土地を共有する形で相続する方法です。売却手続きや現金のやり取りをする必要がなく、手がかからないのが特徴です。
相続人が3人いれば3分の1ずつ持ち分を持って土地を利用します。デメリットとしては、もし相続人の1人が土地を売却したいと考えても、他の相続人の許可が得られなければ売却できないことがあります。
また、共有持分のままで更に相続が進むと、従兄弟同士で共有する可能性も出てくるため、権利関係が複雑になることが想定されます。
土地の相続登記にかかる費用
2024年4月から義務化される相続登記は、以下2つの手続きが必要です。
- 登録免許税
- 司法書士報酬
どちらも司法書士に依頼するのが一般的ですが、費用が発生します。
登録免許税
登録免許税は、登記手続きを申請する際に国に納税する税金です。
登記手続きの申請書類に収入印紙を貼り付けて提出することで納税します。収入印紙は郵便局や法務局で購入できますが、司法書士に登録免許税額を預け、手続きと合わせて納税処理してもらうことが一般的です。
税額は以下の計算方法で算出します。
固定資産税評価額×0.4%
もし、遺言によって相続人以外が土地を相続した場合には、税率が2%に上がります。
司法書士への依頼報酬
相続登記を司法書士に依頼する場合には、司法書士への報酬も必要です。そして、司法書士への報酬には消費税も課税されます。相続登記の報酬相場は6万円から10万円程度です。
相続登記の必要書類と合わせ、登記費用として登録免許税と司法書士報酬を合わせて支払います。
土地を相続した場合の相続税の算出方法
土地を相続した場合、以下の計算式で相続税額を求めます。
- 土地を含めた遺産総額-基礎控除額-葬儀費用
- 1で出た課税遺産総額を法定相続分で按分する
- 2で出た数字に相続税率を掛けて合計する
- 3で出た税額を相続割合に応じて計算し、負担する
遺産総額は不動産や預貯金、有価証券などプラスの財産と、借金や負債などマイナスの財産を差し引き、相続時精算課税制度などの適用があればそれも合算します。
基礎控除とは相続人数によって変わる控除額です。基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
基本額3,000万円+相続人数×600万円
仮に相続人が3名いれば4,800万円が基礎控除額になるので、遺産総額が4,800万円以下ならば相続税は課税されません。
また、相続割合とは相続した遺産額の割合のことを言います。
相続税の計算方法について、以下の例を元にシミュレーションします。
- 土地:4,000万円
- 株式:3,000万円
- 預貯金:3,000万円
- 遺産総額:1億円
- 相続人:配偶者、子供2人
- 葬儀費用:200万円
上記の条件で相続する場合、相続する遺産の金額は以下の通りです。
10,000万円-4,800万円(基礎控除額)-200万円=5,000万円(課税遺産総額)
5,000万円のうち、2,500万円が配偶者の法定相続分、1250万円ずつが子ども2名の法定相続分です。
そして、税率は以下の速算表を用いて税額を計算します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
参考:国税庁ホームページ「相続税の税率」
上記の表に基づいて計算した場合、配偶者と子供2人それぞれの相続税は以下の通りです。
- 配偶者の税額=5,000万円×20%-200万円=800万円
- 子どもの税額=1,250万円×15%-50万円=137.5万円
- 税額合計=800万円+137.5万円+137.5万円=1,075万円
以上の計算により1,075万円が相続税額になり、このあとは相続割合によって負担する相続税額を求めます。
土地相続の税金を下げる「小規模宅地の特例」とは
土地相続において、条件を満たすと「小規模宅地等の特例」が適用され、
土地評価額が最大80%減額されます。
前項の相続税額計算で土地評価額が80%減額された場合は、相続税額の合計が180万円になるので、とても影響の大きい控除です。
小規模宅地等の特例には3種類の特例があります。
| 土地の種類 | 限度面積 | 減額率 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等の特例を利用するためには、故人が住んでいた土地を相続し、相続人は以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者(相続人)
- 故人と同居していた相続人
- 故人と別居していて3年以上借家に住んでいる相続人
出典:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
3年以上借家に住んでいる相続人の条件を満たすためには、配偶者や故人と同居していた相続人がいないことが前提です。
同居については住民票が置いてあるだけでは条件を満たせず、同居していた実勢が求められます。
特定事業用地等の特例を利用するためには、以下の条件があります。
- 相続が始まる3年前よりも前からその土地で事業を営んでいる
- 相続人が相続税の納付期限までに事業を継承している
最後に貸付事業用用地等の特例を利用するためには、以下の条件があります。
- 相続開始前からその土地で不動産貸付業を営んでいる
- 相続人が相続税の納付期限まで不動産貸付業を継続している
不動産貸付業と認められるための目安は、10室以上のアパートやマンションで賃貸経営をしている必要があります。
その他にも不動産貸付業に認められる要件は細かく分かれているので、専門家などに相談して確認しましょう。
以上の「小規模宅地等の特例」の条件を満たしたうえで、相続税の申告をすることで特例が適用されて控除を受けられます。
相続人が複数いる場合は売却も検討する
複数の相続人がいる場合には、売却して換価分割することでトラブルを抑制できます。
なぜなら、土地や不動産の相続では、分割方法や土地評価額、土地評価方法ですらトラブルの原因になる可能性があるからです。
相続が発生してからの売却でも、将来的な相続で争点となりそうな不動産がある場合には、事前に売却を検討しておくことも相続対策になります。
相続後の土地を売却したい方は、一括査定サイト「IELICO(イエリコ)」を使って査定を依頼してみましょう。

「IELICO(イエリコ)」は、国内初の不動産の一括査定サービス「不動産売却HOME4U(ホームフォーユー)」での20年の実績を元にした審査基準を設けているので、利用者にとって最適な不動産会社を提案してくれます。
査定を依頼する会社は厳選された優良企業2,100社の中からお客様の条件にあった会社を「IELICO(イエリコ)」がピックアップし、その中から最大6社まで選択することができます。
その他、12,500件以上の口コミから、自分に合う不動産会社を見つけることが可能です。査定を依頼する会社を探すなら、「IELICO(イエリコ)」をぜひご活用ください。
土地を手放したい場合は「相続土地国庫帰属制度」を活用する
土地を手放す方法のひとつに「相続土地国庫帰属制度」があります。
土地が管理されないまま放置され、いずれ所有者不明の土地になってしまうより、国庫に帰属させて管理・活用されることを目的としている制度です。
令和5年4月27日から始まる制度の利用条件は、以下の通りです。
【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
この制度の条件を満たしていれば、書類をそろえて土地の所在地を管轄する法務局に申請します。
審査に通れば負担金を納付することで土地が国庫帰属になります。これからの制度ですが、売却することが難しそうな土地ならば、一度検討してみることをおすすめします。
土地相続に関するポイントをおさらい
小規模宅地等の特例の条件を満たした場合は、以下の控除が受けられます。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
詳しくは「5.土地相続の税金を下げる「小規模宅地の特例」とは」をご確認ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2025年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 2025年問題まであと2年!不動産は本当に大暴落するの?今後の不動産売却のタイミングは?
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点
- 不動産売却で確定申告を行う手順・必要書類・税金の計算方法