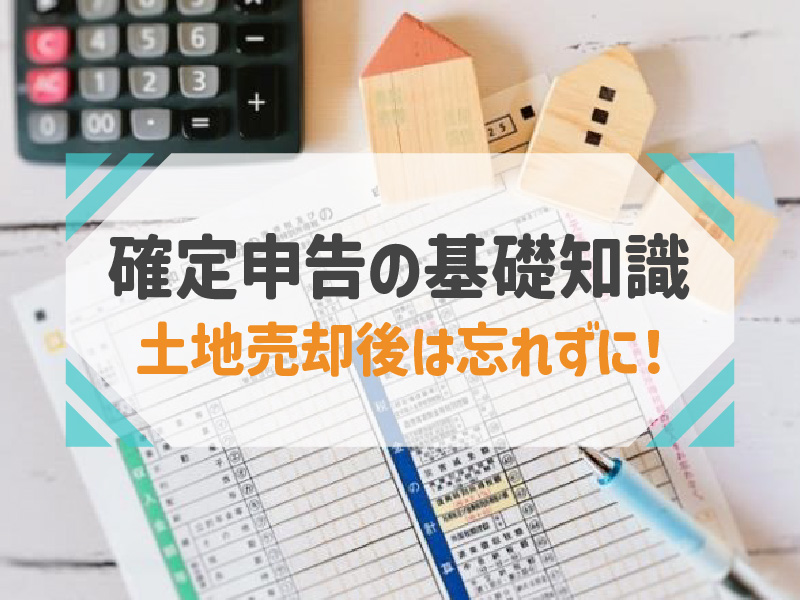土地売却をした後には確定申告が必要となる可能性があります。
土地の売却が初めての場合「どんな時に確定申告が必要なのか」「税金はどうやって計算するのか」「申告方法がわからない」など、不安に思う方もいるでしょう。
この記事では、土地売却の確定申告について
- 確定申告が必要なケース
- 確定申告に必要な「譲渡所得」の計算方法
- 確定申告の期限
- 必要な書類
- 申告方法
など、覚えておきたい基本的な知識について解説します。
確定申告の流れや、税金がお得になる特例についても解説しているので、最後までお読みいただくことで、確定申告が初めてでも安心して手続きを進められるでしょう。
- 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格”を見つけましょう
- 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
目次
土地売却後に確定申告が必要かは譲渡所得で決まる

土地の売却で確定申告が必要かどうかは、譲渡所得で判断します。
譲渡所得とは、売却して得た利益です。譲渡所得が発生した場合には税金が課されるので、確定申告をしなければなりません。また、購入額より売却額が少ないなど利益が出なかった場合は、確定申告をすると税金が還付されます。
譲渡所得の確定申告については、まず以下3点について理解しておきましょう。
- 譲渡所得の計算方法
- 譲渡益が発生する場合
- 譲渡損失が発生する場合
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、以下の計算式で算出できます。
譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)
譲渡所得は土地などの不動産を売却した金額ではなく、売却によって得た利益のことをいいます。
譲渡所得の計算方法は、土地を売却した譲渡価格から、最初に土地を購入した際の価格である取得費を引き、さらに仲介手数料や税金など土地売却にかかった費用を引けば算出できます。
特別控除の対象になる場合は、控除額も引きます。
取得費とは、土地の購入にかかった費用や改良などの費用の総額です。
譲渡費用とは仲介手数料など、土地を売るために直接かかった費用のことをいいます。
取得費を証明する書類が残っていない場合など、取得費が不明な場合は売却代金に5%をかけた金額を取得費とすることができます。
譲渡益が発生する場合
譲渡所得を計算してプラスであれば、確定申告をして所得税を納めなければなりません。
マイホーム売却の特例(3000万円特別控除)や取得費加算の特例など、特例を利用する場合も確定申告が必要です。
譲渡損失が発生する場合
譲渡所得がマイナスで損失が発生した場合は、確定申告が不要です。
ただし損失が生じた場合の確定申告では、譲渡所得以外の給与所得や事業所得などと相殺して、税金の負担を軽減できる可能性があります。
また、損益通算しても大きな損失が残る場合は譲渡損失の繰越控除の対象となり、最長4年間は所得税や住民税の負担が軽減されますので、損失が発生した場合も確定申告することをおすすめします。
確定申告の期限はいつまで?

確定申告の期限は、土地を売却した翌年の3月15日です。
土地を売却して譲渡所得が発生した場合には、翌年の2月16日から3月15日の期間に確定申告をしなければなりません。
譲渡所得が発生しているのに確定申告をしない場合にはペナルティがあり、無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、納付が必要な税額が50万円までは15%、50万円を超える部分には20%が本来の税額に加算されます。
ただし、1日でも期限をオーバーすればペナルティの対象となるわけではなく、期限から1ヶ月以内に自発的に確定申告をした場合には無申告加算税が課されません。
その他にも、期限内に申告する意思があったと認められれば無申告加算税が課されることはありません。
ただし、無申告加算税が課されないケースでも、期限が過ぎてからの確定申告には「遅延税」が課されますので、忘れずに期間内に申告しましょう。
土地売却後の確定申告で必要な書類

土地を売却した後の確定申告では、以下の書類が必要です。
- 確定申告書B
- 確定申告書第三表(分離課税)
- 譲渡所得の内訳書
- 売却した際の売買契約書
- 譲渡費用証明のための領収書
- 土地を購入した際の売買契約書
- 取得費を証明するための領収書
- 本人確認書類
- 源泉徴収票
どのような書類なのか、ひとつずつ解説します。
確定申告書B
確定申告書Bは確定申告書の第一表と第二表にあたる書類で、申告する人の収入や控除、支払わなければならない税額などを記入します。
確定申告書第三表
確定申告書第三表は、土地売却で利益が出た場合に必要な書類です。
譲渡所得の内訳書
譲渡所得の内訳書は4枚あり、譲渡所得の金額を申告しますが、譲渡損失がある場合には必要がない場合もあります。
売却した際の売買契約書
売却した際の売買契約書は譲渡価格の証明に必要です。添付して提出するのでコピーしておきましょう。
譲渡費用証明のための領収書
譲渡費用証明のための領収書は、仲介手数料や印紙税など売却にかかった費用を証明するためのものです。
建物を取り壊した場合には、工事の費用も譲渡費用として計上します。
土地を購入した際の売買契約書
土地を購入した際の売買契約書は、購入した金額を証明するために必要です。
相続した土地の場合は、被相続人が購入した際の売買契約書を用意してください。
取得費を証明する領収書
取得費を証明する領収書は仲介手数料や税金、登記申請を依頼した司法書士への報酬など、土地を購入・取得するためにかかった費用を証明するための書類です。
本人確認書類
本人確認書類はマイナンバーカードがあれば、両面をコピーして提出します。
マイナンバーカードがない場合には、マイナンバーの通知書や住民票など個人番号が記載された書類1点と、運転免許証やパスポートなどを1点コピーして添付してください。
源泉徴収票の提出は不要ですが、サラリーマンなど給与所得者は所得や税額を申告書に記入する際に使用します。
土地売却後の確定申告のやり方

土地を売却した後の確定申告は、下記の手順で進めていきます。
- 適用できる特例・控除を調べる
- 必要な書類を準備する
- 税務署に確定申告の書類を提出する
- 所得税を納税する
ひとつずつ詳しく解説します。
適用できる特例・控除を調べる
土地を売却する際に適用できる特例・控除がいくつかあるため、どれを利用できるのか調べましょう。
受けられる特例によって、納める所得税の金額が変わるなど違いがあるので、売却活動を本格的にスタートする前に調べておくことをおすすめします。
土地の売却時に適用できる特例・控除は以下の3つです。
- 3,000万円の特別控除
- 特定居住用財産の買換え特例
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
売却で利益がある場合の特例が、3,000万円の特別控除です。特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、損失があった場合に受けられます。
3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除は、土地を売却して得た利益から3,000万円を差し引ける特例です。
利益が3,000万円以下の場合は、この特例を受ければ3,000万円までの譲渡所得は非課税となります。
特例を受けるための要件は以下の通りです。
- 自分が居住している建物、または建物+土地を売却した場合
- 過去に居住していた場合は、住まなくなった日から3年が経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 建物を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内に土地譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 建物を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、貸駐車場などの用途で使用していないこと
- 親子など近親者への売却ではないこと
特例を受けるためには、一般的に以下の書類が必要です。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
- 売却した土地の全部事項証明書
- 住民票の写し
特定居住用財産の買換え特例
特定居住用財産の買換え特例は、マイホームを売却した際に買換え資産を購入した場合に、売却した不動産よりも買換えた不動産のほうが高額な場合に適用されます。
特例が適用されると課税されませんが、税金を免除されるわけではなく繰り延べされる制度です。
特例を受けるための要件は以下の通りです。
- 自分が居住している建物、または建物+土地を売却した場合(居住・所有ともに期 間が10年を超えること)
- 過去に居住していた場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 建物を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内に土地譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 建物を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、貸駐車場などの用途で使用していないこと
- 親子など近親者への売却ではないこと
- 買い換える建物の床面積は50㎡以上で、土地面積は500㎡以下であること
- 建物を売却した年の前年から翌年までの3年の間に居住する物件を買い換えること
- 買い換える物件が中古住宅の場合は、取得の日以前25年以内に建築されているか、一定の耐震基準を満たしていること
出典:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」
特例を受けるために必要な書類は以下の通りです。
- 譲渡所得計算明細書
- 譲渡に係る売買契約書の写しなど、譲渡に係る額が1億円以下であることを証明するもの
- 譲渡した不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し(譲渡日から2ヶ月経過後に譲渡した資産のある市区町村から交付されたもの)
- 買換資産の明細書
- 売買契約書など買換資産の購入金額が明らかになる書類
- 買換不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し(買換資産の所在地のもの)
- 買換資産が耐火建築物の中古住宅である場合で、取得日から25年以内に建築されたものでないときは、耐震基準適合証明書・住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書
特定居住用財産の買換え特例は、2023年12月末で終了予定なので気をつけてください。ここで紹介した書類は一般的な場合に必要なものなので、さらに書類を求められるケースもあります。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除は、適用を受けることで「損益通算」と「繰越控除」を受けられます。
損益通算は不動産売却における損失を他の所得と合算でき、繰越控除とは損益通算してもなお損失が残る場合に翌年以降3年間繰り越せることです。
特例を受けるための要件は以下の通りです。
- 自分が居住している建物、または建物+土地を売却した場合
- 過去に居住していた場合は、住まなくなった日から3年が経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること(取り壊した場合は取り壊した年の1月1日時点)
- 建物を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内に土地譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 建物を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、貸駐車場などの用途で使用していないこと
- 居住していた物件を売却した売買契約日の前日時点で、その物件の償還期間10年以上の住宅ローン残高が残っていること
- 居住していた物件の譲渡価額(売却価格)が、上記の住宅ローン残高を下回っていること
出典:国税庁「No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」
特例の適用には、一般的に以下の書類が必要です。
- 譲渡所得計算明細書
- 譲渡に係る売買契約書の写しなど、譲渡に係る額が1億円以下であることを証明するもの
- 譲渡した不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し(譲渡日から2ヶ月経過後に譲渡した資産のある市区町村から交付されたもの)
- 買換資産を取得予定の場合は、買換資産の明細書
確定申告の際に、すでに買換資産を取得している場合には更に必要となる書類があります書類を準備する前に、管轄の税務署に相談することをおすすめします。
必要書類を準備する
土地の売却による確定申告では、以下の書類が必要です。
- 確定申告書B
- 確定申告書第三表(分離課税)
- 譲渡所得の内訳書
- 売却した際の売買契約書
- 譲渡費用証明のための領収書
- 土地を購入した際の売買契約書
- 取得費を証明するための領収書
- 本人確認書類
- 源泉徴収票
特例を受ける場合には、上記の書類に加えて特例ごとに必要な書類を準備しなければなりません
税務署に確定申告書を提出する
確定申告に必要な書類の準備が整うと、税務署に確定申告書を提出します。提出の方法は主に3つの方法があり、以下の通りです。
- e-taxで申告
- 所轄の税務署に郵送
- 税務署の窓口に提出
e-Taxで申告する
e-taxはスマホやPCなどを使い、インターネットで申告する方法です。インターネットが使える環境であればどこからでも、24時間いつでも申告ができるのがメリットです。確定申告書を税務署に取りに行かなくても良いので、忙しい人にもおすすめです。
申告書に正しく記入できるか不安な人も、指示通りに順番に記入して進めていけるので、問題ないでしょう。
所轄の税務署に郵送する
郵送でも確定申告はできます。ポストに投函するだけなので、忙しい人には便利な方法です。
申請書類は、税務署に確定申告書を取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロードしましょう。
管轄の税務署を調べるには、国税庁の検索ページで住所や地図などから検索できます。。
税務署の窓口で提出する
税務署の窓口に直接持って行き、提出できます。また税務署の開庁時間は平日8時30分~17時までですが、受付時間外でも、時間外収受箱に投函すれば提出できます。
確定申告期間中は相談コーナーが設けられているので、記入方法が分からない場合にはひとつひとつ丁寧に教えてもらえるので安心です。ただし、申告期限直前だと行列は必至なのでかなりの時間を要します。時間に余裕をもって訪れてください。
所得税を納税する
納税額が確定すると、所得税を納税します。納税の期間は確定申告と同じで、原則2月16日から3月15日です。納付する場所は税務署の会計窓口または金融機関で、専用の納付書を使用して納めます。
事前に手続きをしておくと口座振替も可能で、銀行口座から引き落とされるのは4月20日頃です。口座振替にするには、振替納税依頼書を税務署に提出しておかなければなりません。
- 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格”を見つけましょう
- 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
土地売却後の確定申告は余裕を持って準備しよう

土地売却後の確定申告ではさまざまな書類が必要なので、余裕を持って準備を始めましょう。
準備が大変なだけでなく、期間が決まっているために、期限が近づいてから準備を始めると間に合わなくなる可能性があります。
書類によっては取得まで時間がかかるケースもあるので、売却活動を開始する前に本記事で解説した必要書類や税金特例・控除などを把握し、活動と平行しながら準備を進めるとよいでしょう。
土地売却時の確定申告に関するポイントをおさらい
土地売却で譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。また損失が発生した場合も税金特例を適用するためには確定申告をしなければなりません。
詳しくは「1.土地売却後に確定申告が必要かは譲渡所得で決まる」をご確認ください。
土地売却後の確定申告では以下の書類が必要です。
- 確定申告書B
- 確定申告書第三表(分離課税)
- 譲渡所得の内訳書
- 売却した際の売買契約書
- 譲渡費用証明のための領収書
- 土地を購入した際の売買契約書
- 取得費を証明するための領収書
- 本人確認書類
- 源泉徴収票
詳しくは「3.土地売却後の確定申告で必要な書類」をご確認ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点