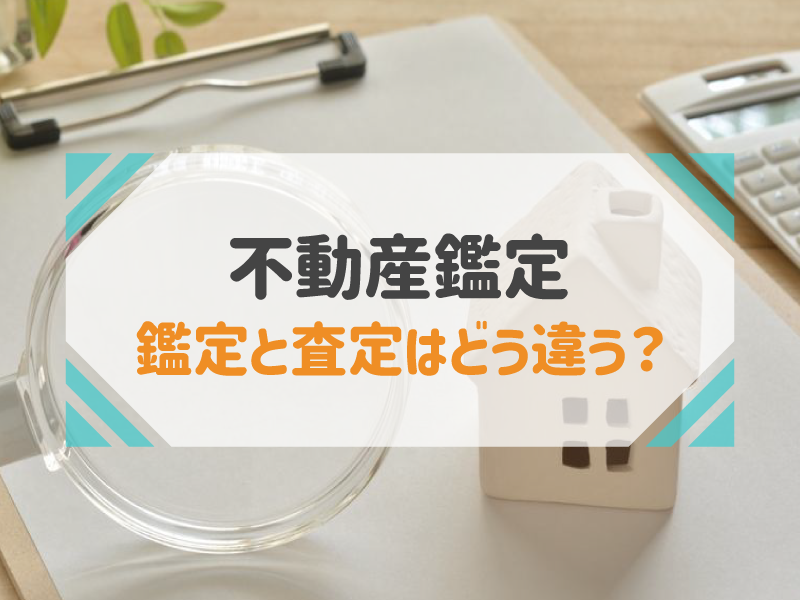不動産を売却する際などには、不動産の価値を知る必要があります。
ただ、『不動産鑑定』や『不動産査定』といった異なる算定方法があるため、どの方法をとるべきか分からない方も少なくありません。
そこでこの記事では、不動産鑑定とは何で、どんな場面で、どんな人に必要かを詳しく解説します。
不動産鑑定を正しく理解し、状況に応じて『鑑定』か『査定』かを正しく選択できるようになりましょう。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「IELICO(イエリコ)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
不動産鑑定とは【仕組みをわかりやすく解説】
不動産鑑定とは、土地や建物といった不動産の正確な価値を評価するための鑑定のことです。
国家資格である不動産鑑定士だけが鑑定を行えます。
この章では、不動産鑑定の特徴を以下の3つに分けて解説します。
- 不動産鑑定士の有資格者が行う
- 不動産鑑定と不動産査定との違い
- 不動産鑑定でかかる費用
詳しく見ていきましょう。
不動産鑑定士の有資格者が行う
不動産鑑定は、不動産鑑定士だけが行えます。
不動産鑑定士の資格試験は非常に難関で、合格後も1~2年にわたる実務研修を行い、国土交通大臣の認可を受け不動産鑑定士となります。
参照:「不動産の鑑定評価に関する法律」第2章第3条
不動産鑑定士が行う鑑定は、非常に厳格で精度が高く、以下3つの方法で算出されます。
- 取引事例比較法:類似物件の取引事例から価格を算出
- 収益還元法:将来生み出すと予想される利益から価格を算出
- 原価法:再度建築した場合の原価から経年劣化分による減額を加味して価格を算出
上記の3つの手法については、4章「不動産鑑定の3つの方法」で詳しく説明しています。
不動産鑑定と不動産査定との違い
不動産の価値を評価するもうひとつの方法に「不動産査定」があります。
「不動産査定」と「不動産鑑定」との違いは以下の通りです。
| 不動産鑑定 | 不動産査定 | |
|---|---|---|
| 依頼先 | 不動産鑑定士 | 不動産会社 |
| 費用 | 有料 | 無料 |
| 期間 | 数週間 | 数日 |
不動産鑑定は国家資格である不動産鑑定士の資格を有する者が不動産の鑑定評価に関する法律に基づき不動産の適正価格を示すものです。
正確性が高く、税務署や裁判所、銀行などの第三者に対して適正な価格を占めす必要がある場合にも効果的な価格を算出してくれます。
不動産査定は不動産会社がどのくらいの価格で売れるのかを独自に判断・算出したものです。
査定の精度は鑑定ほど高くはありませんが、不動産の現況と売却事例等を用いて算出するため、売買における適正価格を知ることができます。
不動産査定の流れは以下の記事で詳しく解説しています。
不動産鑑定でかかる費用
不動産鑑定は鑑定士への報酬が発生する、有料の評価方法です。
不動産鑑定でかかる費用は不動産鑑定士によって異なりますが、基本的には国土交通省の定めるガイドラインをもとに決められています。
そのため、価格のほとんどは不動産の評価額によって変動します。
国土交通省・中央用地対策連絡協議会が発表している「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準について」から、目安の費用を確認していきましょう。
| 評価額 | 宅地または建物の所有権 | 自用の建物及びその敷地の所有権 |
|---|---|---|
| 500万円まで | 16万1,000円 | 21万円 |
| 1,000万円まで | 16万1,000円 | 23万6,000円 |
| 1,500万円まで | 17万4,000円 | 27万5,000円 |
| 2,000万円まで | 18万1,000円 | 27万7,000円 |
| 2,500万円まで | 19万9,000円 | 30万1,000円 |
| 3,000万円まで | 21万1,000円 | 32万5,000円 |
| 4,000万円まで | 22万9,000円 | 36万2,000円 |
| 5,000万円まで | 25万3,000円 | 39万8,000円 |
| 6,000万円まで | 27万7,000円 | 42万2,000円 |
| 8,000万円まで | 31万3,000円 | 45万8,000円 |
| 1億円まで | 35万1,000円 | 49万6,000円 |
「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準について」より一部抜粋
不動産鑑定が必要な場面

不動産鑑定が具体的にどのような場面で必要なのか把握しておきましょう。不動産鑑定が必要な場面は主に以下の4つです。
- 相続するとき・されるとき
- 査定が困難な不動産を売買するとき
- 不動産を担保にするとき
- 離婚で財産分与するとき
それぞれの場面について詳しく説明していきます。
相続するとき・されるとき
相続時に遺産分割をする際、不動産鑑定をすると公平な遺産の振り分けができます。
例えば、遺産が4,000万円の不動産のみ、相続人が4人いるとします。不動産を1人の相続人が相続した場合、残りの3人は何ももらえません。それでは不公平なので、不動産を相続した相続人が他の3人に対してお金を支払って精算します。
このような遺産の分割方法を代償分割と呼びます。
不動産の遺産分割は、他の不動産評価額でも行えますが、相続人それぞれの事情で参考にしたい評価額が異なることも多くトラブルが発生しかねません。
相続人同士で意見がまとまらない時は、最も正確な不動産鑑定で相続を行いましょう。
査定が困難な不動産を売買するとき
不動産の売買では、不動産会社による、不動産の売買に焦点をあてた査定を受けるのが一般的です。
しかし、売却するのが病院やゴルフ場、ソーラーパネル設置用地などのように、不動産会社では価値の判断が難しい不動産もあります。
そのような不動産を売買する場合は、不動産鑑定を受けて、信頼できる価値を算出してもらいましょう。
不動産を担保にするとき
自身が所有する不動産を担保に資金調達を行う場合も、不動産の正確な価値を把握する必要があります。
例えば、4,000万円の資金調達を予定していて、金融機関が不動産の評価額の8割を融資上限としているケースでは、不動産の評価額が5,000万円以上なければ目的を達成できません。不動産の評価額を事前に把握しておけば、資金計画も立てやすくなるでしょう。
離婚で財産分与するとき
離婚の際は財産分与を行いますが、結婚後に築いた不動産も分与の対象になります。
不動産を財産分与するには、不動産の価値を把握しなければいけません。
固定資産税評価額や相続税評価額、不動産会社の査定額など、いずれの価格も不動産の価値とすることができますが、それぞれ価格差が大きいため夫婦の意見が合致しない場合もあります。
不動産鑑定は、様々な視点と現況に基づいた最も正確な価格なので、話が合わない場合は不動産鑑定を利用しましょう。
離婚調停などに陥った場合も、不動産鑑定評価額は不動産価値の根拠として提出できます。
不動産鑑定がおすすめの人
この章では、不動産鑑定がどのような人に適しているかをまとめました。不動産鑑定がおすすめの人の条件は以下の通りです。
【不動産鑑定がおすすめの人の条件】
- 相続発生時の遺産分割で不動産の正式な価格を知りたい
- 離婚の際の財産分与で不動産の正式な価格を知りたい
- 個人間で不動産を売買するにあたり不動産の正確な価格を知りたい
また、不動産鑑定をおすすめしない人の条件は以下の通りです。
【不動産鑑定をおすすめしない人の条件】
- 遺言書で遺産分割方法が細かく決められている場合
- 不動産を売却するか判断するために価値を知りたい
- 不動産の売却を進めるために価値を知りたい
不動産鑑定の3つの方法
不動産鑑定士の鑑定は、不動産鑑定評価基準に基づいて行われます。主に以下の3つの手法を利用して、適正な評価額を算出しています。
- 原価法
- 取引事例比較法
- 収益還元法
それぞれの手法を詳しく見ていきましょう。
原価法
原価法は以下の計算式で算出します。
再調達原価とは、同条件の不動産を再建した場合にいくらかかるか算出した価格です。
また、減価修正とは、経年劣化による資産価値の減少を指します。
再調達原価から減価修正を差し引くことで、現在の不動産の価値を算出できます。
建物や造成地、埋め立て地などの鑑定評価に用いられますが、既成市街地の土地については再調達原価を求められないので用いることができません。
取引事例比較法
取引事例比較法は、対象の不動産と条件が近い過去の取引事例を参考に適正価格を算出する方法です。
以下の手順で算出します。
- 類似物件の情報を収集する
- 各事例に補正が必要な場合は補正を行う
- 地域要因がある場合は補正を行う
- 補正が完了した価格を比較して算出する
不動産の売買には一定の時価が存在するわけではなく、当事者の都合で取引価格が大きく変動します。
例えば、大幅な値下げをしてでも早く売りたい場合や、知人同士の個人間取引で安価に取引される場合など、こうした事例はそのまま参考できず、各事例の補正が必要になります。
また、交通の利便性や自然災害リスクの高さ、地勢の状態などの地域要因がある場合には、それらも踏まえて価格を算出する必要があります。
これが地域要因における補正です。
取引事例比較法は、特殊な事例を比較対象に含んでしまうと、正確な価格算出が難しくなります。
そのため、客観的で特殊条件を含まない類似物件をどれだけ見つけて比較できるかが重要です。
収益還元法
収益還元法とは、収益の発生しているアパート・マンションなどの不動産を鑑定する際に用いられる手法です。
収益還元法は直接還元法とDCF法の2種類ありますが、比較的分かりやすい直接還元法で説明します。
- 直接還元法:年間の賃料収入を利回りで割って価格を計算するもの
- DCF法:直接還元法で想定されていない家賃の下落や空室リスクを織り込んだもの
直接還元法は以下の計算式で算出します。
例えば、1年間の純収益が300万円で、利回りが5%の不動産を所有している場合、「300万円÷5%=6,000万円」が不動産の評価額です。
営利目的で使用していない不動産であっても、営利目的で貸し出せるものであれば収益還元法を用いることが可能です。
不動産鑑定の結果に影響を与える3つの要因
不動産鑑定評価の結果には、以下の3つが影響します。
- 一般的要因
- 地域要因
- 個別要因
それぞれの要因を詳しく説明していきます。
一般的要因
一般的要因とは不動産を売買するときの情勢や環境など、世の中のあり方全般による要因のことです。
これを大きな括りで、さらに自然的要因、社会的要因、経済的要因、行政的要因などに大別されます。
具体的な一般的要因は、以下の通りです。
| 一般的要因 |
|
参照元:国土交通省「不動産鑑定基準」
地域要因
地域要因とは、不動産のある場所の周辺がどのような地域かによって価格に影響を与える要因のことです。
住宅地域、商業地域、工業地域、農地地域、林地地域などに大別されます。
具体的な地域要因は、以下の通りです。
| 地域要因 |
|
参照元:国土交通省「不動産鑑定基準」
個別的要因
個別的要因とは、対象の不動産固有の事情のことです。
「どんなところにある、どのような土地なのか」「どのくらい広く、どのように作られている建物なのか」といった具合に、多くの評価点があります。
具体的な個別的要因は、以下の通りです。
| 個別的要因 |
|
参照元:国土交通省「不動産鑑定基準」
不動産鑑定の流れ
不動産鑑定は、結果が出るまで1週間~2週間程度の時間を要します。
事前に流れを把握し、手続きをスムーズに進められるようになりましょう。
不動産鑑定の主な流れは以下の通りです。
- STEP1:不動産鑑定士を探す
- STEP2:委託契約を結ぶ
- STEP3:不動産鑑定士に資料を提出
- STEP4:不動産鑑定士による調査
- STEP5:不動産鑑定基準に基づいた評価
- STEP6:不動産鑑定評価書を受け取る
各ステップを詳しく見ていきましょう。
STEP1】不動産鑑定士を探す
まず不動産鑑定士を探します。
どの不動産鑑定士に鑑定を依頼しても特に問題ありませんが、地域の事情に精通している不動産鑑定士のほうがより正確な評価が期待できます。
インターネットに住所と不動産鑑定士の2つの単語を入力して検索すれば、最寄りの事務所を検索できます。
また、各都道府県の不動産鑑定士協会のホームページから、各地域を管轄する不動産鑑定士を検索することもできます。
STEP2】委託契約を結ぶ
不動産鑑定士によって料金が異なるため、複数社に見積もりを依頼し比較したうえで決めると安心です。
また、質問したいことも多いと思いますので、人として誠実で、かつ実績のある鑑定士を選ぶといいでしょう。
不動産鑑定士と依頼者の双方が条件に合意した場合は、委託契約の締結に移行します。
依頼内容についての詳細が記載された依頼書兼承諾書を交わします。
STEP3】不動産鑑定士に資料を提出
不動産鑑定士に不動産鑑定に必要な資料を提出します。資料の一例は、以下の通りです。
【必要書類の一例】
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 構図、地積測量図、実測図
- 住宅地図
- 固定資産評価証明書(固定資産税・都市計画税)
- 建物竣工図、建物図面
- 管理規約、催促、建物管内規則
- 建築確認通知書、検査済証
必要な資料は不動産の種類や目的によって異なります。
依頼の際に、先だって必要書類を聞いておくとスムーズです。
STEP4】不動産鑑定士による調査
不動産鑑定士による、鑑定のための調査が始まります。
対象となる不動産の現地調査だけでなく、法務局や市区町村の関係官公庁で得られる情報からも調査をします。
STEP5】不動産鑑定基準に基づいた評価
登記簿謄本や要因資料、取引事例などの資料から不動産鑑定基準に基づいて評価が行われます。
評価の完了までは1~2週間程度かかります。
STEP6】不動産鑑定評価書を受け取る
評価が完了した後は、不動産鑑定士から不動産鑑定評価書の説明を聞きます。
特に問題がなければ、不動産鑑定評価書を受け取って鑑定は終了します。
不動産鑑定のポイント
不動産鑑定とは以下のようなものです。
- 土地や建物といった不動産の正確な価値を判断するための鑑定
- 不動産鑑定士しか行うことができない
- 不動産査定は仲介依頼を受けるための営業行為の一環で行われるもの
- 不動産鑑定にかかる費用は数十万円
詳しくは「1.不動産鑑定とは」をご覧ください。
不動産鑑定がおすすめの人は以下の通りです。
- 相続発生時の遺産分割で不動産の正式な価格を知りたい
- 離婚の際の財産分与で不動産の正式な価格を知りたい
- 個人間で不動産を売買するにあたり不動産の正確な価格を知りたい
詳しくは「3.不動産鑑定がおすすめの人」をご覧ください。
不動産鑑定の流れは以下の通りです。
- STEP1:不動産鑑定士を探す
- STEP2:委託契約を結ぶ
- STEP3:不動産鑑定士に資料を提出
- STEP4:不動産鑑定士による調査
- STEP5:不動産鑑定基準に基づいた評価
- STEP6:不動産鑑定評価書を受け取る
詳しくは「6.不動産鑑定の流れ」をご覧ください。
費用を抑えたいなら簡易鑑定は以下の通りです。
- 不動産鑑定評価基準に基づきつつ一部の記述や評価を省略して行われる不動産の評価
- 通常の不動産鑑定よりも費用を抑えられる
- 裁判所や税務署といった公的機関には提出できないので注意
詳しくは「7.費用を抑えたいなら簡易鑑定」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2025年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 2025年問題まであと2年!不動産は本当に大暴落するの?今後の不動産売却のタイミングは?
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点
- 不動産売却で確定申告を行う手順・必要書類・税金の計算方法