相続した実家を手放したくても、売却方法がわからず迷っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、実家の売却を検討している方に向けて、売却のポイントや手順・税金などを解説します。
お読みいただき実践することで、後悔することなく実家を売却できるでしょう。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「IELICO(イエリコ)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
目次
1. 実家売却のタイミング

相続する実家の取り扱いについてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
特に気になるのが、相続前と相続後、どのタイミングで家を売るのがよいのか、という点です。
売却のタイミングを見極めるため、「相続前」と「相続後」に売るメリットをそれぞれ詳しく見ていきましょう。
相続前
相続前に売却するメリットとしては以下のようなことが挙げられます。
- 遺産分割しやすい
- 3,000万円特別控除を受けられる
- 家族信託も選択肢になる
ひとつずつ見ていきましょう。
遺産分割しやすい
相続前に不動産を売却して現金にしておけば、相続財産を遺産分割しやすくなります。
相続財産に不動産が含まれる場合、相続後に遺族で相続財産をどのように分けるか揉めやすいのです。
例えば、相続財産のほとんどが不動産だった場合、残された家族が複数人いると、均等に分けるのが困難です。
このような場合、遺産分割がまとまらない事態に発展するおそれがあります。
そのため、相続前に不動産を売却して現金にしておくほうが、相続財産を遺産分割しやすいのです。
3,000万円特別控除を受けられる
3,000万円特別控除を活用できる点もメリットです。
不動産を売却して利益が出ると、利益額に応じて税金を納めなければなりません。
その際、売却する不動産がマイホームであるといった条件を満たしていれば、3,000万円特別控除の適用を受けられます。
3,000万円特別控除とは、その名の通り、譲渡所得の計算において3,000万円分の特別控除を受けられる制度です。
節税効果の高い制度なので、積極的に活用していくことをおすすめします。
なお、3,000万円特別控除は「空き家」になると適用できないため、相続後に誰も住んでいない場合は利用できません。
家族信託も選択肢になる
被相続人の生前であれば、家族信託の利用を検討できるのもメリットです。
家族信託は認知症などに備えて、財産の管理を子などに任せる信託契約です。
家族信託を結んだあとは、財産の管理を任された人が不動産を売却等できるようになります。
また、被相続人の生前、意思のはっきりしているうちに財産の管理人を選べる点もメリットとして挙げられます。
遺言書を遺さず亡くなってしまった場合、相続人間で財産の扱いを巡ってトラブルに発展してしまうことは多々あります。
その点、家族信託契約を事前に結んでおけば、こうしたトラブルを回避しやすくなるでしょう。
相続後
相続後に売却するメリットは、以下の点が挙げられます。
- 相続税の節税になる
- 譲渡所得税の節税になる
それぞれ見ていきましょう。
相続税の節税になる
相続後に不動産を売却するひとつ目のメリットは、相続税の節税ができることです。
相続税の計算上、不動産は相続税路線価や固定資産税評価額で評価されます。
相続税路線価の場合、実勢価格の80%程度、固定資産税評価額は実勢価格の70%程度になります。
そのため、同じ額の現金を持っているより、不動産で持っていた方が相続税を安く抑えられる効果が期待できるのです。
譲渡所得税の節税になる
不動産を売却して得られた利益には譲渡所得税が課されます。
しかし相続後の売却の場合、相続税の申告期限から3年以内に売却することで「相続税の取得費加算の特例」の適用を受けられます。
本特例の適用を受けることにより、譲渡所得税の計算上、相続税として納税した分の一部を取得費に加算することで、譲渡所得税の納税額を抑えることが可能です。
2. 実家売却前に確認すべきこと
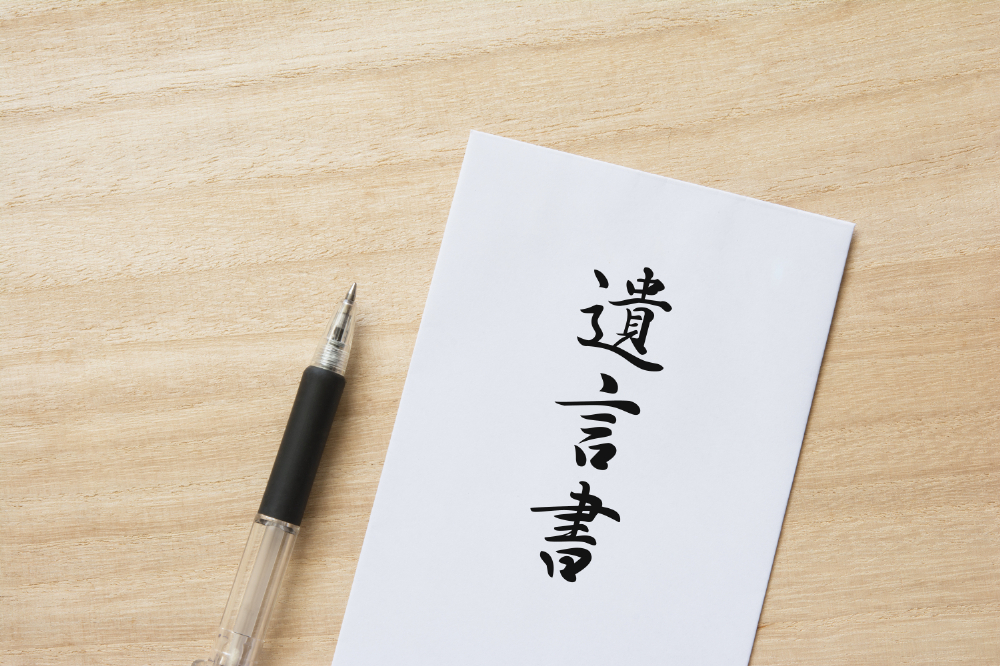
実家を売るタイミングを決めたら、売却の準備を開始しましょう。
実家の売却前には確認すべきことがいくつかあります。
- 遺言書
- 実家の名義
- 隣家との境界線
- 実家の片付け・整理整頓
それぞれについて詳しく解説します。
遺言書
まずは遺言書の有無を確認してください。
相続発生後、遺言書がない場合は相続人が集まって遺産分割協議を行いますが、遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。
正式な遺言書として認められるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 被相続人が自筆で全文書く
- 日付・氏名が記載されたる
- 氏名の後に印鑑が押されている
- 訂正がある場合は訂正印と訂正箇所の記載がある
遺言書が「公正証書遺言」になっているケースもあるので、遺言書のありかが分からない場合は公証役場に問い合わせるとよいでしょう。
実家の名義変更
相続により、被相続人から相続人に所有権が移ったとしても、正式に登記の手続きをしなければ相続人の所有する不動産であることを第三者に主張できません。
相続後に所有権を被相続人から相続人に移す登記手続きを、相続登記と言います。
相続登記は、自分で法務局に行って手続きすることもできますが、司法書士に依頼すれば、必要書類を揃えるだけで手続きを代行してもらえます。
隣家との境界線
近年では、不動産売却前に境界確定を済ませておくのが一般的です。
境界確定の済んでいない不動産は近隣とのトラブルになる可能性もあり、避けられてしまう可能性が高いでしょう。
境界確定をするためには、測量士や土地家屋調査士に依頼して測量してもらわなければなりません。
また、隣地や前面道路の所有者と立ち会いのもと手続きを行う必要があります。
場合によっては1~2ヶ月以上かかることもあるため、早い段階で手続きを進めておくことが大切です。
実家の片付け・整理整頓
家を売却する前に、片付けや整理整頓を行っておきましょう。
家具や家財が遺されたままだと、売却活動に支障をきたす可能性が高いからです。
亡くなった方の家財などを整理することを遺品整理と呼びますが、遺品整理専門の業者も存在します。
費用がかかりますが、プロに任せることできれいに家の中を整理してもらえます。
また、仏壇を処分する際は、お寺で「閉眼供養」をしてもらう必要があります。
「閉眼供養」とは、位牌に宿る故人の霊魂を抜き取るための儀式です。
仏壇の処分が必要になったら、お寺に相談しましょう。
3. 実家売却の手順
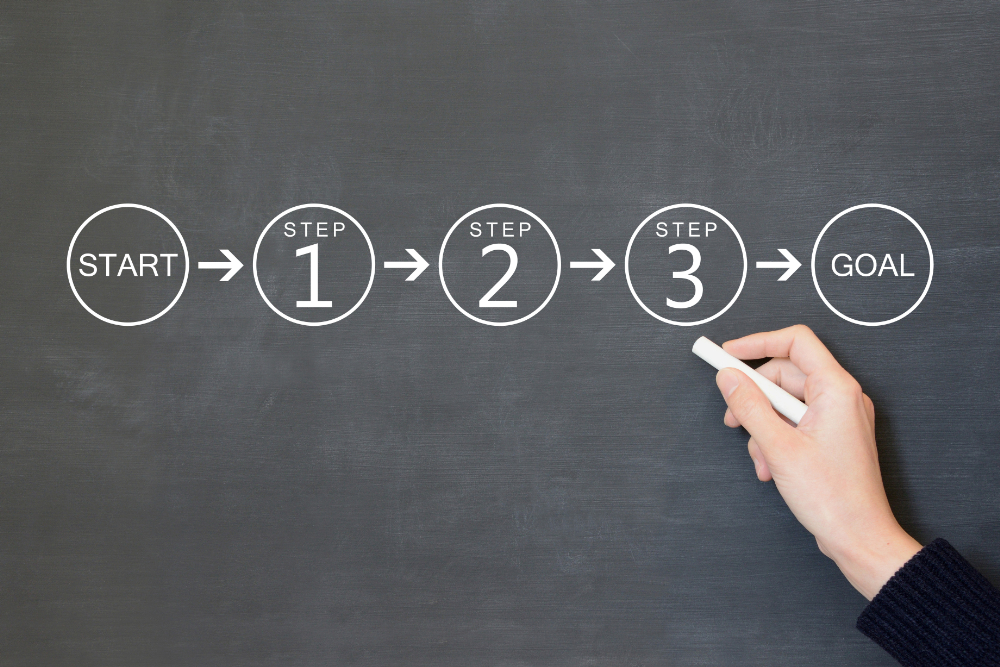
ここまで実家を売却する前にするべきことを見てきました。
つづいて、実家を売却する手順を確認していきます。
- 必要書類の準備
- 査定依頼
- 媒介契約
- 販売活動
- 売買契約
- 引き渡し
順番に見ていきましょう。
1.必要書類の準備
まずは必要書類を準備してください。
実家売却で必要になる書類は、以下の通りです。
| 必要書類 | 作成方法・場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 登記済権利証または登記識別情報 | 被相続人から相続 | ― |
| 地積測量図 | 被相続人から相続 あるいは法務局で取得 | ― |
| 実印・印鑑証明・住民票の写し・本人確認書類 | 市区町村役場で取得 | ― |
| 売買契約書 | 被相続人から相続 紛失した場合は不動産会社に問い合わせ | ない場合は、概算法で物件価格の5%を取得費として算出する |
| 重要事項説明書 | 被相続人から相続 紛失した場合は不動産会社に問い合わせ | ― |
| 固定資産税納税通知書及び固定資産税評価証明書 | 被相続人から相続 あるいは市区町村役場で取得 | ― |
| 建築確認済証および検査済証 | 被相続人から相続 紛失した場合は住宅会社に問い合わせ | ― |
| 建築設計図書、工事記録書 | 被相続人から相続 紛失した場合は住宅会社に問い合わせ | ― |
| 管理規約、使用細則、維持費関連書類 | 被相続人から相続 紛失した場合は管理組合に問い合わせ | マンションの場合 |
| 耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書 | 被相続人から相続 | ない場合もある |
2.査定依頼
必要書類の準備が済んだら、不動産会社に査定依頼を出しましょう。査定依頼は複数の不動産会社に依頼するのがおすすめです。
同じ不動産でも、不動産会社によって査定価格が異なることがあります。
複数の不動産会社に査定依頼することにより、不動産会社によって査定結果が異なっても、その平均を実家の売却相場と捉えることが可能です。
また、査定結果を聞く際に、どの程度説得力のある根拠があるのか、不動産会社ごとの対応を比較できるのも複数の不動産会社に査定を依頼するメリットです。
複数社に査定を依頼する際に便利なのが、NTTデータグループが運営する一括査定サイト「IELICO(イエリコ)」です。

イエリコは、全国2,100の提携不動産会社の中から最大6社の紹介を受けることができます。
また、12,500以上の口コミがあり、複数の不動産会社の中から自分に合った会社を見つけやすいのも特徴です。
ぜひイエリコで比較して、信頼できる最適な不動産会社を見つけてください。
3.媒介契約
査定結果を聞いた後、売却を依頼する不動産会社が決まったら、その不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には、次の3種類があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
特に大きな違いは、「一般媒介契約」が複数の不動産会社と契約できるのに対し、「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」は1社としか契約できない点です。
「一般媒介契約」は複数の不動産会社に契約できるため、早く売れやすいというメリットがある一方、各不動産会社はあまり積極的に売却活動を行ってくれない可能性があります。
「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」は、売却までに時間がかかりますが、契約した不動産会社が確実に仲介手数料を受け取れるため、売却活動を熱心にサポートしてくれる可能性があります。
3種類それぞれの特徴を理解したうえで、どの媒介契約にするか選ぶことが大切です。
4.販売活動
媒介契約後は、広告や販売活動など、不動産会社が主体で行っていくことになります。
とはいえ、任せきりにしてしまうと、不動産会社が積極的に活動せず、売却期間が長引くおそれがあります。
そのため、任せきりにするのではなく、密に連絡を取って動向を確認するなどしておくのが望ましいでしょう。
広告活動の結果、物件に興味がある方から連絡を受けたら、内覧を行うことになります。
内覧する場合は、内覧日前にしっかり整理整頓したり、天気のよい日を選んだりするなどする工夫をしましょう。
5.売買契約
内覧の結果、購入希望の連絡を受けたら、価格面など交渉を行い、お互いが納得したら売買契約に進みます。
売買契約時には買主から手付金を受け取りますが、売主は不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があるため、資金を用意しておきましょう。
仲介手数料は売買契約時に半分、引き渡しの際の決済時に半分といった形にするのが一般的です。
ただし、不動産会社によっては売買契約時に全額を請求するケースもあります。仲介手数料の額についても、事前に確認してください。
6.引き渡し
売買契約後は、買主の住宅ローン本審査が行われ、審査で承認を得たら決済・引き渡しとなります。
売却する実家にローンが残っている場合には、売却代金でローンの残債処理など諸手続きを行う必要があるでしょう。
4. 実家売却に必要な税金と費用

実家売却時にはさまざまな税金・費用がかかります。
ここでは、以下の税金や費用について見ていきましょう。
- 相続税
- 登録免許税
- 譲渡所得税・住民税
- 復興特別所得税
- 印紙税
相続税
相続税は、相続の開始を知った日から10カ月以内に納税する必要があります。
そのため、相続後に実家を売却し、売却代金で相続税を支払うような場合には、できるだけ早く売るようにしないといけません。
相続税は、以下の流れで計算します。
- 遺産総額を計算し基礎控除額を差し引く
- 課税遺産総額を法定相続分で分ける
- それぞれに税率をかけて控除額を差し引く
- 各人の取得割合に応じて按分する
計算方法の詳細を見ていきましょう。
遺産総額を計算し基礎控除額を差し引く
まずは遺産総額を計算し、基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は以下の計算式で求めます。
例えば、妻と子2人が法定相続人の場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。
遺産総額が1億円だった場合、1億円-4,800万円=5,200万円が課税遺産総額になると考えるとよいでしょう。
課税遺産総額を法定相続分で分ける
次に、課税遺産総額を法定相続分で分けます。
法定相続分が配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分は2分の1,子の法定相続分は2分の1です。
ただし、子は2人いるため、それぞれ4分の1となります。
このケースでは、それぞれの課税遺産額は以下の通りです。
- 配偶者:5,200万円×1/2=2,600万円
- 子:5,200万円×1/4=1,300万円
それぞれに税率をかけて控除額を差し引く
法定相続分で分けたら、それぞれに税率をかけて控除額を差し引きます。
相続税の税率は以下のように定められています。
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この場合、それぞれの相続税額は以下の通りです。
- 配偶者:2,600万円×15%-50万円=340万円
- 子: 1,300万円×15%-50万円=145万円
各人の取得割合に応じて按分する
最後に、法定相続分で分けた相続税額の合計額を算出し、各人の取得割合に応じて按分します。
まずは相続税額の合計額を算出しましょう。
次に、各人の取得割合に応じて按分します。
例えば、妻が40%、子がそれぞれ30%だった場合、以下のように計算します。
- 配偶者:630万円×40%=252万円
- 子1:630万円×30%=189万円
- 子2:630万円×30%=189万円
上記の金額、さらに各種控除を差し引きます。
控除にはさまざまなものがありますが、例えば配偶者控除であれば、配偶者が取得した財産の合計額が1億6,000万円まで非課税となります。
そのため、相続全体の納税額を安く抑えたいのであれば、配偶者の取得費率を高くするとよいでしょう。
また、相続税を支払った実家を相続税の納付期限から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を譲渡所得税から控除できる取得費加算の特例の適用を受けることが可能です。
登録免許税
登録免許税は所有権移転等の際に納める税金です。
具体的には所有権移転の手続きをする際に、法務局に対して支払います。
相続登記の登録免許税は不動産の価格(固定資産税評価額)の0.4%と定められています。
譲渡所得税・住民税
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税・住民税を納めなければなりません。
譲渡所得税・住民税の計算方法は以下の通りです。
- 課税譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除
- 納税額=課税譲渡所得×税率
譲渡所得税・住民税の税率は売却した不動産の所有期間によって異なります。
具体的には以下の通りです。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
また、売却する不動産の所有期間が10年超の場合は、課税譲渡所得6,000万円までの部分について14.21%の軽減税率の適用を受けられる特例もあります。
相続不動産の場合、所有期間は、被相続人が所有していた期間も加算できるため、10年超となるケースも少なくありません。
また、売却した実家が昭和56年5月31日以前に建てられ、生前、被相続人が住んでおり、亡くなった後は誰も住んでいない空き家になっているといった一定の要件を満たせば、3,000万円の特別控除を受けられる制度もあります。
譲渡所得税は不動産を売却した年の翌年2月16日~3月15日の間に確定申告して納めます。
復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災の復旧のために充てられる税金で、譲渡所得税のうち、2.1%分が該当します。
例えば、短期譲渡所得の所得税の税率は30.63%となっていますが、この内訳は、所得税30%に対して、復興特別所得税は0.63%です。
復興特別所得税は、譲渡所得税の確定申告と同時に納税します。
印紙税
印紙税は売買契約書に貼付する形で納税するものです。
売買契約書に記載の金額に応じて、以下の金額を納税する必要があります。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を超え 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
5. 実家売却で後悔しないための注意点

実家の売却にあたっては、3つ注意点があるため把握しておきましょう。
- 控除の期限内に売却する
- 放置すると老朽化が進んで資産価値が下がる
- 不動産会社選びに失敗すると売却期間が長引く
それぞれ詳しく見ていきましょう。
控除の期限内に売却する
まずは、控除の期限内に売却することを意識してください。
実家を相続して相続税を納めた後に、売却する場合、その売却価格に応じて譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税の計算の際、相続税の期限から3年以内であれば、相続税の一部を取得費に加算できる取得費加算の特例の適用を受けられます。
取得費加算の特例を受けることにより、譲渡所得税の負担を抑えられるため、相続を知った日から3年10カ月以内に売却することを考えておくのがおすすめです。
放置すると老朽化が進んで資産価値が下がる
建物は時間と共に、カビやほこり、ねずみやシロアリ被害の発生などにより劣化していきます。
建物は住みながらでも劣化が進みますが、実家を相続したものの誰も住まずに放置していると、老朽化が進むのが早くなってしまいます。
老朽化が進むと日に日に資産価値が落ちていくため、早めに売却を進めることが大切です。
不動産会社選びに失敗すると売却期間が長引く
不動産会社選びも重要なポイントです。不動産会社と一口に言っても、エリアや不動産の種類など得意分野はそれぞれ異なります。
よく調べずに得意分野の異なる不動産会社に売却を依頼してしまうと、売却期間が長引いてしまうことになりかねません。
しかし、不動産会社がどんな物件やエリアを得意といったことが分からないという方も多いでしょう。
そうした方におすすめなのが、「IELICO(イエリコ)」です。

イエリコを利用すれば、全国2,100の厳選された提携不動産会社の中から、物件に合った不動産会社について、最大6社紹介を受けることが可能です。
実家の売却を考える際にはイエリコをご活用ください。
6. 実家を売却しないときの活用方法

最後に、実家を売却せずにそのまま活用する方法をご紹介します。
具体的には以下の4つです。
- 賃貸
- 民泊
- 駐車場
- 物置・別荘
ひとつずつ見ていきましょう。
賃貸
実家を賃貸として貸し出し、収入を得る方法です。
実家が立地のよい場所にあるようなケースでは、活用しやすい方法だと言えるでしょう。
他人が住んでくれることにより、管理の手間が減るというメリットもあります。
老朽化が進んだ物件の場合はリフォーム費用などかかってしまう可能性があるため、費用対効果がどの程度あるのか事前にしっかりリサーチすることが大切です。
民泊
民泊として貸し出し、収入を得るケースです。
こちらも、借りた人が使ってくれることにより、管理の手間が多少減ります。
民泊施設として観光客等が利用しやすい立地にあるのかなど、事前の調査が求められるでしょう。
駐車場
家を建て壊し、駐車場などに活用して収入を得るケースです。
自動車の利用が多く、周辺の駐車場が足りていないような場合におすすめです。
どのように活用していくか決め切れていない場合には、一旦建物を解体して駐車場として貸し出し、将来的に別の方法で活用するといった方法も検討するとよいでしょう。
ただし、建物を解体すると、固定資産税が最大6分の1になる住宅用地の特例の適用を受けられなくなる点に注意が必要です。
建物があったときと比べると、固定資産税の負担が最大で6倍になる可能性があります。
物置・別荘
貸し出しなどはせず、物置や別荘として個人利用するケースです。
実家が郊外にあり、固定資産税などの負担が小さいのであればこのような活用法も検討するとよいでしょう。
ただし、人が住まなくなった家は老朽化が進みやすい点には注意が必要です。
万が一、老朽化したものを放置して、台風などの際に建物が倒壊して第三者に被害を与えた場合は損害賠償請求しなければならない可能性もあるといった点は押さえておいてください。
この記事のポイントまとめ
実家売却のタイミングは、相続前と相続後それぞれのメリットを押さえた上で決めるのがおすすめです。
【相続前のメリット】
- 遺産分割しやすい
- 3,000万円特別控除を受けられる
- 家族信託も選択肢になる
【相続後のメリット】
- 相続税の節税になる
- 譲渡所得税の節税になる
- 実家売却前に確認すべきこと
詳しくは「1.実家売却のタイミング」をご覧ください。
実家売却前に確認すべきことは以下の通りです。
- 遺言書の有無と内容を確認しておく
- 実家の名義変更を行っておく
- 隣地との境界線が確定しているか確認しておく
- 遺品整理を実施しておく
詳しくは「2.実家売却前に確認すべきこと」をご覧ください。
実家売却の手順は以下の通りです。
- まずは必要書類を確認する
- 不動産会社に査定依頼を出した後、媒介契約を締結する
- 不動産会社が販売活動を開始する
- 購入希望者が現れたら売買契約を締結し、決済、引き渡しへと進む
詳しくは「3.実家売却の手順」をご覧ください。
実家売却で後悔しないためには、以下3つの注意点を押さえておきましょう。
- 控除の期限内に売却する
- 放置すると老朽化が進んで資産価値が下がる
- 不動産会社選びに失敗すると売却期間が長引く
詳しくは「5.実家売却で後悔しないための注意点」をご覧ください。
家を売却しないときの活用方法は以下の通りです。
- 賃貸に出して賃貸収入を得る
- 民泊施設として貸し出し利用料を得る
- 駐車場として貸し出し賃料を得る
- 物置や別荘として活用する
詳しくは「6.実家を売却しないときの活用方法」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点





