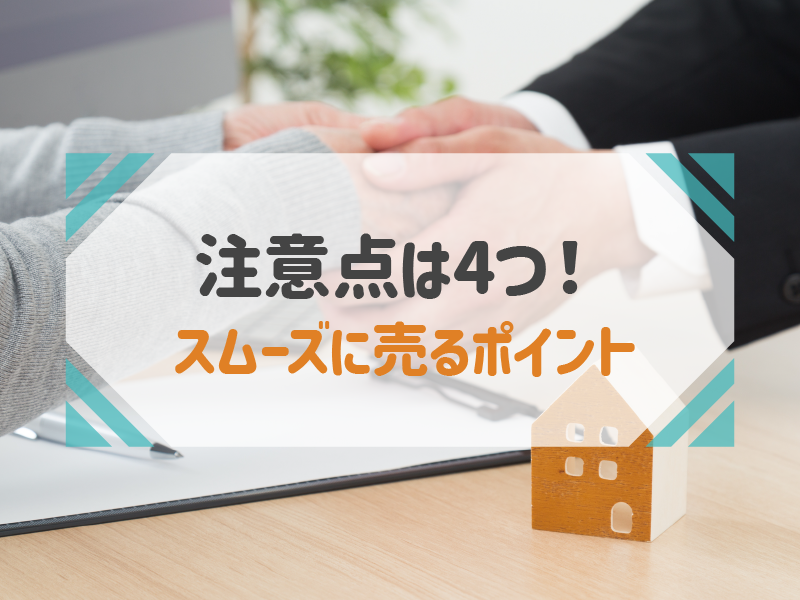家の売却で損をしないためにも、売却したい時期や希望する金額を明確にしておくことが大切です。この記事では、家を売却するときのさまざまな注意点を詳しく解説します。
- 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格”を見つけましょう
- 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
1.家を売る手順と注意点
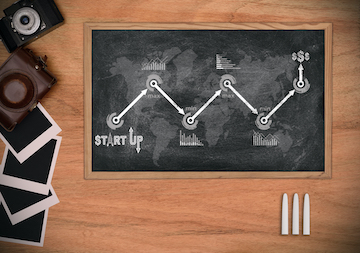
家を仲介で売却する場合、一般的には4~6か月程度の期間がかかります。売却が完了し、関連手続きが終わるまでにそれなりの時間を要しますので、基本的な手順について正しく把握しておきましょう。
- 売りたい家の相場を自分で調べる
- 不動産会社に査定依頼を行う
- 不動産会社と媒介契約を締結する
- 売却活動を進める
- 内覧対応を行う
- 買い主と売買契約を締結する
- 決済・引き渡し
- 確定申告を行う
各手順におけるポイントと注意点をそれぞれ解説します。
1-1.売りたい家の相場を自分で調べる
家の売却を検討するときには、不動産会社に物件を査定してもらう必要があります。しかし、提示された査定額が適正なものであるかは、比較するものがなければ判断しづらいものです。
そのため、不動産会社に査定依頼を行う前に、自分でも相場を調べてみると良いでしょう。webを通じて誰でも利用できるサイトがあり、主なものとして次の2つが挙げられます。
| サービス名 | 概要 |
|---|---|
| 土地総合情報システム |
|
| レインズ・マーケット・インフォメーション |
|
国土交通省が情報提供を行っている「土地総合情報システム」は、実際に行われた取引についてのアンケート調査をもとにしているため、リアルな取引価格を知ることができます。また、REINS(不動産流通機構)が提供している「レインズ・マーケット・インフォメーション」では、直近1年間の取引を調べることが可能です。
土地の売却相場を調べるなら「土地総合情報システム」を活用し、一戸建てやマンションの取引について調べたいときは「レインズ・マーケット・インフォメーション」を活用してみましょう。注意点としては、個人情報保護の観点から物件の詳しい住所は閲覧できない点が挙げられます。
しかし、大まかな所在地は把握できるので、周辺エリアの相場を把握するには役立つはずです。
1-2.不動産会社に査定依頼を行う
自宅がいくらで売却できるのかを知るには、不動産会社に査定してもらいましょう。原則として無料で査定を行ってもらえますし、査定額を見れば大まかな売却価格の目安を把握できます。
査定依頼は1社ずつ個別に問い合わせることも可能ですが、手間や時間がかかりますので工夫が必要です。不動産の一括査定サービスを利用すれば、物件情報などを入力するだけで、一度に複数の会社に依頼できます。
複数の会社が提示してくる査定結果を比較すれば、より妥当な売却価格と、良い条件で売却できそうな不動産会社も分かるでしょう。査定結果は査定額だけでなく、売り出し価格や類似物件の取引事例などが記載されています。
家を売るのに適したタイミングを見極めるうえでも重要ですので、複数の会社に査定依頼を行ってみましょう。注意点としては、信頼性の低い一括査定サービスを利用すると営業の電話などに悩まされてしまう恐れがあることです。
提携している不動産会社をどのような基準で審査しているのか、口コミなどの評判は良いかなど自分なりの判断基準を持って、信頼できるサービスを利用してみましょう。
1-3.不動産会社と媒介契約を締結する
査定結果を比較した後は、どの不動産会社に仲介業務を依頼するかを決めましょう。仲介業務を依頼するときは不動産会社と媒介契約を締結する必要があり、以下の3種類があります。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 複数の不動産会社との契約 | 〇 | × | × |
| 売り主が見つけた相手との取引 | 〇 | 〇 | × |
| REINSへの登録義務 | 任意 | 7日以内 | 5日以内 |
| 売り主への業務報告 | 任意 | 14日ごとに1回以上 | 7日ごとに1回以上 |
| 媒介契約の有効期間 | 任意 | 最長3か月 | 最長3か月 |
一般媒介契約は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことが可能であり、売り主自身が買い主を見つけたときに直接取引を行うこともできます。築浅物件や人気のエリアにある物件などを売却するときに向いている契約形態です。
専任媒介契約は1社としか契約ができませんが、一般媒介契約と同じように売り主が見つけた買い主と直接契約を結ぶことも可能です。
専属専任媒介契約は直接取引が行えませんので、不動産会社に買い主を見つけてもらう契約形態となります。
注意点としては、一般媒介契約では複数の会社と契約を行うため、専任媒介契約や専属専任媒介契約と比べて、対応を後回しにされる可能性があります。売り主自身も担当者と積極的にコミュニケーションを取るようにして、売却活動を進めてもらうようにしましょう。
専任媒介契約や専属専任媒介契約は、契約の有効期間内は途中で解約できないので、会社選びに注意したいものです。媒介契約を締結するときは、複数の会社を比較して担当者との相性もチェックしてみてください。
なお、築年数の経った古い家を売りたい場合は、不動産会社と密な連携やコミュニケーションをとりやすい、選任媒介契約や専属選任媒介契約がおすすめです。古い家の売却方法や注意点については、以下の記事も併せてご覧ください。
1-4.売却活動を進める
家の売却活動そのものは、不動産会社が主体となって行うものであるため、売り主のほうで何か特別な行動は必要ありません。しかし、不動産会社に任せきりにしていては、思うように家の売却が進まないこともあるでしょう。
専任媒介契約と専属専任媒介契約では、REINSへの登録義務や売り主への業務報告の義務があるため、不動産会社としても熱心な対応を見せてくれるでしょう。注意点としては、一般媒介契約についてはそれらの義務が課せられていないため、場合によってはあまり積極的に売却活動に取り組まないこともあります。
気になる部分は売り主自身も尋ねるようにして、担当者がきちんと売却活動を進めてくれているかをチェックしてみてください。
1-5.内覧対応を行う
売却活動を進めていく中で、売り主自身が対応する場面もあります。物件の内覧を希望する方が現れたときには、スケジュールを合わせて案内してみると良いでしょう。
空き家の場合は不動産会社に内覧対応を任せることもできますが、居住中の物件を売却するときには基本的に売り主が対応を行います。売り主自身が対応することで、住み心地や周辺環境の状況などを直接伝えることができ、物件情報だけでは分からない部分を詳しく紹介できます。
内覧時の印象は、物件の購入意思に影響を与える部分がありますので、適切な対応を心がけましょう。物件の魅力をうまくアピールできれば、相場よりも高い金額で売却できる可能性もあります。
注意点としては、日当たりを気にされる内覧者が多いので、内覧希望日が日中となるケースが多い点です。日中に内覧対応が行えるように、スケジュールをうまく調整してみましょう。
1-6.買い主と売買契約を締結する
物件の購入希望者が現れたら、契約条件や売買価格などをすり合わせて、交渉がまとまったところで買い主と売買契約を締結します。売買契約書は不動産会社が作成しますので、内容に誤りがないかをチェックしてみましょう。
建物に不具合がある場合は、売買契約書にきちんと内容を盛り込んでおくことが大切です。売却後のトラブルを未然に防ぐために、どの部分に関して売り主として責任を持つのかを明確にしておく必要があります。
また、売買契約を締結する際に、物件価格の10%程度の手付金を受け取ります。契約解除の条件や物件の引き渡し日など、重要な部分に間違いがないように確認しておきましょう。
注意点としては、売り主都合で契約を解除する場合、手付金の倍額を買い主に対して支払わなければならない点です。売買契約を結べば契約内容を遵守する必要があるので、双方が納得できるまで契約内容をよく話し合いましょう。
1-7.決済・引き渡し
物件の引き渡し日に、売り主・買い主・司法書士・不動産会社の担当者が集まって、残金の決済や物件の引き渡し手続きを行います。司法書士や不動産会社の担当者が書類の手続きなどを進めてくれますので、必要な箇所に署名・捺印を行いましょう。
売却代金で住宅ローンを完済する場合は、その後に抵当権の抹消登記を行う必要があります。全ての手続きが終わり、物件を引き渡したら売却が完了です。
決済・引き渡し時の注意点としては、実印・印鑑証明書・預金通帳・買い主に引き渡す書類などを用意し忘れると、残金の決済や物件の引き渡しが行えない点です。事前に何が必要かを担当者によく確認して、準備に漏れがないように気をつけましょう。
1-8.確定申告を行う
家を売却した翌年の2月中旬から3月中旬にかけて確定申告を行います。売却益が出た場合はもちろんですが、売却損が出た場合も確定申告を行うことで、税負担が軽くなる場合もありますので押さえておきましょう。
確定申告に必要な書類は国税庁のホームページなどからダウンロードができますが、売買契約書のコピーや各種領収書などは、自分で用意する必要がありますので早めに準備を整えておきましょう。
書類を作成したら、税務署の窓口に直接持参するか、郵送または電子申告などで手続きを行います。そして、決められた納付期限までに、口座振替やクレジットカード決済などで納税すれば確定申告の手続きは完了です。
注意点としては、確定申告を怠れば加算税や延滞税などのペナルティを課せられる恐れがある点です。申告期限や納付期限をきちんと確認して、期日内に確定申告を行いましょう。
2.家を売る際の費用と税金の注意点

家を売るときには、諸費用や税金がかかりますので、どのような項目で支払いが必要になるのかを確認しておきましょう。不動産会社に確認をすれば、どのタイミングで支払うべきものであるかを教えてくれます。
| 費用の項目 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬 | 取引額に応じて計算する |
| 印紙税 | 売買契約時の契約書にかかる税金 | 取引額に応じて決められる |
| 登録免許税(抵当権の抹消登記費用) | 抵当権の抹消登記にかかる税金 | 不動産1個あたり1,000円 |
| 司法書士に支払う報酬 | 登記手続きを代行してもらう依頼料 | 1~2万円程度 |
| 譲渡所得税 | 売却によって利益が出た場合にかかる税金 | 譲渡所得×所有期間に応じた税率 |
| その他の費用 | 引っ越し費用・ハウスクリーニング費用・測量・解体費用など | 必要に応じて異なる |
上記のようにさまざまな項目で支払いが必要になるため、各項目のポイントを解説します。
2-1.仲介手数料
仲介手数料は、売買契約が成立したときに不動産会社へ支払う成功報酬です。そのため、買い主が見つからなかったときには、支払う必要がありません。
仲介手数料は、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)で上限額が定められており、その範囲内で不動産会社が自由に設定します。取引額に応じて仲介手数料の金額は変わってきますので、下記の表をもとにしっかりと押さえておきましょう。
| 取引額 | 仲介手数料 |
|---|---|
| 200[2]万円以下の金額 | (取引額の5パーセント以内)+消費税 |
| 200万円以上400万円以下の金額 | (取引額の4パーセント以内)+消費税 |
| 400万円を超える金額 | (取引額の3パーセント以内)+消費税 |
なお、仲介手数料を支払うタイミングとしては、売買契約が成立したときと物件の引き渡し時に半金ずつ支払うか、物件の引き渡し時にまとめて支払う場合が多いと言えます。不動産会社によって支払いのタイミングは異なりますので、事前に確認をしておきましょう。
2-2.印紙税
売買契約書を作成するときには、契約金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。これが印紙税であり、2022年(令和4年)3月31日までは軽減税率が適用されている点を押さえておきましょう。
| 契約金額 | 通常の税額 | 軽減後税額 |
|---|---|---|
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
2-3.登録免許税
売り主側が支払う登録免許税とは、抵当権抹消登記にかかる費用を指します。所有権の移転登記費用は買い主側が負担するものであるため、特に気にする必要はありません。
抵当権抹消登記の費用は、不動産1個あたり1,000円と決められており、土地と建物であれば2,000円がかかります。抵当権を抹消するためには、住宅ローンを完済していることが前提なので注意しておきましょう。
2-4.司法書士への報酬
抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼する場合、1~2万円程度の費用がかかります。売却する物件の権利関係が複雑だったり、相続した不動産を売却したりするときには、司法書士に依頼をするほうが良いでしょう。
2-5.譲渡所得税
譲渡所得税とは、譲渡所得にかかる所得税・復興特別所得税・住民税の総称のことです。家を売却したときに利益(譲渡所得)が出たら支払う必要がありますが、売却代金(譲渡価額)そのものに課税されるわけではなく、購入にかかった費用(取得費)や売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた譲渡所得に課税されます。
譲渡所得の計算方法を計算式にまとめますと、次のとおりです。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
算出した譲渡所得に対して、物件の所有期間に応じた税率をかけることで、譲渡所得税を計算します。税率は、物件の所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得の区分となります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得では税率が大きく異なりますので、いつ取得した物件であるかをきちんと確認しておきましょう。
| 譲渡所得の区分 | 税率 |
|---|---|
| 短期譲渡所得(所有期間5年以下) | 39.63%(所得税30.63%※+住民税9%) |
| 長期譲渡所得(所有期間5年超) | 20.315%(所得税15.315%※+住民税5%) |
2-6.その他の費用
その他の費用としては、引っ越し代やハウスクリーニング代などが挙げられます。土地の境界が不明な場合は測量費用がかかりますし、建物を解体して売却するときは解体費用などがかかります。
物件の状況によって必要な費用は異なりますので、どのような費用がかかるのかを不動産会社にあらかじめ確認しておきましょう。
3.家を売るタイミングを決める際の注意点

家を売るタイミングは人によって異なりますが、売却目的から売りたい時期や希望する売却価格などを決めておくとスムーズです。不動産会社と媒介契約を結ぶ前に、「早く売りたい」「少しでも高く売りたい」などの売却目的を明確にしておきましょう。
- 売却目的を決めておこう
- 売却希望時期・希望金額を伝えよう
- 家を売る方法を選ぼう(仲介・買取)
- 一括査定サービスを活用してみよう
3-1.売却目的を決めておこう
売却目的を最初に決めておくほうが良いのは、目的別に売却方法や締結すべき媒介契約の種類が異なるからです。家を少しでも高く売りたい場合は、不動産会社に仲介してもらう形で売却活動を進めるほうが良いでしょう。
一方、できるだけ早めに売却したいときは、売り出し価格を相場よりも下げたり、不動産会社に買取を行ってもらったりする方向で売却活動を進めていきます。どのような目的で家を売却するのかが決まっていたほうが、不動産会社とのコミュニケーションも取りやすいはずです。
3-2.売却希望時期・希望金額を伝えよう
転勤や子どもの進学などで住み替え時期が決まっている場合は、スケジュールを逆算することで売却活動を始めるタイミングや売却を希望する時期などが決まってきます。一方、特に売却時期が決まっていなければ、少しでも高く売れる可能性が高くなるでしょう。
売却希望時期や希望金額は、不動産会社が売却活動の方針を決める際に基準となるものであるため、しっかりと伝えることが大切です。重要な部分ほど、コミュニケーションを緊密に行いましょう。
3-3.家を売る方法を選ぼう
家を売る方法としては、大きく分けて「仲介」と「買取」があります。仲介は媒介契約を締結して、不動産会社に物件の購入希望者を見つけてもらう方法です。
物件の売却まで4~6か月程度の時間がかかりますが、相場に近い金額で売却できる可能性が高い方法だと言えます。もう1つの買取については、不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。
契約条件や金額などが折り合えば、すぐに売却できるので早めに物件を売却したい方におすすめの方法だと言えます。ただし、不動産会社も全ての物件を買い取り対応するわけではありません。買取を考えるときは早めに相談をしてみましょう。
3-4.一括査定サービスを活用してみよう
家を売ることを考えるときには、不動産の一括査定サービスを活用すると売るべきタイミングを見極めることに役立ちます。webに接続できる環境であれば、いつでも査定依頼を行うことができます。
また、物件情報などを一度入力すれば、複数の不動産会社に査定依頼を行えるので手間や時間がかかりません。ここでは、不動産の一括査定サービスであるIELICO(イエリコ)を紹介します。
イエリコは、2001年に国内で初めて不動産の一括査定サービスを開始した、「不動産売却HOME4U(ホームフォーユー)」のサービスの1つです。20年以上にわたってサービスを提供していきた実績があり、累計で45万件以上の査定依頼の実績があります。
独自の審査基準で厳選した2,100社の優良企業を紹介しており、査定依頼を行うときには最大6社までを選択できます。査定依頼に必要な情報の入力は最短1分で完了でき、初めて利用する方でも簡単に操作することが可能です。
また、イエリコは情報サービス事業で業界最大手のNTTデータグループが運営を行っています。長年にわたって培ってきたセキュリティ技術によって、個人情報の取り扱いなど安心して利用していただける環境を整えています。
そして、自分に合った不動産会社を見つけるために、16,000件以上の経験者の口コミが役に立つことでしょう。不動産会社の強みや特徴を把握できますので、気になる不動産会社に査定を依頼することが可能です。
家の売却を考えるときには、イエリコを活用して信頼できる不動産会社を見つけてみましょう。
4.不動産会社を選ぶ際の注意点

家の売却を成功させるには、不動産会社選びが重要です。そのときに注意しておきたい点は、複数の会社の中から自分に合ったところを選ぶことです。主な注意点として、次の3つが挙げられます。
- 複数の会社を比較することが大事
- 家の売却を得意とする会社を選ぼう
- 担当者との相性もチェックしておこう
4-1.複数の会社を比較することが大事
信頼できる不動産会社を見つけるのは、できるだけ多くの会社を比較してみると良いでしょう。1社だけに家の査定を行ってもらっても、査定額が適正な価格であるのか判断がつかないものです。
また、売却活動の方針や提案内容が良いものであるのかも、比較対象がなければそのまま受け入れてしまいがちです。複数の会社に査定依頼を行えば、会社ごとに査定額や提案内容が異なるでしょう。
複数の査定結果を見比べることで、相場の目安や各社の特徴を把握できるはずです。売却予定の家にどのようなニーズがあるかを知る機会となるため、相場に見合った価格で家を売り出すことができます。
企業規模や知名度だけで判断するのではなく、それぞれの会社をきちんと比較したうえで最適な会社を選んでみてください。
4-2.家の売却を得意とする会社を選ぼう
不動産会社を選ぶときは、売却予定の物件について類似した実績がある会社を選んでみると良いでしょう。会社によって得意とするジャンルや成約実績に違いがあるため、一戸建てを売却したいなら、一戸建ての成約実績が豊富な会社を選ぶほうがスムーズです。
物件の仲介業務を依頼してもなかなか買い主が現れないときは、不動産会社に必要なノウハウがない場合もあります。思うように成約に結びつかない場合には、実績にある会社に変更してみるのも1つの方法です。
4-3.担当者との相性もチェックしておこう
良い不動産会社を選ぶことも大切ですが、実際に売却活動を進めるのは担当者でもありますので、担当者との相性も確かめておきましょう。細かな質問にもきちんと答えてくれる、積極的に提案を行ってくれるなど、売り主の立場に立って行動してくれる担当者を選ぶことが大切です。
仮に担当者があまり熱心でないときは、会社に伝えて担当者を変更してもらうことも念頭に置いておきましょう。
家の売却で失敗しないためには、不動産会社との相性はもちろん、住宅ローンや売却相場の把握など、さまざまな情報を知っておくことが大切です。家の売却の注意点について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
まとめ
家を売るときに後悔をしないためには、売却の手順やタイミングの見極め方をきちんと踏まえておくことが大切です。また、家を売却したときには売却代金がそのまま手元に残るわけではなく、売却にかかった費用や税金面についても考えておく必要があります。
そして、何より信頼できる不動産会社を見つけられるかが、家の売却を成功に導くために大きな要因となります。細かなことでもしっかり対応してくれる不動産会社を選べば、売却活動を進めるうえで安心できるでしょう。
不動産の一括査定サービスを活用すれば、複数の不動産会社の中から自分に合った会社を見つけられます。効率的に家の売却を進めるために、是非活用してみましょう。
この記事のポイント まとめ
- 売りたい家の相場を自分で調べる
- 不動産会社に査定依頼を行う
- 不動産会社と媒介契約を締結する
- 売却活動を進める
- 内覧対応を行う
- 買い主と売買契約を締結する
- 決済・引き渡し
- 確定申告を行う
詳しくは「1.家を売る手順と注意点」をご覧ください。
- 売却目的を決めておこう
- 売却希望時期・希望金額を伝えよう
- 家を売る方法を選ぼう(仲介・買取)
- 一括査定サービスを活用してみよう
詳しくは「3.家を売るタイミングを決める際の注意点」をご覧ください。
- 複数の会社を比較することが大事
- 家の売却を得意とする会社を選ぼう
- 担当者との相性もチェックしておこう
詳しくは「4.不動産会社を選ぶ際の注意点」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点