減収などの理由により、やむを得ず住宅ローンを滞納してしまうこともあるかもしれません。
しかし住宅ローンを滞納をしたとしても、早めに手を打てば最悪の状況に陥ることはありません。
この記事では、住宅ローンが払えないときの対処法をご紹介します。この記事を読めば、住宅ローン滞納時の流れを理解でき、苦境に陥らないための対策方法が分かります。
売却の検討も始めている方は『【入門編】不動産売却の全知識』も合わせてご覧ください。
- 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格”を見つけましょう
- 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
目次
1.住宅ローンを滞納するとどうなる?

借りたお金は返済スケジュールの通りに返していきたいものですが、失業や減収などの理由から、やむを得ず住宅ローンを滞納してしまう可能性はあります。
住宅ローンを滞納してしまうと以下のことが起こりえます。
- 優遇金利の解除
- 遅延損害金の発生
- 事故情報登録される(ブラックリスト)
- 一括返済を求められる
- 競売で強制的に売られる
一般的に、住宅ローンは優遇金利と言われる低い金利で借りられています。
ただ、住宅ローンの滞納をすると優遇金利を解除されてしまいます。
滞納期間中は、遅延損害金が発生し続け、2~3カ月の滞納が続くと信用情報機関で事故情報登録がされます。
事故情報登録とは、俗にいうブラックリストのことで、口座開設や新規の借り入れなどに制限がかかってしまいます。
金融機関対応によって期間は異なりますが、3~6カ月程度の滞納で一括返済が要求され、それも返済できなければ競売の手続きが行われます。
競売が行われると、オークション形式で強制的に不動産を売却され、最終的に強制立ち退きとなります。
2.【時系列】住宅ローン滞納による競売までの流れ

住宅ローンを滞納してから半年~1年程度対応できずに放置すると、最終的に自宅が競売にかけられてしまいます。
では、住宅ローンの滞納は何回まで許容され、最終的に競売になるまでにどの程度の期間がかかるのでしょうか。
ここからは、住宅ローンの返済を滞納した後、競売になるまでの流れを時系列で見ていきましょう。
- 【1~30日】遅延損害金の発生・優遇金利の解除
- 【1〜2ヶ月】電話や支払い請求書が届く
- 【2〜3ヶ月】督促状が届く
- 【3〜6ヶ月】催告書・期限の利益喪失
- 【6ヶ月】保証会社の代位弁済
- 【6〜10ヶ月】競売開始決定通知が届く
- 【10ヶ月〜】期間入札の通知が届く
【1~30日】遅延損害金の発生・優遇金利の解除
滞納の1日目から遅延損害金が発生します。住宅ローンの遅延損害金は多くの場合で年14%程度です。
滞納額が10万円であれば、1日38円、1カ月でも1166円と高くありませんが、滞納額が増えれば雪だるま式に膨れ上がるので注意しましょう。
また、住宅ローンの滞納により優遇金利が解除されてしまいます。
具体的にどれほどの滞納で優遇金利を解除するかは、金融機関それぞれの裁量にかかっているため、明確にお答えすることができません。
ただ、1~2日程度の滞納であればまず問題なく、中には1度目の滞納であれば、事情を考慮して多めに見てくれる金融機関もあります。
反対に、累積2度目の滞納や、無断の長期滞納は要注意です。
滞納の理由を連絡しないだけでも、金融機関への心象が悪くなるため、早期に優遇金利を解除される可能性もあります。
【1〜2ヶ月】電話や支払い請求書が届く
住宅ローンの返済を滞納すると、金融機関から支払い請求書が届きます。この時点で延滞分を返済できればさほど大きな問題にはなりません。
ただし、住宅ローンのほかにクレジットカードの支払いの遅れなどが重なっていると、事故情報に登録されることもあるため注意が必要です。
いわゆるブラックリストに掲載された状態となり、基本的にローンを借りることが難しくなります。
【2〜3ヶ月】催告書が届く
住宅ローンの滞納回数が増え、滞納から2~3カ月経つと、銀行から催告書が届きます。
1~2カ月程度で送られてくる支払い請求書と催告書の違いとして、一般邸に催告書は最後通牒としての役割を持っている点が挙げられます。
住宅ローンを滞納してから催告書が送られてきた場合、後はないと考える必要があるでしょう。
なお、この時点で滞納分を完済してしまえば、ブラックリストに事故情報が残る以上の問題は起こりません。
返済が難しい場合は、金融機関に支払い期限の相談をしましょう。
【3〜6ヶ月】催告書・期限の利益喪失
催告書が届いた後も対応できずに放置すると、「期限の利益喪失通知」が届きます。
期限の利益とは、住宅ローンを長期にわたった分割払いで返済する権利です。
期限の利益喪失通知が届いた後は、毎月返済ではなく、一括して返済しなければなりません。
一括返済ができなければ、金融機関は競売にむけて手続きを始めます。
【6ヶ月】保証会社の代位弁済
期限の利益が喪失した後、保証会社が債務者の代わりに金融機関に弁済を行います。これを代位弁済といいます。
代位弁済をすることで、債務者から金融機関への債権が消失しますが、引き続き保証会社に支払いを続けます。
【6〜10ヶ月】競売開始決定通知が届く
金融機関は競売の手続きを進めています。
早くて滞納6カ月で、競売開始決定通知が届きます。
競売はすぐに始まるわけではなく、裁判所が競売に向けて準備を進めている段階です。
【10ヶ月〜】期間入札の通知が届く
通知が届いた後、3カ月~半年程度で期間入札の通知が届きます。
この通知が届くと、間もなくして競売が開始され、入札も始まります。
期間入札の通知には、競売の入札期間と開札期間などが記載されています。
3.住宅ローンの支払いが苦しくなったときの対処法
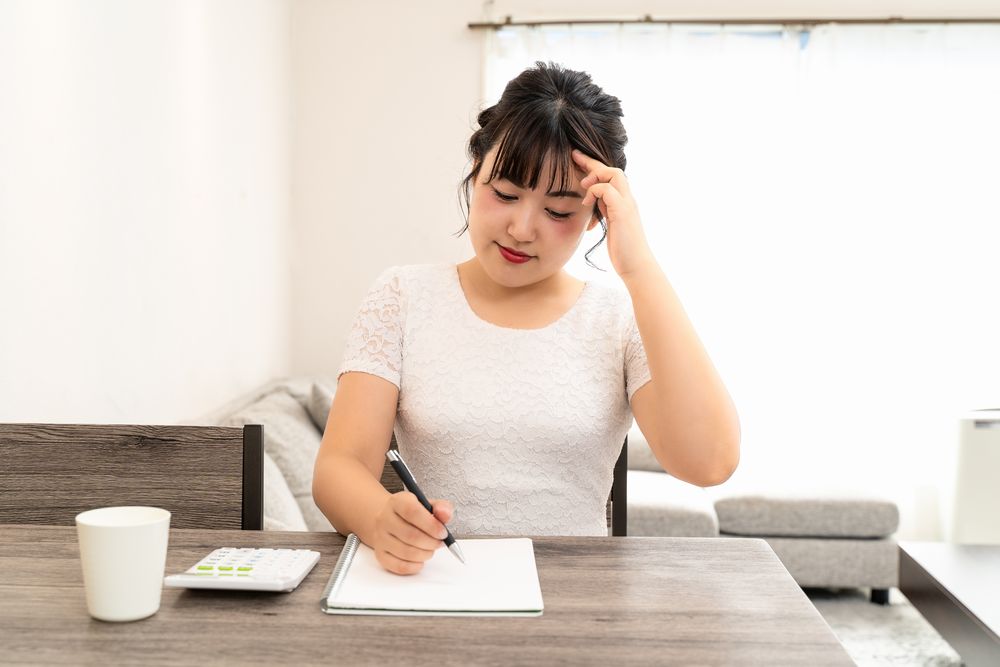
何らかの理由で住宅ローンの支払いが厳しくなった場合は、どうすればよいのでしょうか。
ここでは、住宅ローンの支払いが苦しくなった時の対処法を4つご紹介します。
- 家計の見直し
- 借入先に相談
- 住宅ローンの借り換え
- 売却する(売却後に住み続ける選択肢もあり)
- 国・自治体の支援制度を利用する
これらの対処法を順番に行っていきましょう。
3-1.家計の見直し
まずは、家計を見直し、住宅ローンの返済資金を生み出せないか検討する必要があります。例えば、毎月の固定費で使いすぎているものがないか確認してください。
具体的な見直しポイントは、以下の通りです。
- 外食にお金をかけすぎていないか
- 生命保険の保険料の額は妥当か
- 携帯電話の料金を安く抑えられないか
例えば、家族全員の携帯電話を格安SIMに変えるだけで月数万円安くなる可能性もあります。
まずは、無駄なことにお金を使っていないか確認することが大切です。
3-2.借入先に相談
借入先に相談することで、返済期間や支払額を調整してくれる可能性があります。金融機関としても、ローンが滞納され、最終的に競売になってしまうと、損失を被ることも多いからです。
競売は、購入後も前の入居者が居座っていることも多く売却に適した状態にありません。
そのため、一般の方法で売却するより安い6~7割ほどの価格で取引されます。
そのため、返済期間や支払額を調整することでローンをしっかり返済できることが伝われば、金融機関が対応してくれることもあります。
3-3.住宅ローンの借り換え
住宅ローンの借り換えを検討するのも一つの方法です。
例えば、全期間固定金利で借りている方が、変動金利に借り換えるなどすると、毎月返済額を大きく抑えられる場合があります。
ただ、ローンの借り換えには多くの手数料がかかるため、資金に余裕がない方にはおすすめできません。
ローンの滞納前で資金があり、金利を1%近く減らせる場合は、借り換えを前向きに検討してみましょう。
3-4.売却の検討(売却後住み続ける選択肢も)
住宅ローンの返済が厳しくなってきたら、早めに売却を検討するのも一つの方法です。
ただし、不動産を売却するには、原則として住宅ローンの完済が必要です。
売却金額と手持ちの資金を合わせて、物件の引き渡し日に住宅ローンを完済しましょう。
リースバックという売却方法なら、売却後も家に住み続けることも可能です。
リースバックは、不動産を買い上げた不動産会社に、賃料を支払うことで賃貸として住みなおす方法です。
また、住宅ローンの完済が必須といいましたが、金融機関が売却に同意している場合はその限りではありません。
抵当権を設定している債権者の合意を得て行う売却を、任意売却と言います。
詳しくは本記事4章をご覧ください。
3-5.国・自治体の支援制度を利用する
国や自治体は、生活が困難な方を支援する借り入れ制度を展開しています。
無金利から1.5%程の低金利で借り入れることができるため、家計が急変した場合の利用がおすすめです。
例えば、『総合支援資金』や『緊急小口資金貸付』なら、保証人をつけることで無金利で借り入れを行えます。
ただし、カードローンなどの高金利な借り入れで住宅ローンを賄うのは危険ですので注意しましょう。
低金利の住宅ローンが、高金利な借金に入れ替わるだけで、債務は確実に膨らみやすくなります。
総合支援資金や緊急小口資金貸付について詳しくは『政府広報オンライン:生活福祉資金貸付制度』をご覧ください。
4.競売を回避!任意売却の検討時に知っておきたいポイント

原則として、不動産は住宅ローンを完済しないと売却できませんが、金融機関の合意が得られれば例外的に売却ができます。
こう言った売却方法を任意売却と言います。
競売はオークション形式のため、場合によっては本来の価値の50%~60%で売買される場合もあります。
一方で任意売却は、通常の売却同様に売り出せるので、より高い価格で売却できます。
任意売却は、住宅ローン滞納者への例外的な措置であり、競売を回避する手段でもあります。
ただし、任意売却中も競売の手続きを進行していくため、競売の開札日前日までに売却を達成しなければいけません。
任意売却には金融機関の交渉があり、かつタイムリミットもあるため、任意売却が得意な不動産会社に依頼することが重要です。
できる限り複数の不動産会社を比較して、実績豊富で信頼できる不動産会社を選びましょう。
一括査定サービスの「IELICO(イエリコ)」なら、たった1分の簡単な情報入力で、最大6社の不動産会社に査定を依頼できます。
不動産会社を比較を行う時間を短縮させたい方は是非ご利用ください。

イエリコはカンタンな情報を入力するだけで、全国の優良な不動産会社2,500社のなかから、6社を選んでまとめて査定依頼ができます。
ぜひイエリコで比較して、信頼できる最適な不動産会社を見つけてください。
この記事のポイントまとめ
住宅ローンを滞納すると以下のようなことが起こり得るので注意してください。
- 支払い請求や催告書を経て、最終的には競売されてしまう
- 滞納すると損害遅延金を支払う必要がある
- 滞納するとブラックリストに載るためローンを組めなくなる
詳しくは「1.住宅ローンを滞納するとどうなる?」をご覧ください。
住宅ローン滞納後、競売までどのような流れを把握しておきましょう。
- 1~2カ月で請求書、2~3カ月で催告書が届く
- 3~6カ月経過すると期限の利益が喪失し一括返済以外の方法がなくなる
- 半年~10カ月程度で競売が開始する
詳しくは「2.【時系列】住宅ローン滞納による競売までの流れ」をご覧ください。
住宅ローンの支払いが苦しくなったとき、どのように対処するとよいのでしょうか。
- 食費や保険料など家計を見直す
- 住宅ローンの借り換えを検討する
- 売却を検討する
詳しくは「3.住宅ローンの支払いが苦しくなったときの対処法」をご覧ください。
任意売却の仕組みやメリット・注意点についても把握しておきましょう。
- 任意売却は競売前に銀行と相談して家を売却できる仕組み
- 相場より安くなりやすい競売と比べ、相場程度で売却できる可能性がある
- 任意売却は競売が開始するまでの間に売却まで完了する必要がある点に注意
詳しくは「4.競売を回避!任意売却の検討時に知っておきたいポイント」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点





