相続した土地の売却を検討するなかで「税金はいくらかかるのだろうか?」と、疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
土地の売却ではさまざまな税金が課されるため、正確な手残り金額を把握するためにも税金の額を把握する必要があります。
そこでこの記事では、相続した土地を売った時の税金の計算方法や各種節税対策を紹介します。
これを読めば適切に税金を抑える方法が分かり、手残り資金を増やせるでしょう。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「IELICO(イエリコ)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
目次
1.相続した土地を売った時の税金は3種類

まずは、相続した土地を売るとどのような税金がかかるかを確認していきましょう。
相続した土地を売った時の税金は以下の3つです。
【相続した土地を売却する時にかかる税金の種類】
- 登録免許税
- 印紙税
- 譲渡所得税・住民税
土地の価格や数、権利関係によって課される税金は異なるため、それぞれの概要と計算方法を把握しましょう。
1-1.登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記手続きをする際に課される税金です。
相続した土地に抵当権が付いている場合は、抵当権を抹消するための手続きが必要であり、以下の税金が課されます。
なお、一戸建の場合は土地と建物が別々に登記されているため、合計で2,000円の費用がかかります。
1-2.印紙税
印紙税とは不動産の売買契約書の作成に伴って課される税金です。
不動産の売買契約書は印紙税法に定める課税文書に該当するため、契約金額に応じた印紙を貼付する必要があります。
貼付する印紙の額は以下の表を参考にしてください。
| 契約金額 | 印紙税の額(軽減税率適用後) |
|---|---|
| 100万円超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超え5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超え1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円超え5億円以下 | 60,000円 |
2014年(平成26)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までの間に作成される契約書は、印紙税が軽減されます。
1-3. 譲渡所得税
譲渡所得税とは土地が購入時よりも値上がりし、売却時に利益が出た際に課される税金です。
土地の売却で利益が出た際は確定申告が義務付けられているため、売却した年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。
1-3-1. 譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は以下の計算式で算出します。
- 譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
- 譲渡所得 = 譲渡価額 – 取得費 – 譲渡費用
各用語の意味は以下の通りです。
- 譲渡価額:売却価格(売却金額)
- 取得費:購入時の諸費用の合計から減価償却費を差し引いたもの
- 譲渡費用:売却時の諸費用
1-3-2. 譲渡所得税の税率は5年を起点に変わる
譲渡所得税の税率は所有期間によって異なります。
| 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | |
|---|---|---|
| 所有期間 | 5年以下 | 5年超え |
| 所得税 | 30.63% | 15.315% |
| 住民税 | 9% | 5% |
譲渡所得税の税率が変わるのは所有期間が5年を超えてからですが、所有期間の判定は売却した年の1月1日時点である点に注意しましょう。
例えば、2018年(平成30年)5月1日に取得した土地を2023年(令和5年)8月1日に売却したとしても、2023年(令和5年)1月1日時点では所有期間が5年以下であるため短期譲渡所得となります。
長期譲渡所得の判定タイミングは「不動産を購入してから1月1日を6回迎える」と、考えるのがわかりやすいのでおすすめです。
また、相続した土地については相続を開始した日から数えるのではなく、被相続人(亡くなった方)が土地を取得した日を起点として考えます。
つまり、相続後すぐに売却したとしても、被相続人が土地を取得してから5年を超えていれば長期譲渡所得が適用されます。
被相続人が土地を取得してから5年を超えていないなら、5年を超えるまで待ってから売却するのも一つの節税対策です。
なお、土地を取得した際の契約書や領収書が見つからず取得費が分からない場合は、売却価格の5%を概算取得として計算します。
例えば、3,000万円で売却した土地の取得費がわからない場合は150万円を概算取得費とします。
親が土地を買ってから3〜5年間近であれば、5年経過するのを待つのもよい
2.相続した土地の売却に使える特例や控除
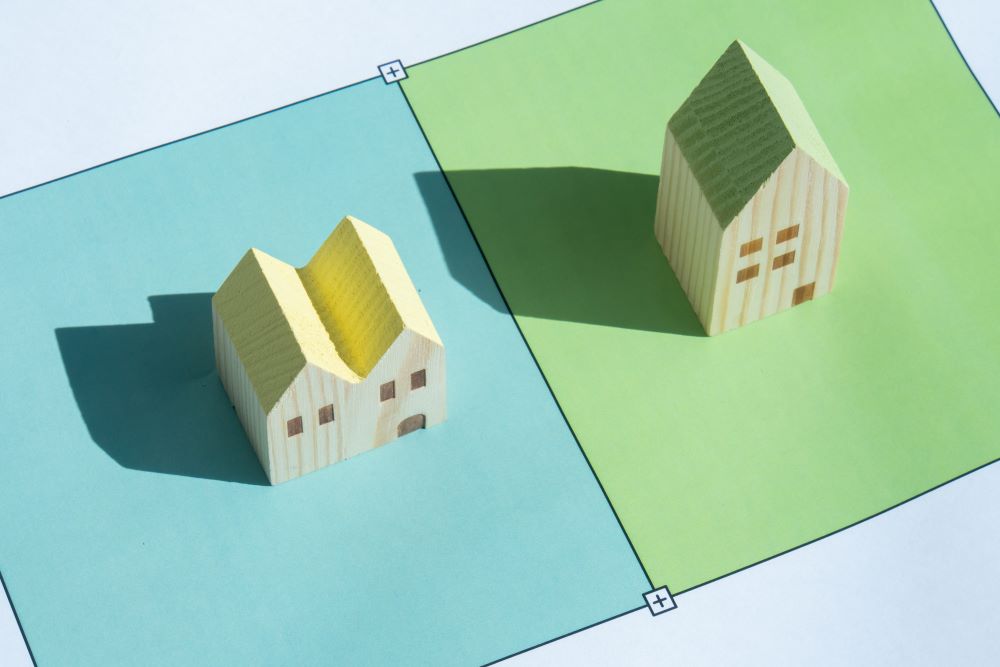
相続した土地を売ったときに特例や控除を利用すると、節税が可能になります。
相続した土地の売却で使える特例や控除は以下の通りです。
【相続した土地の売却に使える特例や控除】
- 相続空き家の3,000万円特別控除
- 取得費加算の特例
- 平成21年及び22年に取得した土地の1,000万円控除
- 低未利用土地等の100万円特別控除
- 農地を売った場合の特別控除
それぞれについて詳しく解説します。
2-1.相続空き家の3,000万円特別控除
相続空き家の3,000万円特別控除とは、相続で取得した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円が控除される制度です。
相続空き家の3,000万円特別控除が適用された場合の計算式は以下の通りです。
特別控除を適用した場合、売却価格から取得費や諸費用(仲介手数料や取り壊し費用など)を差し引いた額が3,000万円以内に収まるのであれば、税金はかかりません。
ただし特別控除を受けるには、相続を開始した日から3年後の年末までに売却する必要があります。
【相続空き家の3,000万円特別控除の要件】
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 相続の時から譲渡の時まで事業や賃貸、居住用として使用していないこと
- 一定の耐震基準を満たすこと
- 売却代金が1億円以下であること
- 同一の被相続人から相続または遺贈で同じ特例の適用を受けていないこと
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
参考:国税庁 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
控除の適用を受けるには、被相続人が亡くなる直前までに住んでいる必要があります。
介護老人福祉施設に入っている場合なども控除の適用は受けられますが、その間に賃貸物件として貸している場合は受けられません。
なお、相続後に相続人が対象不動産に住んでいた場合も控除は適用されません。
その場合、居住用財産の3,000万円控除の適用は受けられる可能性があります。
相続してから3年以内の売却であること
土地の売却はすぐに完了するものではないため、相続空き家の3,000万円特別控除の適用を受けたい場合は、期間内に売却ができるよう早めに行動しましょう。
参考:国税庁 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
2-2.取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、支払った相続税の一部(不動産に関する相続税)を取得に加算できる制度です。
譲渡所得の計算式は「譲渡価額 – 取得費 – 譲渡費用」であるため、取得費が増えるほど譲渡所得が減り税金を抑えられます。
なお、この特例は相続税が課された方に適用される特例です。
相続税は基礎控除や3,000万円特別控除があるため、実際に相続税を納める方はあまり多くありません。
取得費加算の特例が適用された時の計算方法は以下の通りです。
取得費加算の特例を受けるための要件は以下の通りです。
【取得費加算の特例の要件】
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること
- 財産を取得した人に相続税が課税されていること
- 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡していること
■節税ポイント
- 相続してから3年10ヶ月以内の売却であること
- 相続税の納入義務があること
2-3.平成21年及び平成22年に取得した土地の1,000万円控除
「平成21年(2009年)及び平成22年(2010年)に取得した土地1,000万円控除」とは、以下の条件に該当する場合、譲渡所得から1,000万円が控除される制度です。
- 平成21年(2009年)に取得した土地を平成27年(2015年)以降に譲渡
- 平成22年(2010年)に取得した土地を平成28年(2016年)以降に譲渡
控除が適用された場合の計算方法は以下の通りです。
この控除は平成20年(2008年)に起きたリーマンショックの景気対策として導入された制度であり、法人も利用可能です。
主な要件は以下の通りです。
【平成21年及び22年に取得した土地の1,000万円控除の要件】
- 平成21年(2009年)1月1日から平成22年(2010年)12月31日までの間に土地等を取得していること
- 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと
- 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと
- 譲渡した土地が収用等の特別控除や、事業用資産を買い換えた場合の課税繰延べなど他の特例を受けていないこと
- 確定申告を行うこと
参考:国税庁 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
■節税ポイント
- 親が相続した土地を購入した時期を確認!
2-4.農地を売った場合の特別控除
農地を売った場合の特別控除とは、農業委員会のあっせんなどによって農用地区域内の農地を地域の担い手に売った場合に適用される控除です。
具体的な計算式は以下の通りです。
農地を売った場合の特別控除の控除額は、要件によって異なります。
■農地を売った場合の控除額と要件
| 譲渡後の利用方法 | 控除額 | 要件 |
|---|---|---|
| 農地 | 800万円 |
|
| 1,500万円 |
|
|
| 2,000万円 |
|
|
| 農地以外 | 5,000万円 |
|
3.売却時に発生する税金を節税するための対策

ここまで、土地を相続する際にかかる税金と使える特例・控除を見てきました。
この章では、さらに節税をするための方法をお伝えします。
相続した土地の売却で課される税金を少しでも減らすためには、以下のことを実践しましょう。
【少しでも節税するためにできる対策】
- 取得額がわかる書類を用意する
- すべての譲渡費用を売却額から差し引く
- ふるさと納税を利用する
それぞれについて詳しく解説します。
3-1.取得額がわかる書類を用意する
取得費がわからない場合、概算取得費として売却価格の5%で譲渡所得を計算しなければなりません。
本来の取得費よりも低い価格になる可能性が高く、譲渡所得が多くなるため金銭的に損をしてしまうでしょう。
被相続人が対象地を取得した時期が古い場合は資料を見つけるのが困難ですが、できる限り以下のような資料を集めておく必要があります。
【取得費用がわかる書類の例】
- 売買契約書
- 領収書
- 住宅ローンの返済履歴
- 住宅ローンの返済予定表
また、取得費とは土地の購入金額だけではありません。
以下のような費用も取得費に算入できるため資料を集めておきましょう。
【取得費として計上できる費用】
- 取得時の仲介手数料
- 取得時の印紙代
- 登録免許税や不動産取得税
- 土地の測量費
- 建物の解体費用 など
3-2.すべての譲渡費用を売却額から差し引く
相続した土地を売却したと時にかかった譲渡費用も、売却額から差し引いて計上できます。
具体的には以下のような費用です。
【売却額から差し引ける譲渡費用】
- 売却時の仲介手数料
- 売却時の印紙代
- 借家人に家屋を明け渡してもらう時に支払う立退料
- 土地を売るための建物解体費用
- 地主の承諾をもらうために支払った名義書換料
なお、譲渡費用は売るために直接かかった費用であるため、修繕費や固定資産税などは譲渡費用に含まれません。
3-3.ふるさと納税を利用する
ふるさと納税とは、自分の好きな自治体を選んで寄付をする制度です。
寄付した金額は自己負担の2,000円を除き住民税や所得税から控除されます。
不動産の譲渡所得税の内訳は所得税と住民税であるため、ふるさと納税を利用することで税負担を抑えられます。
ただし、ふるさと納税は所得税の還付や住民税の先払いであるため、実質的な節税効果はありません。
不動産を売却した翌年に増える住民税を抑えたい方は、ふるさと納税で対策しましょう。
ふるさと納税は確定申告を行うと所得税・住民税から控除されますが、確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」を使う場合は、住民税のみの控除となります。
控除される金額に数円程度の違いはありますが、基本的にはどちらも同じ額の控除を受けられます。
なお、ふるさと納税には所得に応じた限度額があるため、ふるさと納税サイトのシミュレーションを利用して限度額を調べてみましょう。
4. 相続した土地を売る時に名義変更する手順

土地を相続する際は名義変更が必要です。
相続した土地を売る時に行う名義変更は、以下の手順で行います。
- 相続人を確認する
- 遺産分割協議を行う
- 必要書類を集め、提出書類を作成する
- 法務局に申請する
- 登記識別情報通知を受け取る
まず、相続が発生したら被相続人の戸籍謄本等を取得し相続人を確認しましょう。
相続人の確認が取れたあとは遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要になるため、相続人が多いと協議に時間がかかる場合があります。
次に法務局へ提出する以下の書類を準備しましょう。
| 書類 | 取得先 | 費用 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 法務局 | 480〜600円 |
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 450円 |
| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場 | 300円(自治体による) |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人の本籍地の市区町村役場 | 450円 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 相続人の住所地の市区町村役場 | 390〜450円 |
| 不動産を相続する人の住民票 | 相続人の住所地の市区町村役場 | 300円(自治体による) |
| 不動産の固定資産評価証明書 | 不動産の所在地の市区町村役場 | 300円(自治体による) |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 | ー |
| 相続登記申請書 | 法務局 | ー |
上記の書類が揃い次第法務局に申請を行います。
法務局での手続きにかかる時間は概ね1〜2週間程度であり、手続きが完了次第「登記識別情報通知」が発行されます。
5.【売却のタイミング別】税金の支払い額をシミュレーション

ここからは売却のタイミング別に税金の支払い額をシミュレーションします。
シミュレーション内容を参考に、自身のケースに当てはめて考えてみましょう。
シミュレーション内容は以下の通りです。
- 両親が土地を取得した時期:1989年(平成元年)
- 両親が土地を取得した費用:600万円
- 相続後の状態:空き家
- 相続した土地の売却額:1,800万円
- 相続した土地の売却にかかった費用:150万円(印紙税、仲介手数料、登記費用など)
5-1.相続してから5年未満の場合の税金
相続空き家の3,000万円特別控除は、相続を開始した日から3年後の年末まで適用可能です。
そのため、相続してから5年未満の場合は3,000万円特別控除が適用される可能性があります。
なお、被相続人が5年を超える期間所有しているため、税率は長期譲渡所得です。
- 譲渡所得:売却額1,800万 -(取得費600万円 + 売却にかかった費用150万円)= 1,050万円
- 3,000万円特別控除適用後の税金:0円
譲渡所得が1,050万円≦3,000万円であるため、3,000万円特別控除が適用された場合非課税となります。
5-2.相続してから5年以上経過している場合の税金
相続してから5年以上経過している場合、相続空き家の3,000万円特別控除は適用されません。
- 課税対象額:売却額1,800万 -(取得費600万円 + 売却にかかった費用150万円)= 1,050万円
- 所得税:1,050万円 × 15.315%(長期譲渡所得)= 160万8,075円
- 住民税:1,050万円 × 5% = 52万5,000円
- 支払う税金の合計:所得税160万8,075円 + 住民税52万5,000円=213万3,075円
同じ条件であっても相続空き家の3,000万円特別控除が使えないため、合計213万3,075円の税金を納める必要があります。
ご自身が住みたいなどの特別な理由がない場合は早めの売却をおすすめします。
6.相続した土地を売却するタイミングの見極め方

ここまでの内容で相続した土地を急いで売却したほうがいいのか、それともすぐには売却しなくてもいいのかと悩んでいる方も多いでしょう。
そこで本章では、相続後急いで売却を始めたほうがいいケースと、そうではないケースについて紹介します。
6-1.相続した土地を急いで売却したほうがいいケース
相続した土地を急いで売却したほうがいいケースは以下の通りです。
- 相続した土地の使い道がない場合
- 相続税納税義務者だが資金がない場合
- 相続税を納税した場合
- 売却時にできるだけ税金の特例を受けたい場合
土地は持っているだけで固定資産税がかかるうえに、建物を取り壊して更地にすると固定資産税が跳ね上がります。
老朽化した建物を管理する手間とコストもかかると考えましょう。
急いで売却したほうが、余計なコストをかけずに済みます。
また、相続税を納めた方は早い段階で売却しなければ「取得費加算の特例」が適用されなくなる点に注意しましょう。
土地をできるだけ早く売りたいなら、優良な不動産会社を見つけることが重要です。
優良な不動産会社を見つけるためには、複数の結果を比較できる「不動産一括査定サイト」の利用をおすすめします。
複数社への査定は、NTTデータグループが運営する一括査定サイト「IELICO(イエリコ)」から依頼すると便利です。
イエリコはカンタンな情報を入力するだけで、全国の優良な不動産会社2,500社のなかから、6社を選んでまとめて査定依頼ができます。
ぜひイエリコで比較して、信頼できる最適な不動産会社を見つけてください。
6-2.相続した土地をすぐに売却しなくていいケース
相続した土地をすぐに売却しなくていいケースは以下の通りです。
- 資金に十分な余裕がある場合
- 相続した土地を活用して利益を得られる見込みがある場合
売却せずとも固定資産税や相続税を払えるだけの資金的余裕がある方は、売り急ぐ必要はありません。
また、今後人に貸して収益を得るなど、相続した土地を有効活用する算段がある方は所有していても良いでしょう。
この記事のポイントまとめ
相続した土地の売却で使える特例や控除は以下の通りです。
- 相続空き家の3,000万円特別控除
- 取得費加算の特例
- 平成21年及び22年に取得した土地の1,000万円控除
- 低未利用土地等の100万円特別控除
- 農地を売った場合の特別控除
詳しくは「2.権利証を紛失しても不動産を売却する方法」をご覧ください。
相続した土地の売却で課される税金を少しでも減らすためには、以下のことを実践しましょう。
- 取得額がわかる書類を用意する
- すべての譲渡費用を売却額から差し引く
- ふるさと納税を利用する
詳しくは「3.売却時に発生する税金を節税するための対策」をご覧ください。
相続した土地を売る時に行う名義変更の手順は以下の通りです。
- 相続人を確認する
- 遺産分割協議を行う
- 必要書類を集め、提出書類を作成する
- 法務局に申請する
- 登記識別情報通知を受け取る
詳しくは「4.相続した土地を売る時に名義変更する手順」をご覧ください。
相続した不動産を売却する際の税金は、相続空き家の3,000万円特別控除の適用を受けられるかどうかで大きく異なります。
詳しくは「5.【売却のタイミング別】税金の支払い額をシミュレーション」をご覧ください。
売却を急いだほうがいいかどうかは、手持ち資金の量や今後の土地活用の方針によって異なります。
詳しくは「6.相続した土地を売却するタイミングの見極め方」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点





