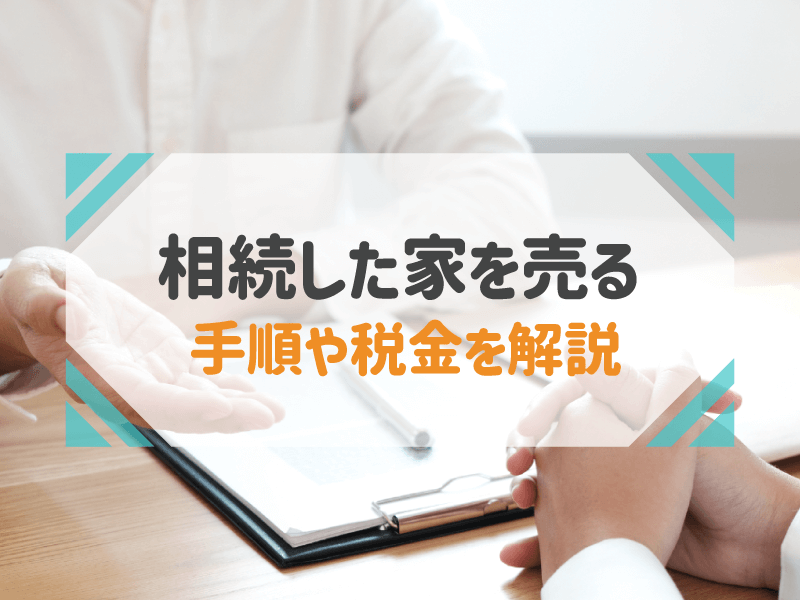実家を相続したものの、住んだり活用したりする見込みがないときは、売却を検討することもあるでしょう。
とはいえ、相続した家を売るには「相続登記」など特別な手続きが必要です。
そのため、売却をためらわれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、相続した家を売却するか迷っている方に向けて、相続の手順や必要なこと、注意点などをご紹介します。
これを読むことで、失敗なく相続した家を売却できるでしょう。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「IELICO(イエリコ)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
目次
1.相続した家を売る流れ

相続した家を売却する場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
大きく分けると、相続時は「家を相続する」「相続した家を売却する」の順に手続きを進めます。
ここでは、手続きの大まかな流れを見ていきましょう。
- 相続の手続きの流れ
- 名義変更してから売却するまでの流れ
1-1. 相続の手続きの流れ
相続の手続きの流れは以下の通りです。
- 遺言所の有無の確認
- 遺産と債務の確認
- 相続放棄の判断:相続開始から3ヵ月以内
- 準確定申告:相続開始から4ヵ月以内
- 名義変更
詳しく見ていきましょう。
1-1-1.遺言所の有無の確認
まずは、遺言状の有無を確認します。
遺言がある場合は、遺言書に則って遺産を分割しなければなりません。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決める必要があります。
1-1-2.遺産と債務の確認
次に、故人の財産について確認します。
現金や不動産・有価証券などプラスの財産だけでなく、債務などマイナスの財産もあるのでもれなく調べてください。
個人の財産が多く、遺言もない場合は、遺産を調べるのも難しくなるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
1-1-3.相続放棄の判断
マイナスの遺産が多い場合などで検討するのが「相続放棄」です。
相続放棄することで、債権などのマイナスの財産を相続しなくてもよくなります。
ただし、相続放棄はプラスの財産も放棄することになる点に注意が必要です。
相続放棄の手続きを済ませると、あとでプラスの財産があると気づいても撤回できません。
また、自分が相続放棄することで、マイナスの財産を別の相続人が相続することになるので、事前に了承を得ておく必要があるでしょう。
相続放棄手続きには期限があり、相続の開始を知ったから3ヵ月以内でなければ放棄できません。
それまでの期間に遺産の有無を確認して、相続するか放棄するかを早めに判断してください。
1-1-4.準確定申告
個人の所得については、1月1日から死亡した日までの所得を相続人が代わって申告する「準確定申告」を行わなければなりません。
準確定申告は、相続開始を知った日から4ヵ月以内と期日が決まっているので、必要な場合は期日までに申告してください。
1-1-5.名義変更
遺言書や遺産分割協議の結果、相続することになったら、不動産の名義を変更しなければなりません。
売却するには不動産の名義を変更する必要があるので、早めに手続きを進めましょう。
また、売却をしない場合でも名義を変更していないと、後々トラブルになったり二次相続で登記が複雑になったりするおそれもあるので、早めに登記しておくことをおすすめします。
なお、相続登記は2024年4月からは義務化されるので、忘れると過料の罰則が科されます。
1-1-6.相続税の申告と納付
相続財産に応じて相続税を申告・納税します。
相続税は相続開始の翌日から10ヵ月以内に納めなければなりません。
相続財産が不動産ばかりで現金が少ないケースだと相続税に対応できないケースもあるので、早めに売却を進める必要があります。
名義変更までに行う手続きで期限があるのは、以下の通りです。
| 手続き | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続財産をすべて放棄する手続き | 相続開始から3ヵ月以内 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する手続き | 相続開始から3ヵ月以内 |
| 準確定申告 | 被相続人の所得の申告 | 相続開始から4ヵ月以内 |
遺言書の確認や遺産分割協議などには期限はありません。
しかし、遺産分割を早めに決めなければ、そのあとの相続放棄手続きや相続税申告などもできなくなってしまうため、相続放棄期限の3ヵ月までには遺産分割について決定しておくことが大切です。
1-2. 名義変更してから売却するまでの流れ
次に、名義変更してから売却までの流れを見ていきましょう。
大まかな流れは次の通りです。
- 名義変更
- 査定
- 不動産会社と媒介契約
- 売却活動
- 売買契約
- 決済と引き渡し
- 相続税の申告と納付:相続開始から10ヵ月以内
相続した家であっても、売却自体は通常の不動産売却と流れは変わりません。
一般的に、不動産売却は媒介契約してから3ヵ月~半年ほど期間がかかります。
相続税の納付期限は相続開始から10ヵ月以内と決まっているため、売却したお金で相続税を支払う予定がある場合は、期限内に売却できるように早めに売却を進める必要があります。
1-2-1.名義変更
不動産は原則として名義人でなければ売却できません。
まずは、不動産の名義を変更して売却活動に進みましょう。
1-2-2.査定
不動産会社を選ぶために、不動産会社に査定依頼をします。
査定価格は各社で異なるため、複数社に依頼して比較検討するのがおすすめです。
1-2-3.不動産会社と媒介契約
売却を依頼する不動産会社が見つかったら、媒介契約を結びます。
媒介契約には、次の3つの契約形態があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
一般媒介契約は、自分でも買い手を選べ、複数の不動産会社を契約できるなど比較的自由が利きます。
ただし、1社に絞らないことで、不動産会社が積極的に売買をサポートしてくれないなどのデメリットもあるので、注意してください。
専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、1社としか契約できないなど制約も多くなりますが、「売却を熱心にサポートしてくれる」「販売状況の定期的な報告が義務付けられている」などのメリットがあります。
それぞれのメリット・デメリットを比較して適切な契約形態を選んでください。
1-2-4.売却活動
媒介契約後は不動産会社が売却活動を進めていきます。
購入希望者が現れると内覧の対応が必要になるので、片付け・清掃などの準備を行いましょう。
1-2-5.売買契約
買主が見つかれば、売買契約に進みます。
売買契約時には、買主から手付金を受け取るのが一般的です。
多くのケースでは、この時点で不動産会社に仲介手数料の半額を支払います。
1-2-6.決済と引き渡し
売買契約から1ヵ月後ほどで決済と引き渡しが行われます。
引き渡し時に不動産会社に仲介手数料の残金を支払うのが一般的です。
1-2-7.相続税の申告と納付
相続財産に応じて相続税を申告・納税します。
相続税は、相続開始から10ヵ月以内に納めなければなりません。
現金が手元にあれば、売却の進捗に関わらずいつでも納税できます。
相続財産が不動産ばかりで現金が少ない場合、相続税を払えない可能性もあるので、早めに売却を進める必要があります。
2.相続した家を売るときにかかる税金

相続した家を売却すると、次のような税金が課せられます。
- 相続税
- 登録免許税
- 印紙税
- 譲渡所得税
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1. 相続税
相続税は相続する財産にかかる税金です。
対象財産には、不動産だけでなく現金や有価証券なども含まれます。
相続税額は、以下の計算式で算出します。
相続税は、相続財産総額から法定相続人の人数に応じた「基礎控除額」を差し引いた額に対して税金が課せられます。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。
例えば、法定相続人が5人の場合、「3,000万円+600万円×5人=6,000万円」が控除されます。
相続税は、財産総額が基礎控除額を上回る場合にのみ課税されます。
2-2. 登録免許税
相続した不動産の名義を変更する際に、課税されるのが登録免許税です。
登録免許税の額は、以下の計算式で算出されます。
不動産の固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税納付書に記載されています。
2-3.印紙税
印紙税は、課税対象の文書を作成した際に収入印紙を貼付・消印して納付します。
不動産の売却の場合、売買契約書が印紙税の課税対象文書です。
印紙税は、作成した書類に記載されている金額(売買契約額)に応じて税額が異なり、一般的な不動産取引の価格帯での印紙税は次の通りです。
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減後税額 |
|---|---|---|
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
2024年3月31日までは軽減措置が適用され、軽減後の税額を納めます。
印紙税は、貼付忘れや消印忘れの場合、本来の税額の3倍の印紙税を納めなければならないペナルティが科せられるので、注意してください。
2-4.譲渡所得税
不動産売却で利益が出た場合、利益に対して譲渡所得税(所得税・住民税)が課税されます。
譲渡所得税=課税対象譲渡所得×税率
譲渡所得は、不動産を売却した額から購入にかかった費用である取得費と売却に掛かる費用の譲渡費用を差し引いた額です。
この額に対して、譲渡所得税の税率が課税されます。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なり、以下の通りです。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
相続の場合、被相続人が取得した日から所有期間が算出されます。
3.相続した家を売るときに譲渡所得税を控除できる各種特例

不動産売却に掛かる譲渡所得税は、高額になるケースもあります。
このようなときに、各種控除を適用すると譲渡所得税額を抑えられます。
譲渡所得税で控除できる特例は次の通りです。
- 取得費加算の特例
- 空き家売却の特例
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1.取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、譲渡所得を算出する際の取得費に相続税額の一部を加算できる特例です。
加算した相続税額分の譲渡所得を抑えられるので、節税ができます。
取得時加算の特例の適用条件は次の通りです。
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
次の条件で売却した場合を見てみましょう。
- 売却額:5,000万円
- 取得費:3,000万円
- 譲渡費用:500万円
- 所有期間10年
通常の譲渡所得税は、次のように計算できます。
- 譲渡所得額=5,000万円-(3,000万円+500万円)=1,500万円
- 譲渡所得税=1,500万円×20.315%=3,047,250円
一方、相続税として1,000万円を納税している場合は以下の通りです。
- 譲渡所得額=5,000万円-((3,000万円+1,000万円)+500万円)=500万円
- 譲渡所得税=500万円×20.315%=1,015,750円
3-2.空き家売却の特例
空き家売却の特例は、相続した家が空き家となっている場合に、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
空き家の条件は次の通りです。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
相続開始までに親のみが住んでいる居住用の物件であることが条件です。
相続開始前に老人ホームなどに入所していた場合でも、一定の条件を満たすことで特例を適用できます。
また、売却についても売却期間や売却額に条件があるので、注意してください。
- 売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
4.相続した家を売るのに必要な書類
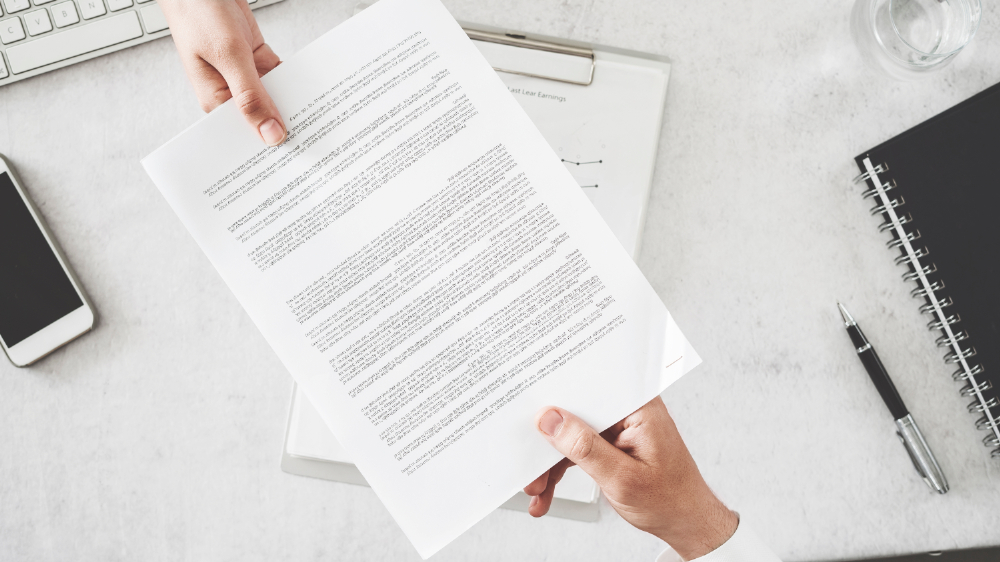
相続した家を売却する場合、さまざまな書類が必要です。
書類によっては準備に時間が掛かるものもあるので、事前に必要な書類を理解してスムーズに準備できるようにすることが大切です。
必要な書類は次の通りです。
| 不動産会社に売却依頼するとき |
|
|---|---|
| 引き渡し時 |
|
必要な書類は、売る物件がマンションなのか戸建てなのかによっても異なります。
また、引き渡し時などで必要な書類が揃っていないと手続きが進められない可能性もあるので、注意してください。
事前に不動産会社に確認して、準備漏れがないように早めに準備に取り掛かることをおすすめします。
5.相続した家の分割方法

相続人が一人であれば、すべてを相続するだけで済みます。
また、相続財産が現金のみであれば、相続人で平等に割ることもできるでしょう。
しかし、家を相続し他にも相続人がいる場合は、遺産の分割が難しくなるので、注意が必要です。
相続財産が不動産の場合、次の4つの分割方法があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
詳しく見ていきましょう。
5-1.現物分割
現物分割とは、相続財産を現物で分割して相続人で分ける方法です。
土地であれば、分筆してそれぞれの相続人が所有するといったケースがあります。
デメリット・・・公平に分割するのが難しい
現物分割であれば、それぞれの相続人が単独で名義人になれるので、その後の売却や活用がしやすいというメリットがあります。
ただし、不動産の場合は現物を平等に分割するのは難しいので注意が必要です。
5-2.換価分割
換価交換は、売却した金額を相続人で分ける方法です。
デメリット・・・ 売却に時間や手間がかかる
換価交換であれば、売却したお金を分けるので平等に分けられるというメリットがあります。
ただし、売却に時間が掛かる場合や売却額でトラブルになるケースも珍しくないので注意してください。
5-3.代償分割
代償分割とは、不動産を相続した人が他の相続人に相続割合に応じた代償金を支払う方法です。
デメリット・・・ 代償金を支払うための現金が必要
代償分割であれば、代償金を支払うことで不動産を単独で所有できるというメリットがあります。
ただし、代償金支払いのための費用は相続人が負担することになるため、相続人に自己資金がなければ代償分割ができません。
5-4.共有分割
共有分割は、相続人が相続割合に応じて不動産の持分を所有する方法です。
デメリット・・・ 売却が難しく数次相続時にトラブルになりやすい
共有名義にするため、単独では不動産の売却ができません。
また、次の相続が発生すると名義人が雪だるま式に増えてしまい、トラブルに発展しやすくなるので注意が必要です。
不動産の物件内容や相続人の状況に応じて、適切な分割方法を選択する必要があります。
一般的に、不動産を売却する場合、換価交換や現物分割を選択するケースが少なくありません。
6.相続した家の名義変更の仕方
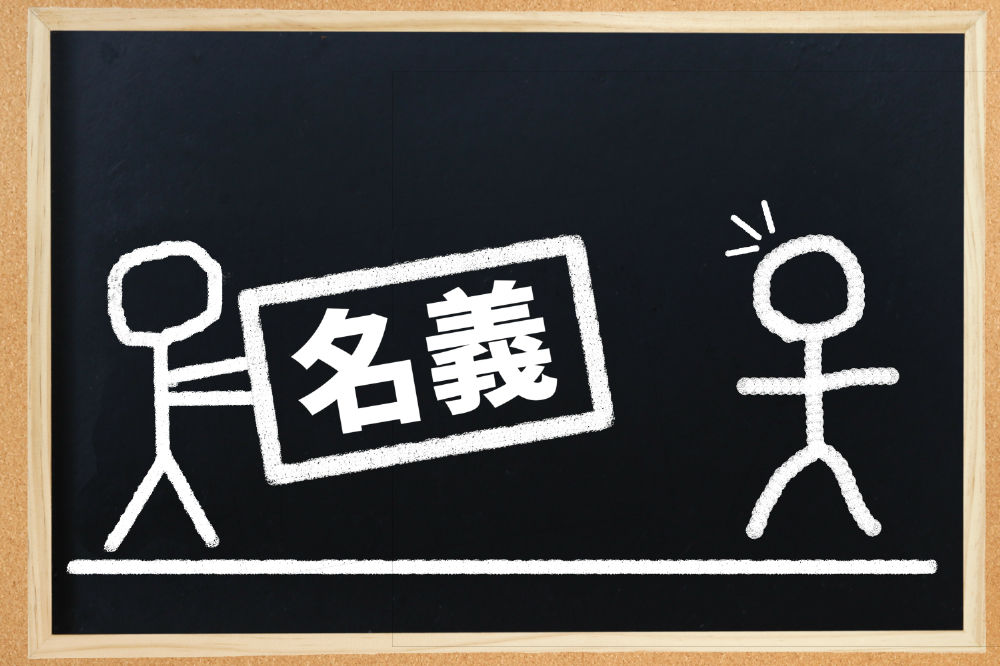
売却するためには相続後に名義変更が必要です。
ここでは、名義変更の手順を解説します。
- 不動産について確認する
- 相続人を確認する
- 必要な書類を用意する
- 提出書類を作成する
- 法務局へ提出する
順番に見ていきましょう。
6-1.不動産について確認する
まずは、相続する不動産について確認しましょう。
該当の不動産の登記事項証明書を取得し、名義人などの不動産情報を把握します。
6-2.相続人を確認する
次に、不動産を相続する人を決めます。
遺言があれば、遺言の通りに相続人が決まります。
しかし遺言がない場合は法定相続人全員で遺産分割評議を行い、相続内容を決めなければなりません。
遺産分割協議は法定相続人全員の合意が必要です。
相続人が後から見つかったなどの場合、協議をやり直さねければならないため、事前に相続人を洗い出しておきましょう。
6-3.必要な書類を用意する
相続人が決まれば、相続人が名義変更の手続きを進めていきます。
名義変更で必要な書類には、次のようなものがあるので準備してください。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 登記申請書 | 登記変更を法務局に申請する書類 |
| 遺産分割協議書 | 遺産分割協議の内容をまとめた書類 相続人全員の実印での捺印が必要 |
| 相続人全員の印鑑証明 | 遺産分割協議書の実印の証明のため |
| 被相続人の除籍謄本 | 相続人と被相続人の確認のために必要 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人の生存確認のため |
| 相続する人の住民証 | 本人の情報確認のため |
| 固定資産評価額 | 登録免許税算出のため |
6-4.提出書類を作成する
登記申請書類は自分で作成する必要があります。
申請書には決まった書式はありませんが、次のような項目の記載が必要です。
- 登記の目的
- 登記の原因
- 被相続人の名前
- 相続人の名前・住所・連絡先
- 不動産の情報
- 課税価格と登録免許税
登記申請書は法務局のホームページなどにテンプレートがあるので、参考にして作成するとよいでしょう。
作成後は登録免許税分の収入印紙が必要なので、用意して添付します。
6-5.法務局へ提出する
書類を用意したら、管轄の法務局に申請します。
申請方法は次の3つです。
- 窓口への持参
- 郵送
- オンライン(e-tax)
窓口での申請であれば、必要最低限のチェックを受けられその場で修正できる場合もあるので、可能であれば窓口での申請をおすすめします。
名義変更は必要書類が多く、申請書の作成も複雑になるので、司法書士などに依頼することを検討しても良いでしょう。
7.相続した家を売る際の注意点

売却するためには相続後に名義変更が必要です。
ここでは、名義変更をする際の注意点を解説します。
- 複数の不動産会社に依頼する
- 相続人が住む・住まないで適用できる特例が異なる
- 単独登記型は遺産分割協議書に換価分割目的であると明記しておく
- 共有名義の物件売却には権利者全員の同意が必要
- 3年以内に売却しないと特例が受けられない
- 所有期間は親が取得した日から計算する
- 取得費は親の購入費用をもとに計算する
詳しく見ていきましょう。
7-1.複数の不動産会社に依頼する
少しでも高値売却するためにも査定依頼は複数の不動産会社にすることをおすすめします。
特に、相続の場合は相続税の申告期限までに売却しなければならないため、スムーズに売却できる不動産会社を選ぶことも重要です。
できるだけ多くの不動産会社で見積もりをとって、査定額やサービス・実績など総合的に判断してください。
複数社に査定を依頼する際に便利なのが、NTTデータグループが運営する一括査定サイト「IELICO(イエリコ)」です。

イエリコはカンタンな情報を入力するだけで、全国の優良な不動産会社2,500社のなかから、6社を選んでまとめて査定を依頼できます。
ぜひイエリコで比較して、最適な不動産会社を見つけてください。
7-2.相続人が住む・住まないで適用できる特例が異なる
相続した家を売却した場合、売却益に対して税金が課せられます。
売却に掛かる税金は各種控除を適用できますが、売却する家に住む・住まないで適用できる特例が異なるので、注意してください。
| 相続人が住む場合 | 相続人が住まない場合 |
|---|---|
|
|
相続した家に相続人が住む場合、その家は相続人のマイホームとなり通常のマイホーム売却時に利用できる特例が適用されます。
反対に、住まずに売却する場合はマイホーム売却時の特例は利用できません。
この場合、先述した取得費用加算特例や空き家の3,000万円控除を適用することになります。
基本的には、住んでマイホーム扱いにしたほうが特例を適用しやすく節税できる可能性が高いです。
7-3.単独登記型は遺産分割協議書に換価分割目的であると明記しておく
売却額を相続人で分割する換価交換には、「共同登記」か「単独登記」の2種類があります。
- 共同登記:不動産を共有でもって売却する方法
- 単独登記:いったん1人が不動産を所有し、売却後に金銭で分配する
共有登記の場合、売却に登記した人全員の立ち合いが必要など不都合が多いため、単独登記を選ぶケースが少なくありません。
ただし、単独登記の場合、売却額を登記人が受け取った後に他の相続人に分配するという形になるため、贈与とみなされてしまい、贈与税が課せられる可能性が高くなるので注意が必要です。
単独登記での換価分割が贈与とみなされないようにするためには、遺産分割協議書に換価分割が目的であることを明記しておく必要があります。
7-4.共有名義の物件売却には権利者全員の同意が必要
不動産を売却するためには、名義人全員の合意が必要です。
そのため、共有名義の不動産を売却する場合は、媒介契約時や売買契約時に全員の同意を得なければなりません。
基本的には、契約時に名義人全員が立ち会います。名義人の1人が遠方に住んでいるなどの場合、売却がスムーズに進められない可能性があるので注意しましょう。
7-5. 3年以内に売却しないと特例が受けられない
取得費用加算と空き家売却3,000万円控除を適用する場合、売却に期限があるので注意しなければなりません。
売却条件は次の通りです。
3年を超えると特例が適用できないので、早めに売却を進めるようにしてください。
7-6.所有期間は親が取得した日から計算する
売却した利益に課せられる譲渡所得税は、物件の所有期間によって税率が異なります。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
この所有期間は、被相続人が家を所有した日が起算日となります。
また、売却した日ではなく売却した年の1月1日が基準となる点にも注意が必要です。
例えば、2015年6月1日に取得した物件を2020年6月31日に売却した場合、実際の所有期間は5年を超えていますが、基準日である2020年1月1日時点では5年経過していません。
そのため、上記の場合は短期譲渡所得の高い税率が課せられます。
譲渡所得の特例を使って控除できる場合は、税額も大きくならないでしょう。
しかし、特例を使わない場合は、基本的に5年経過してから売却するほうが税金を抑えられます。
7-7.取得費は親の購入費用をもとに計算する
譲渡所得額の算出の取得費は、親が購入した費用を元に計算します。
建物の場合は購入した価格ではなく、減価償却分を差し引いた額を計上するため、注意してください。
ちなみに、土地は減価償却しないため、購入価格そのままで計上できます。
しかし、親の購入が数十年前でその時の価格が分からないケースも珍しくありません。
購入費用が分からない場合は、概算取得費として売却額の5%を計上します。
概算取得費で計上すると実際の取得費よりも少なくなってしまって利益が出る可能性があるので、できるだけ取得費が分かる書類を探してください。
代替え手段として、次のような書類・方法が挙げられます。
- 販売元から受け取った売買契約書の写し
- 売主や仲介した不動産会社から受け取った売買契約書の写し
- 通帳の出勤履歴
- 住宅ローンの契約書から推測する
- 抵当権設定額から推測する
ただし、代替書類によっては税務署から否認されてしまう可能性があります。
事前に税務署に代替書類について確認してください。
この記事のポイントまとめ
相続した家を売る流れは以下の通りです。
- 遺言書の有無を確認する
- 単純承認や相続放棄など3ヶ月以内に相続の方法を確定する
- 10カ月以内に確定申告して相続税を納める
詳しくは「1.相続した家を売る流れ」をご覧ください。
相続した家を売るときに譲渡所得税を控除できる特例には以下のようなものがあります。
- 相続税の取得費加算の特例
- 空き家売却の特例
- 相続税の取得費加算の特例は3年の期限がある点に注意が必要
詳しくは「3.相続した家を売るときに譲渡所得税を控除できる各種特例」をご覧ください。
相続した家を売る際の必要書類には以下のようなものがあります。
- 不動産売却や引き渡しなど通常の手続きで必要な書類を用意する必要がある
- 不動産会社に売却依頼する際には、登記簿謄本や売買契約書が必要
- 引き渡し時には本人確認書類や実印・印鑑証明書が必要
詳しくは「4.相続した家を売るのに必要な書類」をご覧ください。
相続した家を名義変更するためには、以下のように手続きを進めます。
- 不動産と相続人を確認する
- 必要書類を準備する
- 提出書類を作成し法務局へ提出する
詳しくは「6.相続した家の名義変更の仕方」をご覧ください。
相続した家を売る際の注意点やポイントとして、以下のようなものが挙げられます。
- 複数の不動産会社に売却を依頼す
- 共有物件の売却には名義人全員の同意が必要になる
- 相続の申告期限から3年以内に売却しないと譲渡所得税を軽減する特例の適用を受けられない
詳しくは「7.相続した家を売る際の注意点ポイント」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点