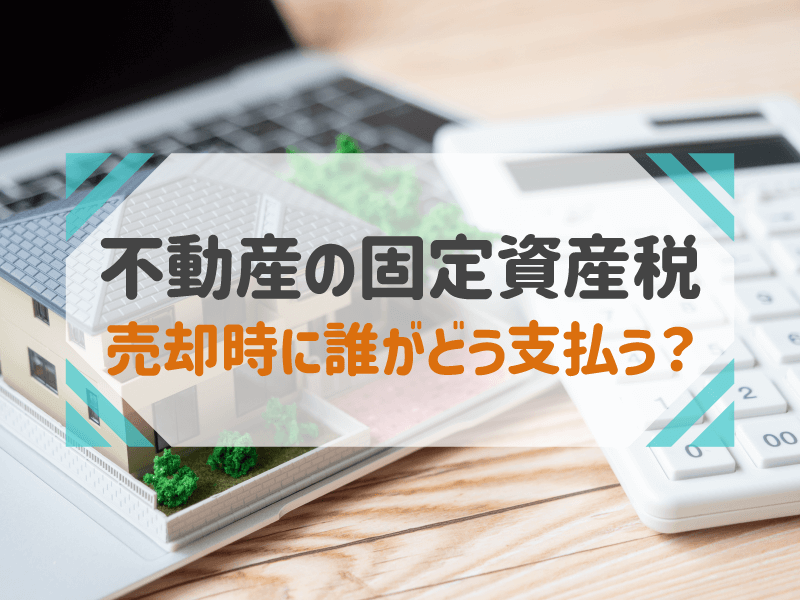不動産を売却する際には、誰がどの費用をいくら支払うかを把握しておくことが重要です。
とはいえ、はじめて家を売る場合はお金に関する不明点があるかもしれません。
なかでも、売却した不動産の固定資産税を「誰がいくら払うか」は、非常にわかりにくいものです。
そこでこの記事では、「不動産の固定資産税はいつ誰が支払うのか」を解説した上で、計算方法や注意点をご紹介します。
これを読むことで、不動産売却時の固定資産税に関する不安が解消されるでしょう。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「IELICO(イエリコ)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
目次
1.固定資産税は誰が支払う?

固定資産税とは、固定資産の所有者が市町村に支払う税金のことです。
ここでいう「固定資産」とは、土地家屋のことを指すので、固定資産税は「土地家屋の所有者がその土地家屋の所在する市町村に支払う税金」になります。
固定資産税は、その年度の1月1日時点の所有者、つまり、不動産売却時の「売主」が1年分を支払います。
そのため、年度途中で不動産を売却した場合でも、その年度の固定資産税の納税義務はあくまで売主側にあるのです。
ただし、実際の不動産売買では、売主と買主間での固定資産税の費用負担の公平性を保つため、日割りで清算するのが一般的です。
固定資産税を分割で支払っている場合、不動産売却後の固定資産税は支払わなくても良いのではないかと疑問に思うかもしれませんが、1年分の固定資産税を支払わなければならないことに注意してください。
なお、土地家屋が「市街化区域」に所在する場合は、一般的に市町村への都市計画税の支払いも生じます。
この場合、固定資産税と都市計画税とを合わせた金額を日割り清算の対象とします。
1-1.売却時は日割り計算して折半するのが慣例
不動産の売却時の固定資産税の扱いに関しては買主との間で「日割り清算」をするのが一般的です。
具体的には、不動産の所有権が変更になる日を基準に、以下のように判別します。
- 所有権の変更日以前の分は売主負担
- それ以降は買主負担
例えば、7月1日に物件の決済(物件代金等の授受)と引き渡しを行う場合、通常は所有権の移転登記も7月1日となります。
その場合の固定資産税は以下のように日割り清算します。
- 6月30日までの分は売主負担
- 7月1日からの分は買主負担
ただし、その年度の納税は売主が行います。
そのため、日割り清算時には、買主負担分の金額を買主から売主に直接支払うのが一般的です。
また、固定資産税の負担額を算出する際には、「起算日」に注意しなければなりません。
不動産取引の商慣習上、東日本と西日本で起算日が異なるのです。
それぞれの起算日は以下の通りです。
- 東日本:1月1日
- 西日本:4月1日
例えば、7月1日に決済・引き渡しを行う場合の起算日及び日割り清算の負担は、以下の通りです。
【東日本の場合】
- 起算日:1月1日
- 売主負担:1月1日~6月30日(181日)
- 買主負担:7月1日~12月31日(184日)
【西日本の場合】
- 起算日:4月1日
- 売主負担:4月1日~6月30日(91日)
- 買主負担:7月1日~3月31日(274日)
このことからも分かるように、地域による起算日の違いによって売主・買主それぞれの負担金額が異なる点に注意が必要です。
また、不動産会社の中には、稀に所在地域と異なる起算日で対応しているケースもあります。
その場合、売主・買主間で負担金額を確認して取引がスムーズであれば、特に問題はありません。
1-2. 売却の翌年からは買主が支払う
不動産売却の翌年からは、固定資産税を支払うのは買主です。
固定資産税の納税義務者が変更になるわけですが、基本的には市町村への届け出の必要はありません。
不動産の売却に伴って土地家屋の登記簿の所有権に関する内容が変更されると、その情報が法務局から市町村に共有され、手続きされるからです。
市町村では、固定資産課税台帳に、課税対象となる土地家屋等の所在地、所有者、評価額などを登録して管理しています。
つまり、毎年1月1日の時点で固定資産課税台帳に記載されている土地家屋の所有者に、固定資産税の納税義務が生じるというわけです。
登記簿上の所有権の移転が行われてから固定資産課税台帳へ反映されるまでは、おおむね1ヶ月程度かかります。
ただし、法務局において所有権移転の申請が12月末までになされていれば、市町村では翌年1月1日の所有者は新所有者、つまり買主と判断されるのです。
翌年の固定資産税の納税通知書は、おおむね5月前後に買主に送付されます。
イレギュラーなケースとして、敷地内に未登記の建物が存在し、かつ固定資産税の対象になっている場合は、所有権が変更になったという手続きを行わなければなりません。
未登記物件は、法務局でも認識していないため、市町村の窓口で直接変更手続きを行う必要があります。
未登記物件がある場合は、売買契約書にもその旨記載されているので、確認してください。
2.家を売却した場合の固定資産税の計算方法

家を売却した場合、物件の引渡し時に所有権移転後の固定資産税相当額、つまり本来買主が負担すべき金額が、清算金として買主から売主に支払われます。
その際の手順は以下の通りです。
- 固定資産税を確認する
- 起算日と引渡しを基準にして清算金の金額を算出する
具体的な内容について、順に説明します。
2-1.固定資産税を確認する
固定資産税の金額は、市町村で算出された固定資産税の数値で確認できます。
確認方法は以下の2通りです。
- 納税通知書で確認
- 公課証明書で確認
2-1-1. 納税通知書で確認する場合
通常、毎年5月頃に送付される市町村からの納税通知書には、その年度の固定資産税の金額が記載されています。
納税通知書は、一括もしくは分割して支払う形式ですが、年度の途中で不動産を売却した場合でも、売主に1年分の固定資産税を支払う義務があります。
2-1-2.公課証明書で確認
市町村の固定資産税を扱う窓口で公課証明書を取得できます。
公課証明書に記載されているのは、以下の内容です。
- 固定資産の評価額
- 課税標準額
- 税相当額
税相当額は1円単位の数値が記載されており、納税通知書の金額より細かい数値が記載されています。
そのため、公課証明書に記載される金額のほうがより正確ではありますが、実際に納税する金額は端数処理(1,000円未満切捨て)された納税通知書の金額です。
2-2.起算日と引渡しを基準にして清算金の金額を算出する
固定資産税の金額を確認したら、引渡し日をもとに日割り清算の金額を算出します。
実際には、物件の引渡し前に不動産会社が金額を算出してくれますが、算出根拠をもとにチェックしておくと安心です。
不動産会社から事前に固定資産税の日割り計算の書面をもらい、内容を確認しておきましょう。
一般的には、不動産会社が「固定資産税計算書」などの名称で、清算内容の計算根拠を記載した書面を用意します。
物件の決済時(物件代金等の授受)の際にも書面を確認してください。
ご紹介した起算日ルールをもとに、具体的な事例で計算すると、以下のようになります。
※固定資産税を15万円、引渡日を7月1日とした場合
売主負担期間:1月1日~6月30日(181日)
売主負担金額:15万円×181日/365日=74,384円買主負担期間:7月1日~12月31日(184日)
買主負担金額:15万円×184日/365日=75,616円
売主負担期間:4月1日~6月30日(91日)
売主負担金額:15万円×91日/365日=37,397円買主負担期間:7月1日~3月31日(274日)
買主負担金額:15万円×274日/365日=11,2603円
実際の金額を比べると、地域と引渡日によって双方の負担金額に差がでます。
そのため、ケースによっては、売主が不利に感じるケースもあるかもしれません。
スムーズな取引のためにも、起算日の交渉をするよりも、そもそもの物件の売却価格を高めに設定しておくほうが現実的と言えるでしょう。
3.固定資産税を精算する際の注意点

固定資産税の清算については法的な根拠があるわけではなく、あくまで売主・買主間における任意の取引です。
ただし、いくつか注意事項がありますので、順に見ていきましょう。
3-1.固定資産税の清算は法律で決められていない
固定資産税の清算については、特に法的な根拠はありません。
基本的な不動産の取引に関しては、「宅建業法」という法律で定められていますが、固定資産税の清算に関しての定めはないのです。
しかし、不動産取引においては、売主・買主双方にとって公平性ある取引を行うことが重要なので、商慣習として固定資産税に関しては日割り清算を行うという手続きが行われています。
売主の負担が軽減されますので、メリットがあると言えるでしょう。
また、固定資産税の清算は売主と買主間で定めた任意の取引です。
そのため、トラブルを避けるためにも売買契約書に明記しておかなければなりません。
不動産の売却時には、売買契約書に固定資産税の清算に関する記載があるかしっかりと確認してください。
その上で、物件の引渡時に、買主から物件の代金と合わせて固定資産税の清算金を受け取るという流れです。
ちなみに、不動産の取引が年初のタイミングの場合、その年度の固定資産税額が確定していないケースがあります。
その場合は、売買契約書に「前年度の固定資産税額をもとに清算を行う」旨記載するのが一般的です。
3-2. 地域によって起算日が異なる
日割り計算を行う際の起算日については、前述のように地域によって起算日が異なります。
実際に、起算日と物件の引渡日によって、売主・買主間の負担額の割合が異なるため、注意が必要です。
ただし、負担額が異なるからといって、起算日を変更することはありません。
調整することでかえって買主との間で揉めるリスクがあるからです。
また、買主に対する固定資産税の清算に関する説明は、仲介する不動産会社が行います。
3-3.清算金に消費税が加算されるケースもある
清算金は消費税の対象になるのでしょうか。
この点については、以下2つのケースに分かれます。
売主が個人の場合、そもそも消費税の対象にはなりません。
家の売却の場合、売主が個人であることが多く、その場合は消費税自体かからないのです。
売主が宅建業者の場合で、かつ消費税の課税事業者の場合は、清算金に消費税が加算される可能性があります。
その場合は、土地・建物の取引と同様、土地部分の清算金は消費税の対象とならず、建物部分の清算金に消費税が課せられます。
清算金も、土地建物取引の一部と解釈されるからです。
また、消費税の課税事業者かどうかについては、その会社の課税売上高の金額等によって判断されます。
なお、固定資産税の清算金は一見、税金に関する金銭のやりとりのようですが、国税庁の見解は、税務上土地および建物の売却による所得と同様の扱いとなります。
そのため、売主からすると、不動産譲渡所得の一部とみなされることがあるので、注意が必要です。
参考URL:未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合(国税庁)
4.不動産業者を探すには一括査定がおすすめ

不動産の売却の際には、一般的には、不動産会社に売却の仲介を依頼して、売却活動を進めるのが一般的です。
その場合、どの不動産会社を選べばいいのでしょうか?
特に不動産の売却が初めての場合、不動産会社の選定は悩ましい問題です。
不動産会社の選定のポイントは、いかに信頼できる不動産会社を見つけるかです。
不動産取引の専門知識はもちろん、担当者との相性や、安心して契約を進められそうかといったことも含めて選定すると良いでしょう。
自分に合ったところを見つけるためにも、複数の不動産会社の査定を受けて、内容や対応状況などを比較して検討することが大切です。
複数の不動産会社に対して不動産売却の相談、物件の査定を依頼する際には、NTTデータグループの運営する一括査定サイト「IELICO(イエリコ)」がおすすめです。

イエリコははカンタンな情報を入力するだけで、全国の優良な不動産会社2,500社のなかから、6社を選んでまとめて査定依頼ができます。
ぜひイエリコで比較して、信頼できる最適な不動産会社を見つけてください。
この記事のポイントまとめ
不動産売却時の固定資産税を支払うのは売主が原則ですが、清算という形で売主・買主双方が負担するケースがほとんどです。
- その年度の市町村の対しての支払いは、売主が支払う
- 所有権移転後に買主が負担すべき固定資産税相当額を清算するのが一般的
- 不動産の翌年からは買主が固定資産税を支払う
詳しくは「1.固定資産税は誰が支払う?」をご覧ください。
固定資産税の精算時の計算方法については、起算日に着目してください。
- 所有権の移転日の前日までを売主負担、所有権の移転日以降を買主負担として計算
- 起算日は東日本は1月1日、西日本は4月1日
詳しくは「2.家を売却した場合の固定資産税の計算方法」をご覧ください。
固定資産税の精算時には、いくつか押さえておくべき注意点があります。
- 固定資産税の清算は法律で決められていない
- 地域によって起算日が異なる
- 清算金に消費税が加算されるケースもある
詳しくは「3.固定資産税を精算する際の注意点」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点