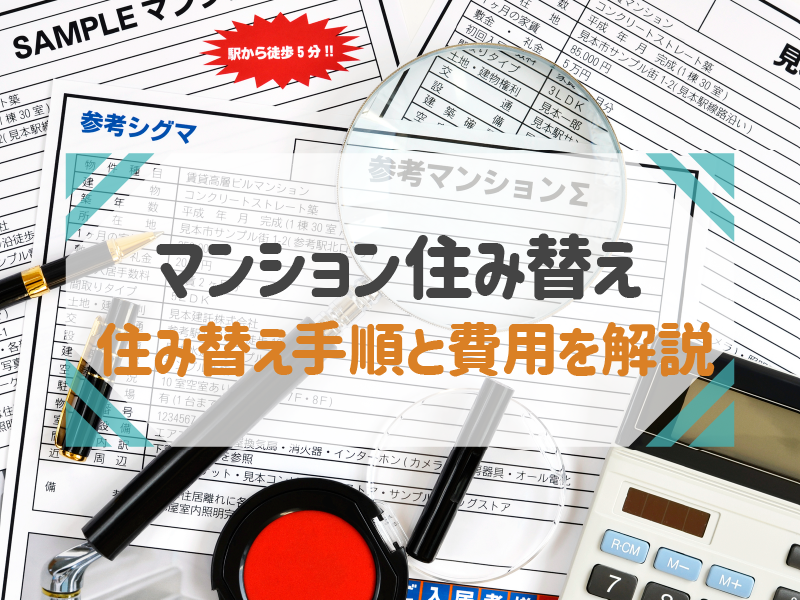住み替えを行う際は、資金計画でつまずかないためにも、事前に段取りを押さえておくことが大切です。マンションを売却して住み替えを行うときの全体的な手順を把握し、高く売るためのポイントを理解しておきましょう。
また、売却時にかかる費用や税金なども把握しておけば、お金の面で安心できます。
この記事では、マンションの住み替えを行うときのポイントを詳しく解説します。
- 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格”を見つけましょう
- 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
目次
1.マンション住み替えの手順

マンションの住み替えでは、まず「売り先行」と「買い先行」の2つのパターンがあることを押さえておく必要があります。今の住まいを売却すると同時に新居を購入できれば理想的ですが、現実的には難しいでしょう。
住み替えを行う際は自宅の売却を先にするか、新居の購入を先に進めるかで手順が異なります。いずれの場合でも、自分の物件を引き渡すときに、手付金を除いた残高が入金となります。
売り先行と買い先行の基本的な手順について解説しましょう。
- 売り先行
- 買い先行
1-1.売り先行
「売り先行」とは、今の住まいを先に売却し、後に新居を見つける方法です。売り先行のメリットは、売却代金を受け取ってから新居を購入することができますので、資金計画を立てやすいという点が挙げられます。
一方で、新居を探す時間をあまりかけられない点と、仮住まいのための費用や引っ越しを2回行わなければならないため、費用がかさむというデメリットがあります。ただし、初めて住み替えを行う方の場合は、売り先行のほうが落ち着いて取り組めるでしょう。物件の売却を早く進められれば、その分だけ新居選びに時間をかけられます。
不動産の一括査定サービスを利用してスムーズな売却を進めてみましょう。のちほど紹介する、一括査定サービスのIELICO(イエリコ)を活用すれば、希望する価格や売却時期を実現できる可能性がありますので、是非活用してみてください。
1-2.買い先行
「買い先行」とは、今の住まいを売却する前に、新居の購入を済ませる方法です。メリットとしては、住み替えのためにかかる費用を最低限度に抑えられる点が挙げられます。新居をじっくりと探すことができますので、新生活の準備を整えやすい方法です。
一方で、新居を購入してから今の住まいを売却することになるため、資金計画を綿密に立てておかなければ資金繰りで苦労するというデメリットがあります。また、急いで物件を売却しようとすれば売り時を選べず、相場よりも低い金額で売ることになり、損をしてしまう可能性もあります。
今の住まいの住宅ローンを完済していなければ、二重ローンとなり、負担が大きくなる恐れがありますので注意が必要です。
2.マンションの住み替えにベストなタイミングは?

住み替えを検討するときに、今の住まいが築浅であれば、できるだけ早めに売却するほうが良いと言えます。マンションは築年数に応じて価格の下落が激しくなるので、築浅の物件のほうが高値で売却できる可能性が高いのです。
住み替えでは今の住まいの売却と新居の購入を両方考えなければならないため、ポイントを押さえて行動する必要があります。住み替えをベストなタイミングで行えれば、今の住まいを納得のいく価格で売却できる可能性が高まるのです。どのようなタイミングで物件を売却するのが良いかを整理しますと、以下のようなタイミングとなるでしょう。
- 住み始めから5年のタイミング
- マンションの大規模修繕後のタイミング
- 住宅ローンの残高が0か売却益が出るタイミング
それぞれのタイミングについて、更に詳しく解説します。住み替え時期を見計らっている方は是非参考にしてください。
2-1.住み始めから5年のタイミング
今のマンションに住み始めてから5年以上かつ築年数が10年以内であれば売却時に損失が発生しづらいと言えます。築浅の物件のほうが買い主は見つかりやすく、高値で売却できる可能性があるからです。
そして、物件の所有年数は売却益にかかる税率にも影響が出ます。不動産を売却したときに利益(譲渡所得)が生じた場合には、譲渡所得税という税金を納める必要があります。
譲渡所得税とは、譲渡所得にかかる所得税・復興特別所得税・住民税の総称です。売却代金(譲渡価額)から、購入時にかかった費用(取得費)と売却時にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた譲渡所得に対して課税されます。
譲渡所得に所定の税率をかけ合わせることで税額は算出できますが、このときに物件の所有期間が影響してくるのです。所有期間による税率の違いについてまとめますと、以下のとおりとなります。
| 譲渡所得の区分 | 税率 |
|---|---|
| 短期譲渡所得(所有期間5年以下) | 39.63%(所得税30.63%※+住民税9%) |
| 長期譲渡所得(所有期間5年超) | 20.315%(所得税15.315%※+住民税5%) |
※2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までは、復興特別所得税として所得税額×2.1%が課されます。
上記のように、所有期間が5年を超えているかどうかで税率が2倍近くも異なる点に注目しておきましょう。マンションを売却するタイミングを考える上で、1つの目安となります。
2-2.マンションの大規模修繕後のタイミング
マンションは毎月の管理費の他に、建物の改修工事などに備えて修繕積立金を徴収されるのが一般的です。修繕積立金は均等積立方式と段階増額積立方式の2種類がありますので、どちらの方式で修繕積立金が集められているのかを確認しておきましょう。
均等積立方式の場合は、毎月一定の金額が徴収されますので、金額にほぼ変わりがありません。そのため、マンションの購入を希望する方にとって、費用面での計算が行いやすいと言えるでしょう。
一方、段階増額積立方式は、約5年おきの頻度で修繕積立金が増えていきます。大規模修繕工事を前にして積立金が不足していれば、大幅に増額される可能性があります。
マンションの購入を検討する方からすれば、将来的な負担は少ないほうがメリットに感じやすいものです。売却を検討するタイミングの1つとして、大規模修繕工事が終わった段階が挙げられます。
大がかりな修繕工事が済んでいれば、しばらくの間は修繕積立金が高くなる可能性が低くなりますので、購入希望者にとってプラスとなるでしょう。
2-3.住宅ローンの残債が0か売却益が出るタイミング
住宅ローンを完済している状態であれば、どのタイミングで売却をしても特に問題がありません。また、売却時に利益が出るのであれば、売却代金でローン残債を一括返済する目途が立ちます。
そのため、住宅ローンを完済したときか、売却代金でローン残債を相殺できるときが住み替えのタイミングとして適していると言えるでしょう。どの程度のローン残債があるかは、金融機関から送られてくる明細書などを確認すれば分かりますので、住宅ローンの返済に問題がないかを確認しておくと安心です。
老後の住み替えを考えている方は、住み慣れた家を離れる不安もあることでしょう。以下の記事では老後の住み替えの不安を解消するポイントをご紹介しています。ぜひ参考にしてください。
3.マンションの住み替えを成功させる2つのコツ

マンションの住み替えをスムーズに行うためには、コツを押さえておくことが重要です。ここでは、準備のタイミングと不動産選びに関する2つのコツについて紹介します。
- 6か月前の売却準備
- 信頼できる担当者がいる仲介会社に頼む
3-1.コツ1|6か月前の売却準備
マンションは売却するまでに4~6か月程度がかかりますので、スムーズに売却活動を進めるには、逆算して6か月前から売却準備を整えておくことが大切です。急いで売却しようとすれば、相場よりも低い金額で売らなければならない面もありますので注意しておきましょう。
また、急な転勤や子どもの進学などの理由で住み替えを行う場合は、売却希望時期をしっかりと決めておく必要があります。場合によっては新居の購入を先に進めなければならないケースもありますので、早めに相談できる不動産会社を見つけておくことが重要です。
3-2.コツ2|信頼できる担当者がいる仲介会社に頼む
売却される物件の情報は、どの不動産会社であってもREINS(レインズ)と呼ばれる共通システムによって閲覧できます。そのため、どの会社に売却を依頼しても一見価格に影響がないように思えるでしょう。
しかし、不動産会社によって得意とするジャンルに違いがあるため、おのずと価格差が生じるものです。複数の会社を比較した上で、相場に沿った価格を提示してくれる会社を選んでみましょう。
また、物件の売却相談だけでなく、住み替え後の資金計画なども一緒に立ててくれる担当者を見つけておくと安心です。細かな質問にもきちんと答えてくれて、誠実に対応してくれる担当者がいる会社に売却活動を依頼しましょう。
不動産の一括査定サービスであるIELICO(イエリコ)を利用すれば、一度に複数の不動産会社に査定依頼が行えます。
イエリコは、2001年(平成13年)に国内で初めて不動産の一括査定サービスを開始した、「不動産売却HOME4U(ホームフォーユー)」のサービスの1つです。20年以上にわたってサービスを提供してきた実績があり、累計で45万件以上の査定依頼の実績があります。
独自の審査基準で厳選した2,500社の優良企業を紹介しており、査定依頼を行うときには最大6社までを選択できます。査定依頼に必要な情報の入力は最短1分で完了でき、初めて利用する方でも簡単に操作することが可能です。
また、イエリコは情報サービス事業で業界最大手のNTTデータグループが運営を行っています。長年にわたって培ってきたセキュリティ技術によって、個人情報の取り扱いなど安心して利用していただける環境を整えています。
そして、自分に合った不動産会社を見つけるために、16,000件以上の経験者の口コミが役に立つことでしょう。不動産会社の強みや特徴を把握できますので、気になる不動産会社に査定を依頼することが可能です。
住み替えを検討するときには、イエリコを活用して信頼できる不動産会社を見つけてみましょう。
4.マンション住み替え売却時にかかる費用

住み替えをスムーズに進めるには、どれくらいの費用がかかるのかを事前に把握しておくと良いでしょう。売却時にかかる費用についてまとめますと、以下のとおりです。
| 費用の項目 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬 | 取引額に応じて計算する |
| 登録免許税(抵当権の抹消登記費用) | 抵当権の抹消登記にかかる税金 | 不動産1個あたり1,000円 |
| 司法書士に支払う報酬 | 登記手続きを代行してもらう依頼料 | 1~2万円程度 |
| 印紙税 | 売買契約時の契約書にかかる税金 | 取引額に応じて決められている |
| ローン完済手数料 | 住宅ローンを繰り上げ返済するときにかかる事務手数料 | 金融機関によって異なるが3~4万円程度 |
| 譲渡所得税 | 売却によって利益が出た場合にかかる税金 | 譲渡所得×所有期間に応じた税率 |
1つひとつの費用項目について、更に詳しく解説します。
4-1.仲介手数料(取引額×3%+6万円+消費税)
仲介手数料とは、物件の買い主が見つかり売買契約が成立した時点で、不動産会社に支払う成功報酬を指します。宅地建物取引業法(以下、宅建業法)によって上限額が決められており、各社はその上限額の範囲内で仲介手数料を設定します。
取引額に応じて仲介手数料の金額は異なり、まとめますと次のようになります。
| 取引額 | 仲介手数料 |
|---|---|
| 200万円以下の金額 | (取引額の5%以内)+消費税 |
| 200万円以上400万円以下の金額 | (取引額の4%以内)+消費税 |
| 400万円を超える金額 | (取引額の3%以内)+消費税 |
上記のルールに沿って計算する方法以外にも、速算式として「(取引額×3%)+6万円+消費税」に当てはめてかんたんに計算することも可能です。正確な金額は物件の売却価格が決まらなければ算出できませんが、目安を知りたい場合は不動産会社の担当者に確認しておきましょう。
仲介手数料はマンションの売却時にかかる費用の中でも大きな割合を占めますので、注意深く考慮する必要があります。
4-2.抵当権の抹消登記費用(不動産1個あたり1,000円)
マンションを売却する際は、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。抵当権の抹消登記費用として支払うことになる登録免許税は、不動産1個あたり1,000円と決められています。
土地と建物の場合であれば、それぞれ費用がかかりますので合計で2,000円がかかります。マイホームの売却程度ならば、自分で登記の手続きを進めることが可能です。
4-3.司法書士に支払う報酬(1~2万円程度)
相続などによってマンションを取得する場合、名義人が複数いる場合があります。
売却後にトラブルにならないためにも、権利関係が複雑なときは司法書士に依頼をして、抵当権の抹消登記手続きを行うほうが良いでしょう。
4-4.印紙税(200円~6万円)
印紙税とは、売買契約書を作成する際にかかる費用のことです。契約金額によって税額は違っており、2022年(令和4年)3月31日までは軽減税率が適用されていますので、下記に挙げた表を参考にして税額を把握しておきましょう。
| 契約金額 | 通常の税額 | 軽減後税額 |
|---|---|---|
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
4-5.ローン完済手数料(3~4万円程度)
住宅ローンの一括返済を行う場合、借り入れを行っている金融機関に対して、繰り上げ返済に伴う手数料を支払う必要があります。
具体的な金額については金融機関によって異なりますが、3~4万円程度を見込んでおくと良いでしょう。
また、金融機関と交わした契約内容次第では違約金を求められる場合もありますので、早めに確認を行っておくことが大切です。
4-6.譲渡所得税(税率20.315%~39.63%)
前述のように、マンションを売ったときに売却益が出たら、譲渡所得税を納める必要があります。
物件の所有期間によって税率は異なりますが、売却した翌年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えている必要がありますので注意しておきましょう。
また、売却損が出てしまっても確定申告を行うことで、税負担が軽減される場合があります。
5.マンション住み替え購入時にかかる費用

住み替えを行った際の新居の購入にかかる費用についても把握しておきましょう。主な費用についてまとめますと、以下のとおりです。
| 費用の項目 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬 | 取引額に応じて計算する |
| 登記費用(所有権移転登記) | 所有権を変更するための登記費用 | 20万円程度 |
| 不動産取得税 | 不動産の取得時に一度だけ発生する税金 | 固定資産税評価額×4% |
| 火災保険料 | 保険会社に支払う保険料 | 10万円程度 |
| 抵当権の登記費用 | 住宅ローンを組む場合は、抵当権を設定する必要がある | 数万円~数十万円程度 |
| 引っ越し・リフォーム代 | 住み替えのための引っ越し費用やリフォームにかかる費用 | 必要に応じて金額は異なる |
それぞれの費用項目について、詳しく見ていきましょう。
5-1.仲介手数料(取引額×3%+6万円+消費税)
新築マンションを購入するときは仲介手数料がかかりませんが、中古マンションの場合は発生しますので注意しておきましょう。
仲介手数料の計算方法については、売却時と同様ですがあらかじめ購入価格が分かっているときは、不動産会社に問い合わせて正確な金額を算出してもらっておくと安心です。
5-2.登記費用(20万円程度)
マンションを購入するときは、残金を決済して物件の引き渡しを受ける際に、所有権を移転させる必要があります。そのときに支払う登録免許税と司法書士に支払う報酬を合わせますと、一般的には20万円程度の費用を見ておきましょう。
ただし、登録免許税の額は固定資産税評価額や軽減税率が適用されるかどうかは、物件によって大きく異なります。実際の金額は購入手続きに入ったら確認しましょう。
所有権は第三者に対して、物件の所有を明確にさせるものであるため、手続きに問題が起こらないように進める必要があります。
5-3.不動産取得税(固定資産税評価額×4%)
不動産取得税とは、新たに物件を取得したときに課される税金です。税額は「固定資産税評価額×4%」で計算されますが、軽減税率が適用される点を押さえておきましょう。2024年(令和6年)3月31日までに住宅を取得した場合、土地や建物に課される税率は3%に軽減されます。
また、課税標準となる金額が一定額を下回る場合には、不動産取得税は課税されません。具体的には、土地の場合は10万円以下、建物は新築で23万円以下、中古で12万円以下までは課税されないので税負担が軽くなります。
5-4.火災保険料(10万円程度)
住宅ローンを組んで物件を購入する場合、火災保険に加入することが求められる場合が多いと言えます。保険料は保険会社によって異なりますが、10万円程度を見込んでおきましょう。
また、建物の構造によっても保険料は違っています。一般的に、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造は保険料が低くなり、木造の場合は保険料が高くなる傾向にあります。
5-5.抵当権の登記費用(数万円~数十万円程度)
住宅ローンを組んで物件を購入するときには、金融機関から抵当権を設定するように求められます。
司法書士に依頼して、抵当権の設定を行うことになりますのでその費用として数万円から数十万円程度が必要です。
金額に幅があるのは、物件価格によって費用が異なるからです。あらかじめ必要な金額を提示してもらい、支払いをスムーズに行えるように準備しておきましょう。
5-6.引っ越し・リフォーム代(各社査定プランによる)
住み替えを行うときは、引っ越し費用が必要になります。
荷物の量や移動距離、引っ越しを依頼するタイミングなどによって費用は異なりますので、複数の会社に査定プランを依頼して早めに比較しておきましょう。
また、これまで住んでいた物件を売りやすくするために、リフォームを行う場合にはそのための費用も必要になります。どの程度の規模でリフォームを行うかによって費用は大きく変わってきますので、不動産会社の担当者とも相談をしながら決めてみましょう。
6.マンション住み替えで発生する税金と注意点

マンションの住み替えを行うときは、税金面にも注意を向けておきましょう。売却益が出た場合、売却損が出た場合のそれぞれで税金の特例制度も含めて紹介します。
- 売却益が出た場合
- 売却損が出た場合
6-1.売却益が出た場合
住み替えのためにマンションを売ったときに、売却益が出た場合には譲渡所得税を納める必要があります。しかし、住宅に関するさまざまな税金の特例制度が設けられていますので、うまく活用することで税負担を軽減できるでしょう。
例えば、マイホームを売却した際によく利用される特例制度として「3,000万円の特別控除」があります。この制度は譲渡所得から最大3,000万円が控除される仕組みであり、大幅な税負担の軽減につながるはずです。
特例制度が適用されるには、以下の要件を満たしておく必要があります。
- 居住している家屋やその家屋とともに譲渡する敷地の売却の場合
- 売った年の前年及び前々年に売却時の各種特例を利用していないこと
- 転居している場合は住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すること
- 売り主と買い主が親子や夫婦などの特別な関係でないこと など
また、税金の特例制度は自動的に適用されるものではなく、確定申告を行うことで認められるものです。マンションを売却した翌年2月中旬から3月中旬にかけて、確定申告を行って税金の特例制度を活用してみましょう。
6-2.売却損が出た場合
マンションを売却して損失のほうが大きければ、納めるべき税金がないので基本的に確定申告を行う必要はありません。
しかし、売却損が出た場合の特例制度も設けられており、具体的には「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が活用できます。
この特例制度を利用すれば、給与所得など他の所得と合算して税額計算が行えますので、結果的に税負担を軽減できる可能性があります。特例制度を活用するための要件は、以下のとおりです。
- 自分が住んでいたマイホームを売却した場合
- 物件を売却した年の1月1日時点において、所有期間5年を超えている
- 家屋の床面積が50平米以上のものを、売却した前年の1月1日から翌年12月31日までの間に取得すること
- 新居を取得した年の翌年12月31日までに、居住または居住する見込みであること
- 新居の取得において返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること など
住宅にまつわる税金の特例制度はたくさんありますので、税理士に相談をしたり、国税庁のホームページなどで最新情報を確認したりしてみましょう。
7.マンション住み替えで活用できる住宅ローンの基礎知識

住み替えを行うときには、金融機関から住宅ローンを借り入れるのが一般的です。
そのため、住宅ローンの基本的な仕組みを理解するとともに、住み替えローンについても押さえておきましょう。
- 住宅ローン
- 住み替えローン
- ローン審査にかかる一般的な期間
7-1.住宅ローン
住宅ローンは、個人がマイホームを取得するときの費用を金融機関から融資してもらう仕組みです。返済期間が35年程度と長めに設定できるのが特徴であり、年収や年齢などにもよりますが最大で1億円程度までの融資が受けられます。
あくまでマイホームとして居住する場合に借りられるものであり、投資用物件などは対象としていません。住宅ローンを組めるかどうかは審査の結果次第ですので、新居にかけられる購入費用を決める際にはとても重要な要素となります。
7-2.住み替えローン
住み替えローンとは、現在借りている住宅ローンに上乗せする形で借り換えし、新居の購入費用もまとめてローンとして組むものです。通常の住宅ローンと比べて、住み替えローンのサービスを提供している金融機関は多くはありませんが、うまく活用することで住み替えをスムーズに進められるでしょう。
ただし、住み替えローンを利用する場合は、住宅ローンの総額が膨らんでしまうので事前にきちんと資金計画を立てておくことが重要です。今住んでいるマンションがどの程度で売却できるかでも、借入額に違いが出てきますので綿密にシミュレーションを行っておきましょう。
住み替えローンについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
7-3.ローン審査にかかる一般的な期間
住宅ローンや住み替えローンの審査は、事前審査(仮審査)と本審査の2段階で行われる仕組みです。
購入したい物件が決まったら、物件の概要を示す書類や現在の住宅ローン残高を示す書類、通帳などを用意して金融機関の窓口で事前審査を申し込みましょう。その際、通帳は記帳を行い、ローン残高は最新の情報が載っているものを用意するようにしましょう。
事前審査の結果は5営業日程度で分かりますので、審査を通過したら売り主と売買契約を締結します。そして、本審査を受けることになりますが、こちらは結果が出るまで10~15営業日程度がかかります。
住宅ローンの本審査に通過し、融資された金額を売り主に支払うことで、物件の引き渡しが行われるのが一般的な流れです。
ローンが残っている場合の売却について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
まとめ
マンションの住み替えをスムーズに進めるには、住み替えのための手順を踏まえた上で、必要な費用や税金を把握しておくことが大切です。資金計画をうまく立てることで、落ち着いた気持ちで取り組んでいけるでしょう。
希望に添った形で住み替えを行うために、何でも相談できる不動産会社を見つけておくことも重要です。不動産の一括査定サービスを通じて、自分に合った会社を選んでみましょう。
マンションを売却するまでには4~6か月程度の期間を必要とするため、不動産会社の担当者としっかりコミュニケーションを取ることが欠かせません。細かな質問にも丁寧に対応してくれる会社を選んでみてください。
この記事のポイントまとめ
- 売り先行
- 買い先行
詳しくは「1.マンション住み替えの手順」をご覧ください。
- 住み始めから5年のタイミング
- マンションの大規模修繕後のタイミング
- 住宅ローンの残高が0か売却益が出るタイミング
詳しくは「2.マンションの住み替えにベストなタイミングは?」をご覧ください。
- 6か月前の売却準備
- 信頼できる担当者がいる仲介会社に頼む
詳しくは「3.マンションの住み替えを成功させる2つのコツ」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2025年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- 【2025年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 2025年問題まであと2年!不動産は本当に大暴落するの?今後の不動産売却のタイミングは?
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点