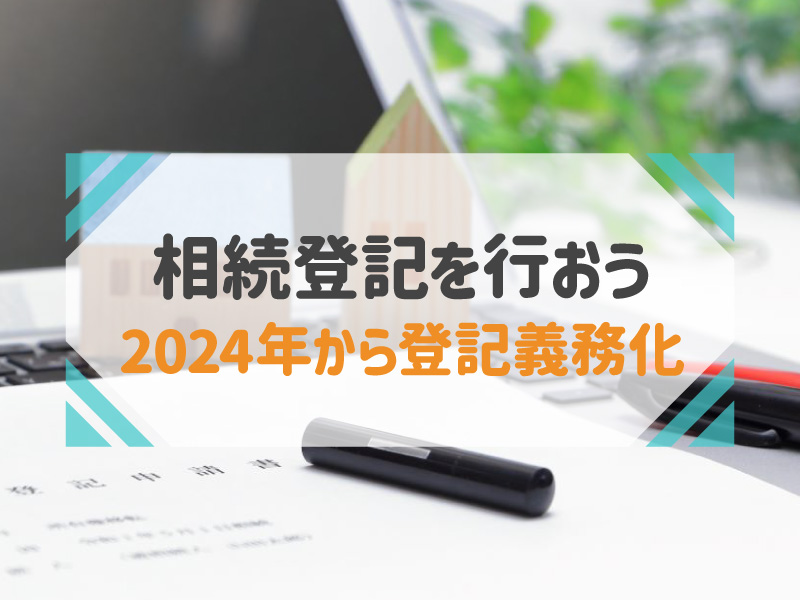不動産を相続した際、相続登記が必要になります。
相続登記という手続きには、現時点では法的な期限がないため、重要と感じていない人や、後になって存在を知る方も少ないかと思います。
この記事では、相続登記のわかりやすい解説や、実際の相続登記の方法まで解説しています。
また、今後法律による相続登記は義務かされますので、相続登記の期限や相続登記をしないリスクについても触れていきます。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「IELICO(イエリコ)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
目次
1.相続登記とは相続不動産の名義変更手続きのこと

相続登記とは、土地や家屋、マンションなどを相続した際に必要になる名義変更手続きです。
不動産は誰が所有者なのか分かりにくいため、登記によって所有者を明確にしています。
相続登記を行わないと、登記上は被相続人名義のままとなります。
本来の所有者が登記上の所有者と一致していない状態では、売却が自由にできなかったり、権利関係のトラブルに発展したりするリスクが起こりえます。
1-1.いつまでに行う必要がある?期限はある?
相続登記は、いつまでに行わなければならないという明確な期限はなく、罰則もありません。
期限こそありませんが、いつまでも先延ばしにしても良いというものでもありません。
相続登記をしないことで、次章で紹介するようなリスクが起こりえるためです。
不動産の相続人が決まってから、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)までを目安に手続きをしておくと安心です。
1-2.相続登記は義務化されている?
相続登記が義務化されていない日本では、所有者が誰なのか分からない土地が数多く存在しています。
そのような土地は、利用または適切な管理を行うことができず、公共事業や災害復興の妨げとなっているので問題視されていました。
その問題を考慮し、2024年4月1日から、相続登記の義務化が施行されます。
法改正後は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料の対象となります。(正当な事由がある場合を除く)
これから不動産を相続する方は『 家の相続から名義変更までの手順!かかる税金やトラブルを回避するポイント 』もご覧ください。
2.相続登記をしない4つのリスク

相続登記を放置することには、以下の4つのリスクを伴います。
- 2次3次相続による相続人の複雑化
- 時間がたつと書類の入手が難しくなる
- 相続登記が完了するまで不動産を売却できない
- 10万円以下の過料が科せられる(法改正後)
それぞれのリスクを詳しく見ていきましょう。
2-1.2次3次相続による相続人の複雑化
2次3次相続が発生した場合に、相続人が次第に複雑化していき、遺産分割協議が困難になる可能性があります。
例えば、親から相続した3子のうち、相続登記をしない状態で1人が他界した場合、そこでも相続が発生します。
最初の相続の時点で、不動産の所有者を一人に決定し相続登記を行っていれば、上記のようなトラブルは回避できます。
2-2.時間がたつと書類の入手が難しくなる
相続登記をしないままの不動産は、相続人全員で共有している不動産みなされます。
本来はAさんが所有者になるべき相続にも関わらず、BさんCさんとの共有不動産となってしまうのです。
相続登記をしない状態で、相続人の一人が死亡すると、さらに相続が発生し、相続人が拡大していきます。
暫定的な共有所有者が広まれば広まるほど、必要書類の調達が難しくなり、思うように相続登記を進められない事態に陥る可能性があります。
2-3.相続登記が完了するまで不動産を売却できない
不動産は名義人本人しか売却できないため、相続登記を完了していない不動産は売却できません。
いざ売ろうと思ったときに売却ができないのです。
急に現金が必要になった時や、不動産の需要が高騰したタイミングなど、いつ何時でも売却ができるように相続登記を済ませておきましょう。
また、不動産売却にはその他の準備も必要なため、売却を検討している方は事前に把握しておきましょう。
詳しくは、不動産売却の全体的な流れをご覧ください。
2-4.10万円以下の過料が科せられる(法改正後)
前章でも触れましたが、2024年4月1日の改正法施工以降に相続する場合、相続後不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記をしなければ10万以下の過料の対象となります。
法改正以前に相続した不動産の場合も、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければ、同様の過料対象となります。
3.相続登記を行う方法

相続登記は、必要書類の用意や法務局への申請が必要です。
スムーズに相続登記を行えるよう、以下で相続登記の手続き方法を確認しておきましょう。
また、「司法書士に代行を依頼する」か「自分で法務局に申請を行う」のかで手続きの流れが異なりますので、それぞれ解説いたします。
3-1.司法書士に代行を依頼する
司法書士に相続登記の代行を依頼した場合には、必要書類の収集から法務局への申請まで全てを行ってくれるため、相続登記にかかる手間を大幅に軽減できます。
また、登記の専門家である司法書士は相続登記について様々な相談に応じてくれるため、不安や疑問を解消できる、相続登記の不備によるトラブルを未然に防げるでしょう。
ただし、司法書士に代行を依頼する際は費用がかかります。どのくらいの費用がかかるのか把握してから依頼しましょう。
司法書士費用に関して詳しくは、次章をご覧ください。
3-2.自分で法務局に申請を行う
相続登記は自分で行うこともできます。しかし、自分で行う場合は不備が生じやすいため、事前にどのような手順で相続登記を進めるのかを把握しておくことが大切です。
自分で相続登記を行う際の主な手順は以下の通りです。
- 不動産の確認・調査
- 戸籍に関係する書類を収集する
- 相続の対象を決める
- 必要な書類を作成する
- 法務局に申請を行う
3-2-1.不動産の確認・調査
まずは亡くなった方がどのような不動産を所有していたのかを確認・調査を行います。自宅に登記事項証明書(登記簿謄本)がある場合にはそれで確認できます。もし、そのような書類がない場合には管轄の法務局で調べて入手することが可能です。
不動産が共有名義になっている場合、相続人が相続できるのは亡くなった方の持分だけとなります。
不動産の種類、面積、名義などをしっかり確認・調査しましょう。
3-2-2.戸籍に関係する書類を収集する
相続する不動産が明確になった後は、誰が相続人なのか把握するために、戸籍に関係する書類を収集します。
なお、遺言書が作成されているケースでは、遺言書の内容に従って不動産の相続を行います。
相続人が誰なのかは、以下の書類で確認できます。
- 戸籍謄本
- 改製原戸籍
- 除籍謄本
- 附票
上記の書類は市区町村役場で発行・入手できます。
3-2-3.相続の対象を決める
遺言書が作成されていない場合には、相続人同士で話し合って誰が不動産を相続するのか決める(遺産分割協議)必要があります。決めた相続内容に相続人全員が合意した場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印を行います。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなくてはなりません。直接会って話をする必要はありませんが、相続人全員で話し合わないと遺産分割協議が無効となるので注意しましょう。
3-2-4.必要な書類を作成する
不動産の相続人が決まった後は、相続登記に必要な登記申請書の作成に移ります。登記申請書は、法務局のホームページに用意されているので、ダウンロードして使用します。記載例も掲載されているので、記載例を確認しながら作成を進めていけば問題ありません。
相続登記には、他にも以下のような書類が必要です。
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 遺言または遺産分割協議書
- 被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人の戸籍謄本や住民票
- 法定相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
書類の手配に時間がかかる可能性があるため、早めに用意しておきましょう。
3-2-5.相続の対象を決める
相続登記に必要な書類を用意した後は、不動産の住所地を管轄している法務局で申請を行います。
不動産登記の窓口に登記申請書と必要書類一式を提出しましょう。
登記には登録免許税がかかるため、収入印紙等を申請書に貼付して提出しましょう。
法務局では、受け取った書類の審査の後に登記を行いますが、登記完了までは1週間~10日程度かかります。
登記完了後は、登記識別情報の通知や登記完了証を受け取って相続登記が完了します。
相続登記以外の相続に関する手続きを知りたい方は『 不動産相続時の手続きや分割方法を徹底解説 』をご覧ください
4.相続登記にかかる費用の目安

相続登記を行う際には、必要書類を用意するのに費用がかかるほか、登録免許税や司法書士報酬などもかかります。書類の取得費用は数千円で済むことがほとんどですが、不動産の価格によっては多額の登録免許税、司法書士に相続登記を依頼する場合はさらに10万円程度の費用がかかるので注意してください。
相続登記にかかる費用の目安を詳しく見ていきましょう。
4-1.書類の取得費用
相続登記に必要な書類の取得費用は以下の通りです。
| 書類名 | 費用 |
|---|---|
| 相続人分の戸籍謄本 | 1通450円 |
| 被相続人の戸籍謄本 | 1通750円 |
| 被相続人の住民票の除票 | 1通300円程度 |
| 不動産の相続人の住民票 | 1通300円程度 |
| 固定資産評価証明書 | 1通300円程度 |
| 相続人分の住民票 | 1通300円程度 |
| 相続人分の印鑑証明書 | 1通300円程度 |
| 相続する不動産の登記簿謄本 | 1通500円程度 |
自治体によって書類取得にかかる費用が異なる場合があるので注意してください。
4-2.登録免許税
法務局で行う相続登記にかかる登録免許税は、以下の計算式(税率)を用いて算出します。
例えば、固定資産税評価額5,000万円の不動産を相続する場合、5,000万円×0.4%の20万円が登録免許税として徴収されます。なお、相続で不動産を取得した方が相続登記を行う前に亡くなった場合は、登録免許税の免税措置を受けられます。
詳しくは法務局の「相続登記の登録免許税の免税措置について」をご覧ください。
4-3.司法書士への報酬
相続登記を司法書士に依頼する際は、上記の費用に加えて司法書士に報酬を支払わなくてはなりません。
| 依頼内容 | 目安費用 |
|---|---|
| 書類の取得費用 | 3,000円程度 |
| 登録免許税 | 10万円程度 |
| 司法書士への報酬 | 6~10万円程度 |
司法書士に支払う報酬は、依頼する司法書士によって異なります。総額は条件によって異なりますが、20万円程度の費用がかかるということを理解しておきましょう。
5.自分でやる・専門家に依頼?おすすめの方法を紹介

相続登記を自分で行うべきなのか、司法書士に依頼すべきなのか悩んでいる方も多いと思います。最後に相続登記を自分で行うのがおすすめなケースと専門家に依頼するのがおすすめなケースについて詳しく説明していきます。
5-1.自分で行うのがおすすめなケース
相続登記を自分で行うことには相続登記にかかる費用を抑えられるというメリットがある一方、時間と手間がかかるというデメリットに注意が必要です。
メリット・デメリットから考慮したうえで、以下のようなケースであれば、自分で行うのがおすすめです。
- 平日に相続登記の作業に取り掛かれる
- 自分で調べて作業に取り組める
- 相続税が発生しない
- 相続登記にかかる費用を抑えたい
5-2.専門家に依頼するのがおすすめなケース
相続登記を司法書士に依頼することには相続登記にかかる手間を省けるというメリットがある一方、相続登記にかかる費用が大きくなるというデメリットに注意が必要です。
メリット・デメリットから相続登記を専門家に依頼するのがおすすめなケースとして、以下のようなケースが挙げられます。
- 平日に相続登記の作業に取り掛かれない
- 法律に詳しくない
- 自分で調べて行動することが苦手
- 相続税の申告が必要
- 相続登記にかかる手間を省きたい
この記事のポイント
現時点で相続登記は義務化されておらず、手続きに期限や罰則はありません。
ただし2024年4月1日以降、相続登記が義務化されますので注意ください。
詳しくは「1.相続登記とは相続不動産の名義変更手続きのこと」をご覧ください。
相続登記をしない4つのリスクは以下の通りです。
- 2次3次相続による相続人の複雑化
- 時間がたつと書類の入手が難しくなる
- 相続登記が完了するまで不動産を売却できない
- 10万円以下の過料が科せられる(法改正後)
詳しくは「2.相続登記をしない4つのリスク」をご覧ください。
詳しくは「3.相続登記を行う方法」をご覧ください。
相続登記にかかる費用の目安は以下の通りです。
- 書類の取得費用:3,000円程度
- 登録免許税:10万円程度
- 司法書士への報酬:6~10万円程度
詳しくは「4.相続登記にかかる費用の目安」をご覧ください。
相続登記は、調べながら自分で行うことができます。専門用語が多く、理解が難しいかと思いますが、その点をクリアできるなら自分で行う方がいいでしょう。
自分で行うことを手間と感じるのであれば、費用こそかかりますが司法書士に依頼しましょう。
- 書類の取得費用:3,000円程度
- 登録免許税:10万円程度
- 司法書士への報酬:6~10万円程度
詳しくは「5. 自分でやる・専門家に依頼?おすすめの方法を紹介」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点