家の売却時にかかる手数料の金額や支払うタイミングがわからず、不安な思いをお持ちではありませんか?
家を売ると、仲介手数料や税金などいくつもの費用が請求されます。
そこでこの記事では、家の売却時の費用や手数料の相場、支払うタイミングなどを詳しく解説。仲介手数料が一目で分かる早見表もご紹介します。
これを読めば、家を売却する際の費用面での不安が解消されるでしょう。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「IELICO(イエリコ)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
目次
1.家を売却した際にかかる費用・手数料の内訳

家を売却する際は、費用や手数料がおよそいくらかを知っておく必要があります。
まずは費用・手数料の目安を一覧で確認しましょう。
| 項目 | 詳細 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産の仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料 |
|
| 印紙税 | 売買契約書に貼付して納める税金 | 数千円〜数万円(売買価格によって異なる) |
| 譲渡所得税 | 家の売却益に応じて課される税金 |
|
| 登記費用 | 抵当権抹消登記費用 登録免許税+司法書士報酬 |
|
| 住宅ローンの返済手数料 | 住宅ローンを一括返済する際の手数料 | 金融機関や手続き方法によって異なる |
| その他の費用 | 解体費用や測量費用、引っ越し費用など |
|
売却時にかかる諸費用の中でも、大きくなりやすいのが仲介手数料です。
そこでこの記事では、失敗なく支払いができるよう、仲介手数料について詳しく解説していきます。
2.仲介手数料はいくら?相場と仕組みを解説

不動産会社に仲介を依頼して家を売却すると、売買成立の報酬として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の相場と仕組みを順番に確認していきましょう。
- 仲介手数料の早見表
- 上限が法律で定められている
- 家の売却手数料の支払いタイミング
- 上限以上となる例外ケース
2-1.仲介手数料の早見表
まずは、仲介手数料がどのくらいかかるかの目安として、仲介手数料の早見表をご紹介します。
| 取引価格 | 仲介手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円 | 19.8万円 |
| 500万円 | 23.1万円 |
| 1,000万円 | 39.6万円 |
| 2,000万円 | 72.6万円 |
| 3,000万円 | 105.6万円 |
| 4,000万円 | 138.6万円 |
| 5,000万円 | 171.6万円 |
| 7,000万円 | 237.6万円 |
| 8,000万円 | 270.6万円 |
| 1億円 | 336.6万円 |
上記の仲介手数料がどのように算出されるか、詳しく解説していきます。
2-2.上限が法律で定められている
仲介手数料は法律で上限が以下のように定められています。
| 売買価格 | 仲介手数料 |
|---|---|
| 200万円以下の場合 | (売却価格×5%)+消費税 |
| 200万円を超え400万円以下の場合 | (売却価格×4%+2万円)+消費税 |
| 400万円を超える場合 | (売却価格×3%+6万円)+消費税 |
たとえば、売却価格が1,000万円の場合は以下のように計算します。
ただし、上記はあくまで上限額です。
上限を超えなければいくらでも構わないこととなっています。
不動産会社にとって、仲介手数料は重要な利益です。
そのため、実際には上限に近い金額を支払うケースが多くなっています。
2-3.仲介手数料の支払いタイミング
仲介手数料を支払うタイミングは、以下の3パターンのいずれかです。
- 売買契約時と決済時に半分ずつ
- 売買契約時に全額
- 決済時に全額
中でも、1つ目の売買契約時に半分、決済時に半分と分けて支払うのが一般的です。
どのように支払うかは不動産会社次第なので、必ず契約前に確認しておきましょう。
2-4.上限以上となる例外ケース
仲介手数料は法律で上限額が定められていますが、以下のようなケースでは、上限以上となることがあります。
- 売主の特別な依頼によって発生した費用
- 「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」適用ケース
それぞれ見ていきましょう。
2-4-1.売主の特別な依頼によって発生した費用
仲介手数料は、不動産会社が通常行うサービスに対して支払う費用です。
そのため、売主からの要望によって発生したイレギュラーな費用については、別途費用を請求できるとされています。
たとえば、遠方にある物件を売却する場合の交通料や、特別な広告を出すための費用などが該当します。
2-4-2.「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」適用ケース
売買価格400万円以下の不動産売買については「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が適用されます。
郊外の空き家など、低価格の不動産売買については仲介手数料の額が安くなります。
こうした物件を不動産会社が積極的に取引したがらない問題があることへの対策として定められました。
特例を適用した場合の仲介手数料の額は、18万円+消費税です。
3.その他家の売却にかかる費用一覧

ここまで仲介手数料の目安を確認していきました。
仲介手数料以外にかかる費用は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書に貼付して納める税金 |
| 譲渡所得税・住民是 | 家の売却益に応じて課される税金 |
| 登記費用 | 抵当権抹消登記費用 登録免許税+司法書士報酬 |
| 住宅ローンの返済手数料 | 住宅ローンを一括返済する際の手数料 |
| その他の費用 | 解体費用や測量費用、引っ越し費用など |
それぞれの費用について、詳しく見ていきましょう。
3-1.印紙税
印紙税は売買契約書に貼付して納める税金です。
売買契約書に貼付する印紙は、売買契約の金額ごとに以下のように定められています。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を超え 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
なお、上記軽減税率が適用されるのは現在のところ令和6年3月31日までです。
ただし、これまでも数回にわたり期限は延長されているため、今後も継続される可能性があります。
3-2. 譲渡所得税
家を売却すると、その利益額に応じて譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税は、以下の計算式で納税額を求めます。
- 課税譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除
- 納税額=課税譲渡所得✕税率
なお、譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間に応じて、以下のように定められています。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
3-3.登記費用
登記費用のうち、所有権移転登記費用は一般的に買主の負担です。
一方、住宅ローンを完済したときに行う抵当権抹消登記費用は売主が負担する必要があります。
登記費用の内訳は、登録免許税+司法書士報酬です。
このうち、抵当権抹消登記の登録免許税は1筆につき1,000円です。
土地と建物でそれぞれ1筆ずつの抵当権を抹消する場合は、2筆で2,000円必要になります。
一方、司法書士報酬は依頼する司法書士によって異なり、相場は1~3万円程度です。
抵当権を抹消するためには、必要書類を揃えて法務局に行き、手続きします。
自分で手続きする場合は司法書士報酬を支払う必要がありませんが、手間と時間がかかることに注意してください。
3-3. 住宅ローンの返済手数料
売却する家に住宅ローンが残っている場合、一括返済のために手数料を支払わなければなりません。
一括返済手数料の額は、利用する金融機関によって異なりますが、例えば、三菱UFJ銀行の場合は以下のようになっています。
| インターネット | 16,500円 |
|---|---|
| テレビ窓口 | 22,000円 |
| 窓口 | 33,000円 |
参照:三菱UFJ銀行
また、上記以外に保証会社事務手数料として11,000円が必要です。
3-5.その他の費用
その他、物件によっては以下のような費用がかかるケースがあります。
- 解体費用
- 地下埋設物撤去費用
- 測量費用
- ハウスクリーニング
- 引っ越し費用
家を売却するにあたり、建物を解体する場合には、解体費用を支払う必要があります。
また、解体の際に、家の下に埋設物が埋まっていた場合には別途撤去費用がかかるため注意してください。
その他、家の売却前に、隣地との境界線を確定しなければ売却できないのが一般的です。
境界を確定するためには測量を実施しなければなりません。
さらに、引っ越しの際にはハウスクリーニングや引っ越し費用も必要となるため、あらかじめこれらの費用を見込んでおくことが大切です。
4. 家の売却時にかかる費用を安くする方法

ここまで、家の売却時には仲介手数料をはじめ、さまざまな費用がかかるとお伝えしてきました。
この章では、家の売却時の費用を安くする方法を3つご紹介します。
- 仲介手数料の値引き交渉を試みる
- 特例を利用する
- リフォームせずに売る
詳しく見ていきましょう。
4-1.仲介手数料の値引き交渉を試みる
仲介手数料は法律で定められた上限以下であればいくらでも構いません。
そのため、値引き交渉してみるのも一つの方法です。
ただし値引き交渉をするなら、媒介契約前にしないといけません。
媒介契約時の契約書には、仲介手数料の金額が記載されているため、あとから定められた金額を覆すことは難しいのです。
また、交渉の結果値引きしてくれたとしても、不動産会社が熱心にサポートしてくれなくなる可能性もある点には注意が必要です。
不動産会社としても、広告費や人件費を割いて売却活動を行っており、より多くの仲介手数料を支払ってくれる人が別にいれば、そちらに力を入れるでしょう。
なお、不動産会社の中には仲介手数料を無料や半額にしているところもあります。
こうした不動産会社は、本来は仲介手数料に含まれるはずの広告費を別途請求するなど、何らかの細工をしている可能性が高いので注意が必要です。
4-2.特例を利用する
家を売却して利益が出ると、利益額に応じて税金を納める必要があります。
この税金には一定の要件を満たせば特例の適用が可能です。
具体的には以下のような特例があります。
- 3,000万円特例
- 特定居住用財産の買い換え特例
- 居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除
- 10年超所有軽減税率の特例
ひとつずつ見ていきましょう。
4-2-1.3,000万円特例
3,000万円特例はマイホームを売却するなど一定の要件を満たすことで適用を受けられるもので、最大3,000万円分の控除を受けられます。
たとえば家を3,000万円で売却して、取得費や譲渡費用の合計が2,000万円だった場合は、差額の1,000万円に対して税金が課されます。
しかし、3,000万円特別控除の適用を受ければ、納税額をゼロにできるのです。
節税効果の高い特例なので、売却して利益が出そうであれば、適用可能か確認してください。
4-2-3.居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除
居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除は、マイホームを売却して損失が出た場合に、損失を損益通算と繰越控除できる特例です。
通常、不動産を売却したときの譲渡所得税は、給与所得などとは別の分離課税のため、他の所得と合算することができません。
ところが、本特例の適用を受けることで、赤字が出たときに給与所得など他の所得と相殺できるのです。これを「損益通算」と呼びます。
損益通算してもなお損失が残る場合は、売却した土地の翌年以降3年間まで繰越が可能です。
4-2-4.10年超所有軽減税率の特例
「10年超暑中軽減税率の特例」は、マイホームを売却することなど一定の要件を満たしたうえで、売却した家の所有期間が10年超だった場合に適用できる特例です。
本特例の適用を受けると、課税所得6,000万円部分まで以下の税率で計算できます。
| 特例 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 10年超所有の軽減税率 | 10.21% | 4% | 14.21% |
なお、本特例は3,000万円特例と併用可能です。
4-3.リフォームせずに売る
売却する家が傷んでいるような場合には、リフォームして売却を検討することもあるかもしれません。
しかし、リフォームには費用がかかります。
また、リフォームに要した費用を売却価格に上乗せできるとは限りません。
リフォームしたほうが高額売却を見込める場合に限ったほうが賢明です。
実際にリフォームするかどうかは、経験豊富な不動産会社の担当者と相談しながら決めることをおすすめします。
5.仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ばないようにしよう

仲介手数料は、家を売却するときの費用の中でも多額になりがちです。
とはいえ、仲介手数料を抑える目的で不動産会社を選ぶことは、おすすめできません。
家の売却を成功させるためのポイントは、仲介手数料の安い不動産会社よりも、優秀な不動産会社との契約です。
複数社に査定を依頼する際に便利なのが、NTTデータグループが運営する一括査定サイト「IELICO(イエリコ)」です。
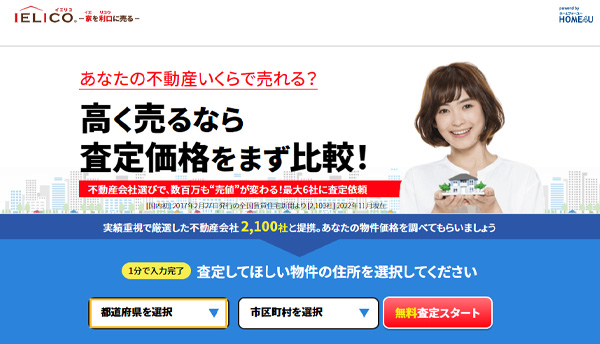
イエリコはカンタンな情報を入力するだけで、全国の優良な不動産会社2,500社のなかから、6社を選んでまとめて査定依頼ができます。
ぜひイエリコで比較して、信頼できる優秀な不動産会社を見つけてください。
この記事のポイントまとめ
家を売却する際にかかる主な費用・手数料は以下の通りです。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 譲渡所得税
- 登記費用
- 住宅ローンの返済手数料
- 測量費
- 解体費用
- インスペクション(建物状況調査)費用
- 引っ越し費用
詳しくは「1.家を売却した際にかかる費用・手数料の内訳」をご覧ください。
仲介手数料の相場と仕組みの概要は以下の通りです。
- 仲介手数料は法律で上限が定められている
- 多くの場合、仲介手数料の相場は法律で定められた上限程度
- 依頼主の特別な依頼による広告など上限以上となるケースもある
詳しくは「2.仲介手数料はいくら?相場と仕組みを解説」をご覧ください。
家の売却時にかかる費用を安くするには以下のような方法があります。
- 仲介手数料は値引き交渉することもできる
- 3,000万円特例など利用することで譲渡所得税の額を安く抑えられる
- リフォームしても価格に転嫁できないこともあるため慎重に判断する
詳しくは「4.家の売却時にかかる費用を安くする方法」をご覧ください。
仲介手数料が安いのに越したことはありませんが、安易に値下げ交渉するのには注意が必要です。
- 仲介手数料の値引き交渉は可能
- しかし、値引きすることにより積極的に活動してくれないリスクがある
- 信頼できる不動産会社を見つけて気持ち良く仲介手数料を支払った方がトータルでお得になることも多い
詳しくは「5.仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ばないようにしよう」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点





