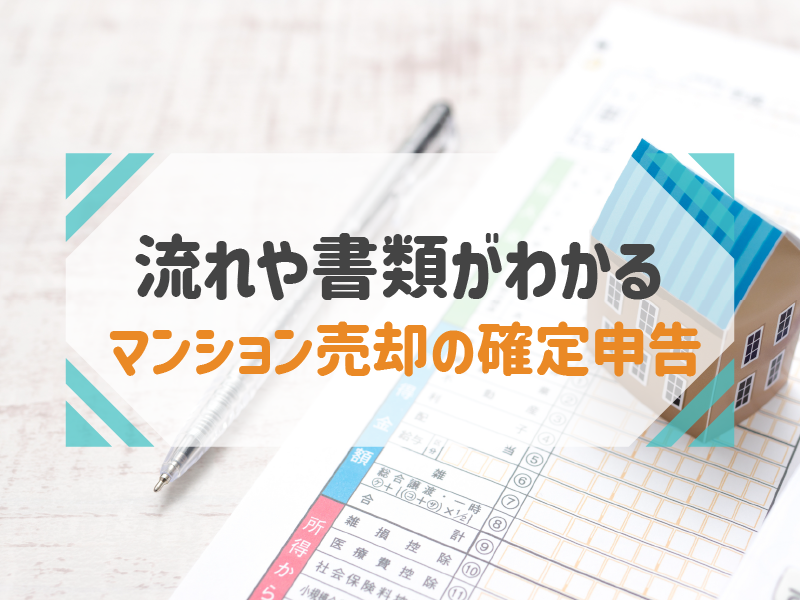マンションの売却後には、状況によって確定申告をしなければならないケースがあります。万が一手続きを忘れたり申告漏れがあったりしますと、延滞税などのペナルティが生じてしまいますので、売却計画を立てる段階できちんと仕組みを理解することが大切です。
今回はどのようなケースで確定申告が必要となるのかを解説したうえで、手続きの流れや必要書類を詳しく紹介します。また、マンション売却時に発生する税金の計算方法や特例についても併せて確認していきましょう。
- 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
- 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格”を見つけましょう
- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます
目次
1.マンション売却で利益が出たら確定申告を行う

マンションを売却したときに確定申告が必要なのは、「売却益」が出た場合です。
売却益が発生したときには、「譲渡所得」として扱われて課税の対象となるため、確定申告を行ったうえで納税をしなければなりません。
ただし、不動産売却における「売却益」は、売却できた金額そのものを指すわけではありません。売却代金から購入費用や売却にかかった費用を差し引き、そのうえで利益があったときに、初めて「所得がある」とみなされるのです。
確定申告の時期は毎年2月の中旬から3月中旬にかけて設けられますので、マンションを売却した翌年の期間内に、正しく申告・納税を済ませる必要があります。
なお、申告・納税を怠った場合にはペナルティが発生します。それが「無申告加算税」と「延滞税」です。
「無申告加算税」は申告を怠った場合のペナルティであり、申告するべきだった税金の額に定められた税率をかけた額が追加発生することになります。「延滞税」は納税を怠った場合に発生します。申告期限日の翌日から納付するまでの日数に応じて課せられるものです。
確定申告を期限までに行わずに税金を遅れて納付した場合には、「本来納めるべきだった税額+無申告加算税+延滞税」を納めなければいけません。
所得が増える可能性があるときには、事前に必要な知識と、マンション売却の確定申告時に必要な書類を準備しておきましょう。
2.マンション売却で損失が出ても確定申告を行うほうが良い

マンションを売却して損失が出た場合には、基本的に確定申告を行う必要はありません。
しかし、確定申告を行うことで、売却損を給与所得など他の所得と合算して計算できる特例の利用が可能です。
すべての所得を合算できれば、課税所得そのものを引き下げることになり、結果として所得税や住民税といった税負担を軽減できます。そのため、マンションの売却で損失が出てしまったとしても、確定申告を行うほうが良いと言えます。
確定申告を行うことで、以下の特例を利用できます。
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
- マイホームを買い換えた場合の損益通算および繰越控除の特例
前者は住宅ローンの残っているマイホームが残債以下の価格で売却され、それによって損失が生じたときに、一定の要件を満たすことで利用できる特例です。また、後者はマイホームの住み替えによって損失が生じたときに、一定の要件を満たすことで利用できます。
これらの特例は、どちらも損失とその他の所得(事業所得や給与所得など)を損益通算できる仕組みです。例えば、給与所得が700万円あり、マンションの売却損が100万円であった場合には、損益通算をして所得を600万円までとみなします。
会社員などで既に所得税を納めていれば、還付されるケースもありますので、損失が出たときには積極的に利用したい制度です。
また、1年間で損益通算しきれなかった分については、翌年以後3年間にわたって引き続き繰越控除をすることができます。
これらの特例を利用するためには、確定申告を行う必要がありますので、売却益、売却損の有無にかかわらず確定申告の手続きを行ったほうが良いでしょう。
『 不動産売却で確定申告を行う手順・必要書類・税金の計算方法 』では、確定申告が必要なケースについてもより詳しく解説しています。
3.マンション売却時の確定申告の流れ

会社員などの給与所得者では、ふだんは自分で確定申告を行う機会がないという方も多いかもしれません。しかし、手順をきちんと押さえておけば、不慣れな方でも正しく申告手続きを済ませることができます。
- 確定申告書を作成する
- 税務署に書類を提出する
- 納付期限までに納税を行う
3-1.確定申告書を作成する
不動産売却後の確定申告は、税務署や国税庁のホームページなどで入手できる「確定申告書B様式」を使って行います。国税庁の「確定申告書等コーナー」を利用すれば、オンラインでも申告ができるのに加えて、記入内容を案内してもらえたり、金額などを自動で計算してもらえたりするので便利です。
3-2.税務署に書類を提出する
必要書類をそろえたら、確定申告書とともに期日までに税務署へ提出します。提出方法は「直接所轄の税務署窓口まで持っていく」、「郵送する」、「e-Taxでデータを送る」の3つがありますので、状況に応じて選びましょう。
ただ、確定申告の時期は税務署が混み合ってしまいますので、自分で書類の準備を行える方は郵送かe-Taxを利用するのがおすすめです。
e-Taxは24時間いつでも申請できるのがメリットであり、還付がある場合には通常よりも早く処理してもらえます。
3-3.納付期限までに納税を行う
売却時に課税される税金のうち、「所得税」と「復興特別所得税」は、確定申告の期限内に納付する必要があります。
納付の方法には、「現金での納付」のほかに、金融機関の口座から引き落とされる「振替納税」、「クレジットカード納付」「e-Tax」などがありますので、適した方法を選びましょう。
また、還付を受ける場合には、申告書に記入した金融機関の預金口座に振り込まれます。一方、売却時の税金のうち「住民税」は、翌年度の5月以降に市町村から納付書が送られ、その後に一括あるいは年4回に分割して納める必要があります。
税金の種類によって支払いのタイミングは異なり、住民税は遅れて納付時期が訪れますので、見落としがないように注意しましょう。
なお、不動産売却全体のお金の流れについては、以下の記事をご覧ください。
4.マンション売却時の確定申告で必要な書類

確定申告時にはさまざまな書類が必要になりますので、漏れがないように注意しながら準備しましょう。主な必要書類は以下の通りです。
- 確定申告書B様式
- 分離課税用の申告書
- 譲渡所得の内訳書
- 売買契約書のコピー
- 各種領収書
- その他特例を使う場合に必要な書類
4-1.税務署から取得する書類
必要書類のうち「確定申告書B様式」「分離課税用の確定申告書」「譲渡所得の内訳書」は税務署から入手することができます。
直接足を運んで取得するほか、税務署のホームページでもダウンロードできますので、申告時期が訪れたら早めに入手しておきましょう。
4-2.自分で用意する書類
確定申告時には、不動産の購入時・売却時それぞれの売買契約書が必要となります。また、購入時・売却時の仲介手数料や印紙税などの領収書も、コピーで問題はないので用意しておきましょう。
これらの書類には、不動産を購入・売却するのにどのくらいの費用がかかったのかを客観的に証明する役割があります。不動産売却時には、売却代金からさまざまな経費を差し引くことができますので、できるだけ細かく関連書類をそろえておくことが大切です。
5.確定申告のためにマンションの売却益を計算する方法

不動産を売却するときには、売却によって「利益が出るか出ないか」が1つの重要なポイントとなります。マンション売却後の確定申告で税金の計算が必要になるからです。不動産売却における利益(譲渡所得)は以下の計算式で求めることができます。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
取得費は簡単にいうと「購入にかかった費用」であり、譲渡費用は「売却にかかった費用」のことです。そのため、譲渡所得を計算するときのイメージとしては、「売却代金から購入費や経費を引いて利益を割り出す」ものだと考えておいて問題ありません。
しかし、取得費や譲渡費用の計算方法はやや複雑ですので、丁寧に理解を深めていく必要があります。ここでは、1つずつ手順を追って計算方法を見ていきましょう。
- 譲渡価額の計算
- 取得費の計算
- 譲渡費用の計算
- 譲渡所得税の計算
5-1.譲渡価額の計算方法
譲渡価額とは不動産を売却できた金額のことです。正確には「売却価格+固定資産税の清算金」で計算しますが、固定資産税清算金は数万円~数十万円程度ですので、金額全体から見れば比較的に小さな割合です。
5-2.取得費の計算方法
取得費とは、不動産を購入するためにかかった費用のことであり、「土地の購入価格+(建物の購入価格-減価償却費)+購入にかかった各種費用」で計算します。
不動産においては、基本的に土地の価値は経年によって劣化しないものとみなされます。
一方、建物については年数が経過するごとに確実に価値が減少していくため、所有期間分の価値を売り主が消費したと考えられます。そのため、建物の代金を経費としてそのまま差し引くことはできません。
そこで使われるのが「減価償却」と呼ばれる計算方法です。減価償却費の計算方法は建物の「用途」や「構造」によって異なり、居住用の鉄筋コンクリートマンションの場合は以下のように計算します。
減価償却費=建物購入価格×0.9×0.015×経過年数
また、取得費には「購入時の仲介手数料」や「印紙税」「不動産取得税」「登記費用」なども加えることができます。取得費を計算する手順についてまとめたのでご確認ください。
- 購入価格を調べる
- 購入価格のうち、土地と建物の割合を明確にする
- 購入にかかった関連費用を計算する
- 建物の減価償却費を求める
- 以下の式で取得費を求める
取得費=土地の購入代金+(建物の購入代金-減価償却費)+購入時関連費用
なお、取得費がわからない場合は、「概算取得費」として売却価格の5パーセントを取得費に置き換えることも可能です。ただし、ほとんどのケースで実際の取得費よりも大幅に低くなってしまいますので、できるだけ正確に費用を計算することが大切です。
5-3.譲渡費用の計算方法
譲渡費用とは不動産を売却するためにかかった費用のことであり、以下のような費用が含まれます。
- 売却時の仲介手数料
- 売り主が負担した印紙税
- 貸家を売るために支払った立ち退き料
- 土地を売るために建物を取り壊した場合の取り壊し費用と、取り壊した建物の損失額
- 違約金 など
あくまでも「売るために直接かかった費用」を指すため、修繕費や固定資産税など、資産の維持・管理にかかった費用は含まれない点に注意が必要です。
5-4.譲渡所得税の計算方法
前述のように、「譲渡価額」から「取得費」や「譲渡費用」を差し引いて利益があった場合には、譲渡所得があったものとみなされ、譲渡所得税の課税対象となります。譲渡所得税は「譲渡所得×税率」で計算することができますが、物件の所有期間によって税率は以下のように異なります。
| 譲渡所得の区分 | 税率 |
|---|---|
| 短期譲渡所得(所有期間5年以下) | 39.63%(所得税30.63%※+住民税9%) |
| 長期譲渡所得(所有期間5年超) | 20.315%(所得税15.315%※+住民税5%) |
※2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までは、復興特別所得税として所得税額×2.1%が課されます。
短期譲渡所得の税率が長期譲渡所得の2倍近くに設定されているのは、投機目的の短期売買を抑制するためとされています。短期売買が加速化しますと、不動産市場が急激に不安定になってしまうため、通常の売却に比べて高い税率が設けられているのです。
このとき、1点注意しておきたいのは、所有期間の計算方法です。譲渡所得の区分においては、「売却した年の1月1日」を所有期間の基準として考えますので、取得してから5年程度のマンションを売却するときにはタイミングをきちんと見極めることが重要となります。
例えば、2016年6月に購入したマンションを2021年の12月に売却した場合、実際の時間では5年以上の年数が経過しています。しかし、2021年の1月1日を基準とするとまだ5年は経過していないため、短期譲渡所得となってしまうのです。
短期譲渡所得と長期譲渡所得では、税率に大きな違いが生まれますので、売却できるタイミングを逆算しながら計画を立てることが大切です。
6.確定申告のために譲渡所得をシミュレーションしてみよう

これまで見てきたように、譲渡所得税の計算方法は少し複雑ですが、1つずつ丁寧に求めていけば自分でも割り出すことができます。ここでは、いくつかの具体例をもとに、実際にシミュレーションしてみましょう。
なお、いずれも「居住用の新築鉄筋コンクリート造マンション」を購入し、数年後に売却するケースを想定しています。
- 購入額:3,500万円(土地1,500万円、建物2,000万円)
- 売却価格:3,000万円
- 固定資産税清算金:5万円
- 取得時の費用:200万円
- 譲渡費用:100万円
- 所有年数:8年
まず、売却価格と固定資産税清算金から譲渡価額を計算しますと、「3,005万円」となります。続いて、譲渡費用は明らかになっていますので、取得費を計算しましょう。
取得費を求める際には、土地と建物の購入金額を明確にしたうえで、建物の減価償却費を計算します。今回は居住用鉄筋コンクリート造マンションですので、計算式は以下の通りです。
2,000万円×0.9×0.015×8年=216万円
ここから、取得費は以下のように計算できます。
1,500万円+(2,000万円-216万円)+200万円=3,484万円
取得費が明らかになりましたので、次に譲渡所得を計算しましょう。
3,005万円-3,484万円-100万円=-579万円
このケースでは売却益が出なかったとみなされますので、「損失時の特例」を利用しない限り、確定申告は不要です。
- 購入額:3,500万円(土地1,500万円、建物2,000万円)
- 売却価格:4,200万円
- 固定資産税清算金:5万円
- 取得時の費用:200万円
- 譲渡費用:100万円
- 経過年数:8年
続いて、先ほどと取得費や譲渡費用などの条件を変えず、より高い価格で売却できたケースを見ていきましょう。
4,205万円-3,484万円-100万円=621万円
ケース2では譲渡所得が「621万円」となり、売却益が発生しました。このケースでは所有期間が8年の「長期譲渡所得」ですので、税額は以下のように計算します。
621万×20.315パーセント=126.2万円
マンションを売却する前に譲渡所得を計算するためには、おおまかな譲渡価格(物件の売却価格)を把握しておく必要があります。売却を本格的に検討しているのであれば、不動産会社に査定依頼を行い、どのくらいで売れそうか目安を算出してもらうと良いでしょう。
不動産の一括査定サービスIELICO(イエリコ)は、2001年に国内で初めて不動産の一括査定サービスを開始した、「不動産売却HOME4U(ホームフォーユー)」のサービスの1つです。20年以上にわたるサービス提供において、累計で45万件以上の査定依頼の実績があります。
使い方はとてもシンプルであり、入力フォーマットに売りたいマンションの条件や特徴を記載しますと、厳選された不動産会社の中から相性の良い依頼先を紹介してもらえる仕組みです。提携する2,100社の不動産会社は、すべて独自の審査基準で厳選されており、査定依頼を行うときには最大6社までを同時に選択できます。
一括査定により、複数の査定結果を効率的に比較できますので、適正価格や依頼に適した会社を見極めやすくなるのが特徴です。また、イエリコは情報サービス事業で業界最大手のNTTデータグループが運営を行っています。
長年にわたって培ってきたセキュリティ技術によって、個人情報の取り扱いなど安心して利用していただける環境を整えています。マンションの売却を考えるときには、IELICOを活用して最適な不動産会社を見つけてみましょう。
7.マンション売却時の確定申告で活用できる税金の特例

マイホームとして居住していたマンションを売却するときには、一定の要件を満たすことで、所得の控除や税率の軽減といった特例を利用できます。ここでは、マイホーム売却時に活用できる特例の種類と仕組みを見ていきましょう。
- 3,000万円の特別控除
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換え特例
7-1.3,000万円の特別控除
マイホームの売却時に一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最高で「3,000万円」を控除できる制度です。例えば、取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得が1,000万円となった場合、長期譲渡所得なら「約203万円」、短期譲渡所得なら「約396万円」もの税金がかかってしまいます。
しかし、この特別控除を利用すれば譲渡所得がゼロになりますので、税金が発生しません。このように、譲渡益から3,000万円をそのまま差し引けますので、各種特例の中でも特に節税効果が大きな制度といえます。
また、特例を受けるためには以下の要件を満たす必要がありますが、マイホーム売却では自然と該当しているケースが多いです。
- 居住している家屋やその家屋とともに譲渡する敷地の売却の場合
- 売った年の前年及び前々年に売却時の各種特例を利用していないこと
- 転居している場合は住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すること
- 売り手と買い手が親子や夫婦などの特別な関係でないこと
7-2.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
前述の「3,000万円の特別控除」を利用しても譲渡所得がプラスになる場合は、次に「所有期間10年超の軽減税率の特例」を検討してみましょう。
この特例は、以下の要件をすべて満たしている場合に利用することができます。
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること
- 売却した年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと
- マイホームの買い替え特例などを利用していないこと(※)
- 売り手と買い手が親子や夫婦などの特別な関係でないこと
※3,000万円の特別控除は併用可能
特例の内容は、所有期間が10年を超えたマイホームを売却した場合に、譲渡所得のうち「6,000万円以下の部分」が本来の長期譲渡所得よりも低い税率で計算されるという仕組みです。具体的には、6,000万円以下の部分が「14.21%」、6,000万円以上の部分が本来の「20.315%」で計算されます。
7-3.特定の居住用財産の買換え特例
この特例はマイホームの買い換えにおいて、「旧居の譲渡価額よりも新居の取得価額が高い場合」に利用できる制度です。具体的な仕組みは、売却する物件・購入する物件のそれぞれについて一定の条件を満たしていれば、売却によって発生した課税を「将来へ繰り延べできる」というものです。
繰り延べられた課税は、将来新居を売却するときまで持ち越すことができますので、すぐに負担をせずに済む点がメリットとなります。ただ、この特例で得られるメリットはあくまでも課税の繰り延べであり、所得の控除や税額の軽減があるわけではありません。
また、前述の「3,000万円の特別控除」とは併用できない点にも注意しましょう。そのため、新居の購入額と旧居の売却額によほどの差がない限りは、「3,000万円の特別控除」を利用したほうが有効なケースが多いです。
ここまでマンション売却時に利用できる税金の特例についてみてきましたが、より詳しく特例の内容や適用条件について知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
まとめ
マンションの売却後に確定申告が必要となるのは、原則として「売却益」が出た場合のみです。しかし、売却益とは単に売却代金を示すわけではなく、実際に計算するためには「取得費」や「譲渡費用」などの仕組みも詳しく理解しておく必要があります。
また、マイホームの売却においてはさまざまな特例を活用して、税金を大幅に抑えたり非課税にしたりすることも可能です。そのため、売却計画を立てる段階で、きちんと売却時の税金の仕組みを理解しておきましょう。
なお、「売却損」が出たときには申告の義務こそないものの、確定申告をすることでその他の所得と「損益通算」できる場合があります。このように、不動産売却後に確定申告を行うケースはとても多くありますので、必要書類と手順を把握して、滞りなく手続きを行える準備を進めましょう。
この記事のポイントまとめ
マンション売却において確定申告が必要なのは、「売却益」が出た時です。ただし、損失が出た場合でも確定申告を行った方がいいケースもあります。
詳しくは「1.マンション売却で利益が出たら確定申告を行う」をご覧ください。
マンション売却時の確定申告で必要な書類は、下記の6点です。
- 確定申告書B様式
- 分離課税用の申告書
- 譲渡所得の内訳書
- 売買契約書のコピー
- 各種領収書
- その他特例を使う場合に必要な書類
詳しくは「4.マンション売却時の確定申告で必要な書類」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
カンタン1分入力
最大6社にまとめて 売却査定依頼
人気記事
- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説
- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点
- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント
- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント
- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】
- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法
- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説
- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介
- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説
- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点